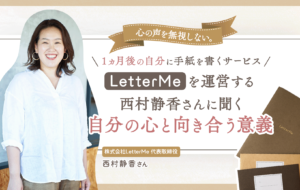介護は「これからどう生きたいか」を考え、深める機会になる。働く人と介護の付き合い方(Blanket・秋本可愛さん)

親の介護=大変・重い・複雑。20〜30代でバリバリ働いている人も、実はそんな漠然とした不安を感じています。誰もが仕事と介護を両立する「ワーキングケアラー」「ビジネスケアラー」になる可能性があるけれど、当事者ではない今、何をすればいいのか、何から学べばいいのか、わかりません。
「すべての人にカイゴリーダーシップを。」を掲げ活動するコミュニティ「KAIGO LEADERS」の発起人・秋本可愛さんは、「介護の前に、親も子どもも『これからどう生きたいか』を考えてみるのが大事」と話します。
大学時代に介護の現場で感じた違和感を出発点に活動を始めた秋本さんに、介護に対する不安の正体、誰にでも来る“その時”に備えてできること、いざというとき“介護を怖がらずに向き合うために必要な知識・視点”を伺います。

秋本可愛(あきもと・かあい)
1990年生まれ。山口県出身。大学在学中の介護現場でのアルバイトをきっかけに課題意識を抱き、2013年卒業と同年に、株式会社Join for Kaigo(現・株式会社Blanket)を設立。日本最大級の介護に志を持つ若者のコミュニティ「KAIGO LEADERS」発起人。2017年、東京都福祉人材対策推進機構の専門部会委員に就任。2022年より厚生労働省「介護のしごと魅力発信等事業:事業間連携等事業」企画委員を務める。
「介護の2025年問題」とビジネスケアラー
昔から「介護の2025年問題」と話題になってきました。
今年がまさにその年ですね。


秋本
私が介護の事業で起業した2013年には、すでに「2025年問題」と言われていました。
2025年は、日本で人口のもっとも多い「団塊の世代」全員が75歳以上、つまり後期高齢者になる年です。75歳になると約3割の方に介護が必要になると言われています。
介護の需要は高まる一方で、介護職の人手不足、財源不足、老老介護、看取り難民……、さまざまな課題が当時から指摘されていて、今も現実としてそれらの課題が残っているんです。
介護業界の人手不足、よく聞きます。


秋本
現状、もっとも大きい課題ですね。多くの業種で人手不足が生じていますが、介護業界はその傾向が顕著です。
最近、世の中では物価高騰と賃上げが進んでいますが、介護業界はいわゆる売上が介護保険のルールとして決まっているので、賃上げを急にするのも難しくて……。
構造上、解決が難しいんですね。


秋本
ニーズはあるのに人を採用できなくて倒産してしまう施設があるぐらい、厳しい状況です。
また、私が学生時代に働いていた介護施設は、職員の入れ替わりが激しかったですね。どんどん人が辞めていくことは課題だと感じました。
厳しい……。


秋本
ただ、いいお話もあるんです。
2000年に介護保険ができたときは、介護職が55万人しかいなかったところから、今は約212万人まで増えているのです。

そんなに増えているんですね!


秋本
ちなみに、介護業界の離職率は全産業の平均よりも低いんです。睡眠や排泄のセンサー、リフトなどのテクノロジー導入によって、働きやすい職場づくりも進んでいます。
ただ、それ以上に介護のニーズが増えており、追いついていないんですね。そのため、まだまだ人手不足ではあります。
なるほど!
とはいえ、まだ人手は足りないんですね。そんな時代で、自分の親に介護が必要になったときが不安です。仕事はどうなってしまうんでしょう……。


秋本
仕事と介護の両立に悩む方は多いですね。仕事と介護を両立している人は「ワーキングケアラー」や「ビジネスケアラー」と呼ばれます。
日本は、家族の介護の話を職場でする文化・風土がまだ十分に根付いておらず、話しづらいのも悩みやすい要因かもしれません。
確かに相談しやすい組織ばかりではないですよね……。


秋本
ただ、蓋を開けてみれば、他にも同じように介護のお悩みを抱えている人も本当はいるはずなんですけどね。
また「自分のキャリアに影響してしまうのではないか」「自分がやっていた仕事に次はアサインしてもらえないのではないか」といった不安感を抱く方もいます。
話しづらさの原因はどこにあるんでしょうか?


秋本
日本では、介護は家族が担うべきだという価値観もまだまだ根強いですから。
たとえば、北欧では「介護は社会が担うべき」という考えが強く、介護は自治体が施設・在宅ともにサービス提供を行っています。高い税率を払う対価として充実した福祉サービスを受けられる環境があるんです。
介護のために仕事を辞め、不安が強くなる
そもそも秋本さんはなぜ介護業界に関わり始めたんですか?


秋本
学生時代、介護施設でアルバイトをしたことがきっかけです。宿泊もできるデイサービスで約2年間働いていました。
食事から入浴、排泄の介助、日中のさまざまな活動の支援まで現場の仕事は一通り経験させていただきました。夜勤にも入っていました。
しっかりと働かれていたんですね。介護のどんな点に魅力を感じたんですか?


秋本
デイサービスに、ご家族も困り果てているぶっきらぼうなおじいちゃんがいたんです。でも、関係性を築いていくと、徐々にコミュニケーションを取れるようになっていったりする。
認知症などの症状で見えにくくなっていた“本当のその人”が見えるようになったりすると、嬉しいですよね。そういうところに介護のおもしろさを感じました。
一方で、衝撃を受けたこともあって……。
はい。


秋本
あるおばあちゃんが「早く死にたい」と言っているのを聞いたんです。「生きていることが申し訳ない」と……。
人生の終わりに、多くの人が通る道である介護において、自分が生きていることを肯定できない。そのことがすごく悲しいと思いました。
それは心が痛みますね……。


秋本
あと当時、いろいろな介護のイベントに参加している中で出会った方なのですが、私が力になれなかったご家族が一番印象に残っています。
仕事と介護の両立を諦めて、「これから親の介護をするために仕事を辞める」とおっしゃっていた方がいたんです。
連絡先を交換したので、やり取りだけは続けていました。そして、実際に仕事を辞め、介護を始めてから、私に対してのメッセージがものすごく長い文章になっていったんですよね。
どんなメッセージが……?


秋本
仕事を辞めてまで介護にコミットしたものの、経済的な不安が生じたり、お母様と2人きりの閉鎖的な空間で精神的な負担が生じたり……。
だんだん不安や悩みが強くなって、長文で伝えてくれていたのですが、私はメールを返すことぐらいしかできませんでした。

負担を下げるために仕事を辞めたのに……。


秋本
そうなんです。
仕事と介護の両立が難しいからその選択をされたと思うのですが、実際には両立するよりももっと負担が増えてしまうこともあるんですね。
「できるだけ親の介護はやらないぞ」と決めている
仕事と介護の両立に悩む方は多いとのことですが、ビジネスパーソンが身近な介護を考える上で、どんな心構えがおすすめですか?


秋本
一番重要なマインドセットは、家族で抱え込まずアウトソースすることです。
たとえば、私は介護の知識が一般の人よりはあるはずなんですけど、いろいろ見た上で「できるだけ親の介護はやらないぞ」と決めています。
「やらないぞ」……?


秋本
もちろん介護をやりたい人には『やる』という選択肢もあると思いますし、生きがいのように感じて取り組んでいる方もいらっしゃいます。そうやって、介護を自ら望んでやるならいいんです。
でも、仕事を辞めて介護をする選択した人の実際のところは、精神的にも、身体的にも、経済的にも負担感があがったというデータがあります。望んでいない場合、関係性が悪くなっちゃうケースも多いんですよね。
なぜですか?


秋本
親とは別に、ビジネスパーソンのみなさんにもそれぞれの人生がありますから。
介護はいろいろな負担があって大変な上に、家族の介護を優先して自分のキャリアを諦めることにもなってしまったりもします。
なるほど。ネガティブな気持ちが溜まっていくと、そういう状況をつくった介護自体がつらくなりますよね。


秋本
家族の介護は、平均して5年以上続くと言われており、なかには10年以上にわたる方もいらっしゃいます。親の存在が負担となる関係性は、健全ではないと思うんですよね。
また、フェーズによって介護の大変さは全く異なります。たとえば、初期のよく動ける認知症の方への介護と、全介助が必要な方への介護はまるで違うんです。
そこまで具体的なイメージができていませんでした……。


秋本
私は家族にも適切な距離というものがあると思っていて。
日本の価値観として「家族なんだから」「親なんだから」と思いがちです。また、介護施設を頼ること自体が「悪だ」「申し訳ないことだ」と思ってらっしゃる方がすごく多いのが現状なのかなと。
はい。
正直、ちょっと罪悪感を抱くというか……。


秋本
『介護はプロに、家族は愛を。』(石川治江著)という本がありますが、まさにその書名のようなバランス感覚が重要だと思います。
親からしても「子どもに迷惑をかけたくない」と、家族の介護を望んでいないケースも多いです。
なるほど。


秋本
ビジネスパーソンの方々は、自分の仕事を大切にしてほしいです。介護はできるだけアウトソースして、極力自分でやらない。
子どもがいるご家庭では、保育園や幼稚園に預けるのは当たり前の選択肢になっていますよね。介護でも、施設やサービスを使うのは当たり前だと思っていいんです。
確かに保育も介護もプロがいるわけですもんね。だから、「自分でやらない」。


秋本
はい。
それから、介護サービスをどうやって受け始めるのか、要介護認定とは何か、どこに相談行けばいいのか、ケアマネジャーとはどういう役割なんか、など最低限の知識は必要になります。
アウトソースするための準備として、知識が必要なんですね。


秋本
そうです。
「介護施設に全てお任せ」だけが選択肢ではありません。通所できたり、数日だけ滞在できたり、食事だけ手配できたりするなど、公的なものから自費のサービスまでさまざまなものがありますよ。
なかには、認知症の症状がある人たちでも、デイサービスで働き、有償ボランティアとして謝礼を受け取る仕組みもできています。
そんなサービスまで!


秋本
本人の意思や備えに応じて変わってくるので、地域にどんな選択肢があるのか、調べてみてもいいですね。
保育にベビーシッターや病児保育サービスがあるように、介護にもさまざまな選択肢があるんですね。

介護の前に「これからどう生きたいか」
とはいえ、お金もかかると思います。親が老後のためにどれくらい貯めているのかもわかりませんし……。
何から始めればいいのでしょうか。


秋本
まず家族との話し合いが大事なのですが、それが難しいですよね。
ひとつ言えるのは「介護の始まりはわからない」ということです。同じケアでも育児なら明確にわかりますが、介護は明確な始まりがないんです。
明確なはじまりがない?


秋本
認知症の前兆がゆるやかに始まっていたり、親が「子どもに迷惑をかけたくない」と思って体調の変化を黙っていたりして、気づいたときには差し迫った状況になって焦ることもあります。
だからこそ、日常的にコミュニケーションを取っておくのは大切だと思います。
そうですね。


秋本
大事なのは、介護について話すというよりも、「これからどう生きたいか」を一緒に考えることです。還暦や定年退職などの節目もいいきっかけになるはずです。
その上で、「介護始まったらどうしたい?」「ぶっちゃけ貯金どれぐらいあるの?」と話せるといいですね。
親が話したがらない場合はどうすれば?


秋本
ご自身の話からしてみてはどうでしょうか?
たとえば、「今後、こういうキャリアでやっていきたいと思ってるんだけど……」などと切り出すと、そこに絡めて親御さんの自身のことも話しやすくなるのではないでしょうか。


秋本
ちなみに2024年、私たちは経済産業省のプロジェクトとして、「家族謎解き体験 ただいまタイムループ」という、家族の会話を練習できる場を作る試みも行いました。
謎解き体験、面白そうです! いろいろな挑戦をされているんですね。


秋本
ありがとうございます。
介護はただ大変なだけではなく、余裕さえあれば、過去や家族に向き合って、関係が前進していく機会にもなるんです。
私たちの会社では「介護が、自分を、他者を、世界を好きになっていくプロセスになる」を掲げて活動をしています。まだまだ道半ばですが……。
介護と向き合う時、余裕があることが大切なんですね。


秋本
はい。だから安心して頼っていい、と思っていてほしいですね。
ちなみに、ある施設では要介護3以上で歩けない状態で施設に入居される方も多いのですが、適切な介護を受けている中で7〜8割の方が歩けるようになることもあります。
環境や関わる人によって、人は大きく変わります。専門職がきちんと関わることで、もう一回元気になるケースはざらにあって。
そんな事例もあるんですね。


秋本
介護=「寝たきりで最期を待つしかない」とイメージする方も多いかもしれませんが、そうとは限りません。介護にはいろんな良いケースがいっぱいあるので、それをもっと知ってもらえたらいいなと思います。
そして、親の人生だけでなく、自分の人生も大切にして、お互いの望みを叶えられる方法を探してみてほしいですね。

2025年8月取材
取材・執筆=遠藤光太
撮影=栃久保誠
編集=鬼頭佳代/ノオト