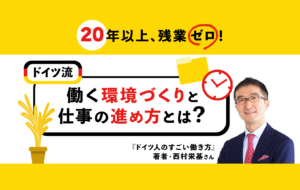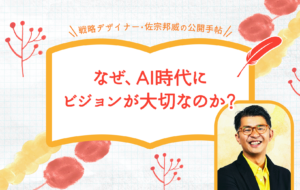朝、AIにタスク相談をするだけで働き方は大きく変わる。Zenmetry長友さんが見つけた仕事と暮らしの整え方

今日もやるべきことが終わらなかった……。そんな夕方は、もう気が滅入ってしまいますよね。
株式会社Zenmetry代表取締役の長友好江さんは、コロナ禍で体験した在宅勤務と育児の両立の苦労から、効率的なタスク管理の必要性を痛感。試行錯誤を重ね、新しいタスク管理の形を開発しました。
それが、朝15分を使ってAIの力を借りてタスク整理をすること。このメソッドが、多くの人の働き方や暮らしを大きく変えているんだそう。長友さんに、AIでのタスク管理が働く人の幸福度まで高める理由を聞きました。

長友好江(ながとも・よしえ)
株式会社Zenmetry代表取締役。早稲田大学政治経済学部卒業後、総合商社を経てIT業界へ転身。2020年のコロナ禍で在宅勤務と育児の両立に苦労した経験から、効率的なタスク管理の必要性を痛感。2021年にプログラミングを学び、2022年4月に起業。AIを活用したタスク管理ツール「Zenmetry」を開発し、多くのユーザーの働き方改革を支援している。最近は趣味で古武術を習うなど、仕事以外の時間も大切にする実践者でもある。
システムに振り回される人間たち
長友さんは「Zenmetry」というツールを開発し、タスク管理の新しい形を提案されていると伺いました。開発のきっかけを教えていただけますか?


長友
きっかけは2020年のコロナ禍です。当時IT企業の部長として働く中で、在宅勤務と育児の両立に苦労していました。
その時は、子どもが起きている昼間は仕事が進められず、寝かしつけ後に仕事をするという生活に疲れ果てていたのです。小さなストレスが積み重なって、ある日突然崩れてしまった。それが今の事業の原体験になっています。


長友
このエピソードは私の個人的な経験ですが、多くの人が同じような状況に直面していたと思います。
これまでも、様々なタスク管理の方法を試されていたそうですね。


長友
そうなんです。社会人になってから20年以上、数々の手帳やデジタルツールを試してきました。
でも、最初は張り切るのですが、どれも長続きしなくて……。古いタスクがたまっていくのを見て自分が嫌になる、という悪循環に陥っていました。
あるあるですよね。従来のタスク管理ツールでは、どんな点が使いにくかったのでしょうか?


長友
メールで来た依頼、Slackでの連絡、会議での約束事……。
何をいつまでにやるべきか、という情報が複数のツールにバラバラに存在していて、確認するだけでも一苦労でした。
それに、出てきたタスクを書き出して、別のツールへ登録すること自体も大変。そもそも、30秒で終わる返信のために別途登録するのは、直感的に「面倒くさい」と感じてしまうのは当然です。
わかります……!


長友
結局、多くの人は頭の中で覚えようとするのですが、それがまたストレスや罪悪感につながってしまう。
さまざまなシステムに人間が振り回されている状況を何とかしたいと思ったんです。
そこから新しいツール開発へと進んだのですね。


長友
はい。最初は、大量のメッセージを集約して重要なものだけを自動的にフィルタリングするツールがあればいいのでは?と考えました。
でも、Slackやメールが何百通も来る人に、「大事なメッセージ100通」を選抜したとしても、結局は本当に大切な情報の見落としが発生してしまう。結局、重要度をツールに判別させるのは、あまり本質的ではないんです。
次にメンションされたメッセージだけを表示するツールを考えましたが、すべてのツールを連携させるのは難しく、方針転換しました。
それでどうしたんですか?


長友
そうした試行錯誤を重ねた結果、今開発しているツールに行き着きました。
それが、Chrome拡張機能として、ブラウザ上でワンクリックでどこからでもタスクを作成・管理できるツール「Zenmetry」です。
今も改良を重ねていますが、まずはあらゆる場所にあるタスクを一つにまとめることに特化しています。


長友
ブラウザ上に表示されたタスクに関する文章を選択すると、AIがその内容を要約し、ブラウザの右側にまとめて表示されるんです。
もちろん、そのタスクをカレンダーに登録することもできます。これによって、どんな場面でもやることが発生したら瞬時にタスク化できるんです。
なるほど……! 転記したり、整理する手間がなくなるのはうれしいですね。

タスク管理の成功のカギは“細かく分ける”こと

長友さんはタスク管理方法についても情報発信されていますよね。
タスク管理をするうえで大切なことは何だと思いますか?


長友
重要なのは、タスクを細かく分解することです。たとえば、「取材の調整」といったタスクは、実は非常に曖昧です。
これを「候補日を出す」「日程を合わせる」「場所を決める」「必要な資料を準備する」といった具体的なステップに分解すると、何をすべきかが1秒で判断できる明確なタスクになります。


長友
私たちの脳は、あいまいで大きなタスクよりも、具体的で小さなタスクの方が取り組みやすいと感じるんです。
そのために、出勤前や仕事前に今日のタスクを洗い出して、それをAIと相談しながら5分−15分程度の作業に細分化します。
それらをカレンダーに入れ込めば、あとは淡々とそのタスクをこなしていくだけになるのです。
「やるだけの状態」になるのですね。


長友
そうなんです。
「この山は登れる」というイメージができると、先延ばしにしていた仕事に対しても「今からやってみよう」という前向きな気持ちになります。
その効果はどのようなものでしょうか?


長友
驚くほど大きいですね。たとえば、何カ月も先延ばしにしていた仕事を細分化したら、30分で終わったという方がいます。
人間の脳は、大きな塊のタスクを前にすると拒否反応を示すけど、「10分でできる」という小さなステップなら、意外とすんなり取り組めるんです。
それに、細分化することで「今日やらなくてもいいこと」に気づいたり、事前に手を打つべきことが見えてきたりします。
たとえば、どんなことですか?


長友
「取材後に記事を書く」というタスクを細分化すると、最初に「文字起こしのデータを準備する」というステップが出てきます。
やることが見えると、「この作業は、インターンの人にお願いできるかも」などと考えられるようになるんです。
タスク細分化の経験を積むと、仕事の見通しがよくなり、他の人に頼めることも増えていく。それにより、仕事の効率化だけでなく、チームのコミュニケーション改善にもつながっていくんです。
そうすると、チームビルディングの観点でもタスク管理が語れそうです。


長友
その通りです。タスク管理=個人の生産性向上というイメージがありますが、実はチームのコミュニケーションとも密接に関わっています。
タスクの細分化によって、明確な指示の受け渡しや進捗報告ができます。すると、追加の確認という手戻りが減るので、チーム全体の生産性が向上する。
また、タスクの可視化により「今何に取り組んでいるのか」がチーム内で共有しやすくなり、サポートが必要な場面でも助け合いやすくなるんですよ。
曖昧さをクリアにするAIの力
そういうタスクの細分化をする場面で、AIを活用されていると伺いました。なぜですか?



長友
それは、人間は完璧ではないからです。ビジネスでは、指示を出す側も受ける側も暗黙の了解で動いている場面がたくさんありますが、実際には認識のズレが生じてしまうことがある。
AIは、そのズレの隙間を埋めてくれる存在です。やることの細分化や確認事項の提案など、人間同士では面倒に感じる部分をカバーしてくれます。
具体的には、どんなふうにカバーしてくれるのでしょうか?


長友
AIにタスクの細分化をしてもらうと、「締切は?」「ページ数は?」「フォーマットは?」といった確認すべき事項をまとめてくれます。
そうすると、周りの確認しながら進める仕事においても、コミュニケーションがスムーズになるのです。
AIが見落としそうなポイントを教えてくれるのはいいですね。


長友
AIはゼロから膨大な量のタスク細分化を考えるのが得意なんです。人間にとって苦になる作業も、AIは苦もなくこなします。
あと、AIは怒りませんから(笑)。何度同じことを聞いても大丈夫です。特に新人や学びの過程にある人にとって大きなメリットだと思います。
さらに、AIは人間のように「これくらい言わなくても分かるでしょ」という態度を取りません。忍耐強く対応してくれるので、人間関係のストレスを減らしながら効率的に仕事を進められるんです。
一歩ずつ積み重ねる、習慣の力

何事も始めたは良いけど続かない……という方も多いかと思います。タスク管理を続けるコツはありますか?


長友
多くの人がタスク管理に挫折するのは、最初から「すべてのタスクを完璧に管理しよう」と思って始めるからです。
まずは小さく始めること、いきなり完璧にやろうとしないことが大切です。私がおすすめしているのは、まず朝5分だけ、今日絶対やらなければならないことを書き出すことです。
それだけでいいんですか?


長友
はい。「何かやらないといけないことがある……」という状態だけで、脳には負担なんです。なので、たった5分でも頭の中のタスクを外に出せると楽になるんです。
それを毎日続けることで、少しずつコツがつかめてきます。これは筋トレと同じ。毎日少しずつ続けることで筋肉がついていきます。
長友さんは、朝にどのようなルーティンを実践されていますか?


長友
私の場合、朝起きて10〜15分程度で今日取り組むべきタスクを細分化し、カレンダーに入れています。
大事なのは「タスク管理をいつやるか」を決めておくことです。朝起きたらすぐ、夜寝る前、通勤中など、自分の生活リズムに合わせて、必ず毎日同じタイミングでタスク管理の時間を確保することが習慣化のコツだと思います。
なるほど。やるのが当たり前という状態にするんですね。


長友
多くの人は「大きな目標に向かって長期的に歩まなければならない」と思いがちですが、それは挫折の元です。
むしろ、まずは日々の小さなタスクに分解して、少しずつこなせるようになること。そこから週単位、月単位の計画へと広げていく方が成功しやすいと思いますよ。
せっかくタスクに落とし込んでも、作業中に別のことが差し込まれて思い通りに進められないこともあります。そういった場合の対応のコツはありますか?


長友
メールなどの「外側からの中断」に対しては、集中する時間と確認する時間を決めることが、ひとつの対策です。
たとえば、ポモドーロテクニックのような形で、25分集中して5分休憩するというリズムを作ると効果的です。
25分間はタスクに集中するけど、休憩時間にはメールやメッセージを確認するという習慣をつければ、常に通知に振り回される状態から脱却できます。
タスクを整えると、人生が整う
ここまでのお話で、タスク管理の仕方を変えられるような気がしてきました。
タスク管理が変わると、生活全体も変わるものなのでしょうか?


長友
確実に変わります。私自身、朝のルーティンを大切にするようになりましたし、ずっと興味があった古武術を習い始めるなど、仕事以外の時間も充実させられるようになり、生活の質が上がったんです。
あと、タスク管理がうまくいくと、顔つきも変わるんですよ。このタスク管理法を実践してくださった方は、息子さんから「最近疲れていないね、元気になったね」と言われたそうです。
素敵なエピソードですね!


長友
ですよね。なので、まずは最初の一歩としては、毎朝または夜、今日やるべきことを書き出す習慣をつけてみてください。手帳でもメモアプリでも構いません。
AIを使うときも、最初は完璧を目指さず、ふわっとした問いかけでも続けることが大切です。使っているうちにコツがつかめてきますから。
AIを試してみるいい機会にもなりそうですね。


長友
一人でやるのが難しければ、誰かと一緒にやることもおすすめです。私たちも、朝15分でのタスク管理を実践する講座を定期的に開いており、たくさんの方にご参加いただいております。
そうやって小さな成功体験を積み重ねることで自信がつき、それが大きな変化につながります。一緒に、一歩ずつ進んでいきましょう。

2025年3月取材
取材・執筆=ミノシマタカコ
撮影=栃久保誠
編集=鬼頭佳代/ノオト