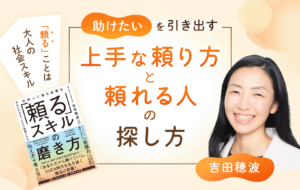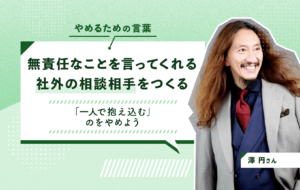創造性を発揮するために、ときには「無責任」になろう。哲学研究者・戸谷洋志さんと考える、職場における「弱い責任」

仕事を抱え込みすぎてパンクしそうになったとき、思い切って誰かを頼ることはできますか?
自分が一度引き受けた仕事なのだから、最後まで自分の“責任”でやらなければ――。この考えの根底にあるのが「自己責任論」です。
しかし、そのせいで本人がパンクしてしまったとしたらどうでしょう。さらに大きな不利益を招くことになりかねません。
哲学研究者の戸谷洋志さんは、自己責任とは異なる、もうひとつの責任のあり方として「弱い責任」という考え方を提案しています。「弱い責任」とはどのような責任なのか。また、責任のとらえ方を変えることで、日々の仕事はどう変わるのか。戸谷さんにお話を伺いました。

戸谷洋志(とや・ひろし)
立命館大学大学院 先端総合学術研究科准教授。「技術」と「責任」が研究テーマ。過去の著書に、『悪いことはなぜ楽しいのか』(ちくまプリマー新書)、『メタバースの哲学』(講談社)、『責任と物語』(春秋社)などがある。
自己責任が生産性を低下させる?
先生はご著書『生きることは頼ること 「自己責任」から「弱い責任」へ』(講談社)のなかで、「弱い責任」という新しい責任のとらえ方を提案されています。
このような新しい概念を生み出されたきっかけは何だったのでしょう。


戸谷
自己責任という考え方は、1980年代以降に日本に普及しました。この概念が広く注目を集めたのは、2004年のイラク日本人人質事件です。
3人の人質に対して「自己責任」という言葉が向けられ、その年のユーキャン新語・流行語大賞のトップテンにも選ばれました。


戸谷
私自身、この自己責任の考え方を知らず知らずのうちに内面化してしまっていると気づいたことが、「弱い責任」という考え方を提案したきっかけです。
具体的に言えば、仕事上でそのために失敗をしてしまったのです。
自己責任を内面化したことによる失敗とは、どういうことでしょうか。


戸谷
私は本学で教員として働く前に、教員への教育支援の仕事をしていました。
その際に、慣れない仕事を周囲にまったく頼らずに進めていたらパンクしてしまい、同僚に迷惑をかけてしまったのです。
ああ……、職場で起こりがちなケースです。


戸谷
当時の私には、1人でその責任を果たすだけの力が備わっていませんでした。本来であれば、自分に不足している力を補ってくれる力のある人に頼って、その仕事の責任を果たすべきだったと思います。
それができなかったのは、「大変でも1人でやり遂げなければならない」「人に頼るのは恥ずかしいことだ」という自己責任論に縛られていたためです。
そのときに、「自分の責任だから」と1人で抱え込んでしまうことで、かえって責任を果たせなくなる場合もあるのだなと思い至りました。
誰にも頼れないことで、結果的にうまくいかなくなってしまうんですね。


戸谷
はい。自己責任論は、経済合理性の観点からも、会社や社会に不利益をもたらすものだと思っています。
私が「弱い責任」という概念を広めたいと考えたのは、自己責任論を弱体化させたいという思いがあったからです。

責任は個人のものか
そもそも、先生のご専門である哲学の分野では、「責任」をどうとらえているのでしょうか。


戸谷
伝統的な哲学では、責任を「誰の行為によってその結果になったのかを特定するもの」ととらえます。
そう聞くと、息苦しい概念のようにも感じられますが、責任は見方を変えれば「功績」です。
ネガティブな結果には「責任」という言葉が使われますが、ポジティブな結果は「功績」として称えられます。
先生が研究されている哲学者ハンス・ヨナスは、責任をどうとらえていたのでしょう。


戸谷
ヨナスは伝統的な責任のとらえ方をクルっとひっくり返した人物です。
彼は「何に対して責任を感じるのか」という視点から責任をとらえました。
どういうことでしょうか。


戸谷
目の前に困っている人がいたとき、その「傷つきやすさを抱えた他者」への気遣いが責任であると考えたのです。また、その責任を果たすためには、周りの人々と連帯してケアにあたるべきだとしました。
なるほど。周囲と責任を共有し合うんですね。


戸谷
はい。責任とは、個人に閉ざされたものではなく、複数の人々に開かれたものだというヨナスの哲学は、責任を個人のものとしてとらえていた伝統的な哲学においては、異端ともいえる考え方でした。
私が提案する「弱い責任」は、誰に責任があるのかではなく、誰に対して責任を負うのかを重視した、このヨナスの哲学にもとづいています。
連帯を可能にする「弱い責任」
あらためて、「弱い責任」とはどのような考え方なのでしょうか。


戸谷
自己責任論のベースには、先ほどお話した伝統的な哲学における責任の概念があります。
たとえば、イマヌエル・カントは、人間を「理性的な存在」だと考えました。他者から影響を受けることなく、自分の意思で選択し、1人で行動し、生きることができる「強い」主体として人間をとらえたのです。
一方で「弱い責任」とは、人間が1人では存在できない「弱い」生き物であるということを前提にした責任概念です。
人間は弱い存在である、と。


戸谷
はい。人間は誰もが、他者の力を借りなければ生きられない赤ちゃんの状態でこの世界に生まれてきます。そして老いることで、何も自分のことができない状態に近づいていく。
長い目で見ると、人間は誰かに依存している期間が非常に長い。1人で生きていると思っている期間も、実は誰かに何らかのかたちで依存しています。
ただ、依存的だからといって、何の責任も果たすことができないわけではありません。
具体的にはどういうことでしょうか?


戸谷
たとえば、通勤途中に駅のホームで座り込んで泣いている子どもがいたとします。どうしたのかとたずねると、「両親とはぐれてしまった」と言います。
こんなとき、多くの人は、大人としてこの子を助けてあげなければならないという責任を感じるでしょう。そして、一緒に駅員さんのもとへ行って事情を説明し、子どもを預けるのではないでしょうか。
このように、1人でその子を助けることができなくても、駅員さんと連帯することで、責任を果たすことができます。
確かに、完全に親元に返すことはできないけど、別の力を持った大人を頼ることはできますね。
それが「弱い責任」ということですか。


戸谷
はい。私たちは互いに依存している存在であるからこそ、他者と連帯しながら、他者の傷つきやすさを想像し気遣う。それが私の定義する「弱い責任」です。
「弱い責任」の考え方では、子どもの身の安全が守れることに対して責任があるのであって、私ひとりだけに責任があるわけではありません。独力で責任を果たすことは必須条件ではないのです。
そのほうが現実的な解決策のように思えます。


戸谷
独力で責任を果たそうとすると、時間がかかったり、長時間子どもを連れまわすことになったりします。
このような行動はむしろ無責任。責任を独力で全うする力がないならば、むしろ他者を頼るべきです。
つまり、「弱い責任」は、責任を全うすることができない可能性を許容するものといえます。

自己責任の息苦しさからの解放
自己責任論ではなく、「弱い責任」の概念を普及させることで、どのような良いことがあるのでしょうか。


戸谷
自己責任という考え方を内面化することで、生きづらさを感じている人は少なくないと思います。そうした人たちは、「弱い責任」という新しい概念を知ることで、その息苦しさから解放されるはずです。
人に頼りやすくなったり、それによって、できることの幅が広がったりするのではないでしょうか。
哲学は、そうした新しい考え方を知ることで、生きやすくなるための学問なのでしょうか。


戸谷
哲学の定義はさまざまですが、私がもっとも納得しているのは、ミッシェル・フーコーの考え方です。彼は、哲学とは、「今とは違った考え方ができるようにすること」だと述べています。
私たちは、親からの教えや個人的な体験、生きている時代、生まれた国などによって価値観が固着しています。
フーコーは、その固着した考えを解きほぐし、納得できる別の考え方に再構成していくことが、哲学の一つの大きな使命であると考えました。
「弱い責任」という概念を普及させることも同様ですね。


戸谷
そうですね。カントのような伝統的な哲学者からすれば、「弱い責任」なんて考え方はとんでもないものかもしれません。しかし、現代の私たちは「そういう考え方をした方がより説明がつく」体験をしていると思うんです。
そうした体験を言語化し、新しい概念として形にしていくこと。それこそが、私が哲学を通じて成したい仕事です。
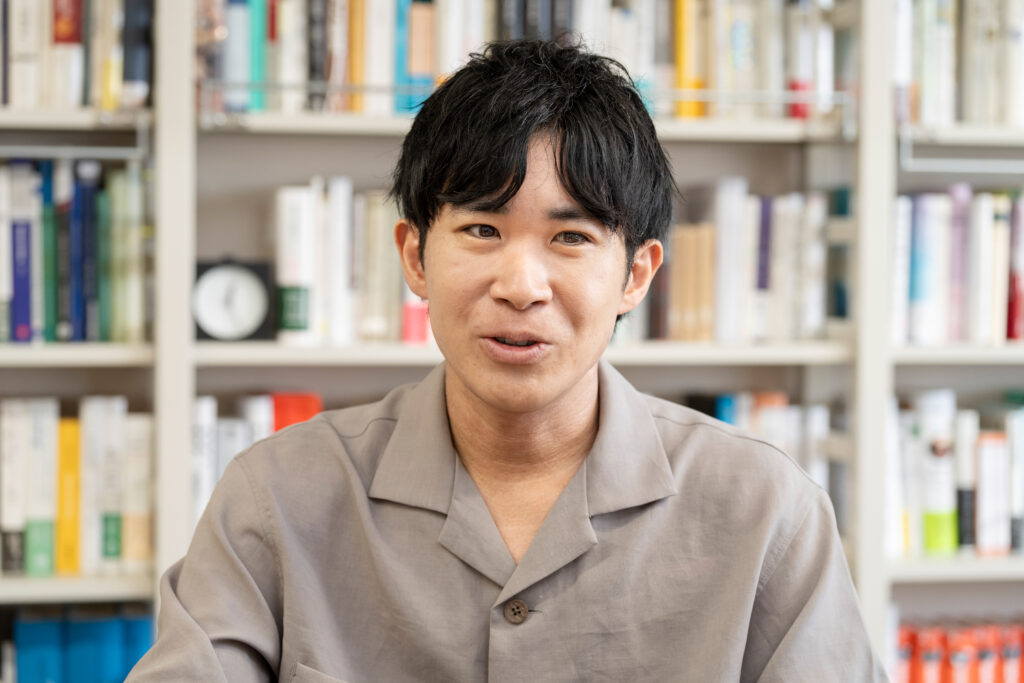
職場での「弱い責任」とは?
私たちが日々働いている職場でも、「弱い責任」という考え方ができるといいですよね。


戸谷
そうですね。自己責任論が根底にある職場では、助けを求めることを恥だと感じたり、誰かに助けられながら仕事をしている人は半人前の存在であると感じられたりします。
そうした状況では、従業員の自己肯定感が低下し、結果的に仕事のパフォーマンスも下がってしまいます。これは、職場全体にとって不利益な状況といえます。
「弱い責任」という考え方を職場に浸透させるにはどうすればよいでしょうか。


戸谷
責任を分けあえる環境であることが重要です。 しかし、「いつでも頼れよ」「何かあったら報告しなさいよ」と命令すると、そこにも従業員の自己責任が生じてしまいます。
確かに……。難しいジレンマですね。


戸谷
責任を分けあえる環境であることが重要です。
しかし、「いつでも頼れよ」「何かあったら報告しなさいよ」と命令すると、そこにも従業員の自己責任が生じてしまいます。
確かに……。難しいジレンマですね。


戸谷
大切なのは、命令しなくても自然と頼ってもらえるような、相手に心理的な恐れを抱かせない雰囲気づくりです。
心理的安全性の確保に近いでしょうか。


戸谷
おっしゃる通りです。最近、私はこの心理的安全性を確保するうえで、「ある種の無責任さを許容すること」が重要ではないかと考えるようになっています。
私だけの責任ではないと思えることは、裏を返せば、私が無責任であっても許される余地がある、ということになります。
無責任であっても、許される……?


戸谷
たとえば、私は学生の論文指導をしています。どう書けばいいのか悩み、相談に来た学生に対して、「どうなっても私が後で何とかしてあげるから、ちょっと自由に考えてきてみなよ」と言うことがあります。
これは、本来、学生が負うべき責任を、私が引き受けているわけです。すると、思い詰めていた学生が、これまでとは違うアプローチを試したり、新しい挑戦を始めたりできるようになります。
そのほうが学生さんも気が楽になり、結果的によい論文が書けそうです。


戸谷
職場に置き換えて考えると、上司が部下の責任を引き受けることで、部下にある種の無責任さが許され、イノベーティブな挑戦ができるようになるのではないかと思います。
何か新しいことを生み出すためには、ある種の「許容可能な無責任さ」も不可欠であり、そのためには上司や上の立場の人がより多くの責任を負う必要があるのかなと思います。
挑戦を促すためには、そのスタンスを明確に伝えておくことが重要ですね。


戸谷
はい。相手が納得できるように明確に説明することも、強者としての責任です。それこそが、人を指揮する立場にある人に求められる素養のように思います。
また、口では責任をとると言いながら、実際は部下に自己責任を求めるようなダブルスタンダードに陥らないよう、一貫した考え方をもつことが大切です。
ただ、この考え方について、マルティン・ハイデガーという哲学者は「最悪だ」と言っています。
最悪……!(笑)


戸谷
「責任をもっとも腐敗させるのは、相手の責任を代わりに引き受けることだ」というのです。でも私は、それは違うんじゃないかなと思っていて。
責任を代わりに引き受けることが、相手の可能性をより自由に発揮させたり、前例のない事象を引き起こしたりすることにつながると思うんです。
だからこそ今後は、「創造性を可能にする無責任さ」の理論化に取り組みたいと考えています。
新しい考え方を知ることで、自分の日常を再構成していく――。戸谷さんのお話で、哲学がとても身近に感じられました。
責任を分け合える職場、そして社会になっていけばいいなと思います。ありがとうございました!



【編集後記】
取材中、はっとした瞬間がありました。私自身も「自己責任論」を深く内面化していることに気づいてしまったのです。
「自分のことは自分で」「人に迷惑をかけない」「頼るのは恥ずかしい」、こうした自分が当たり前だと思っている考え方が、実は「それはあなたの問題、私には関係ない」という冷たい線引きを生み出しかねないなんて! 実際、過去にそんな対応をしたような記憶もあるのが恐ろしいところです。手を差し伸べ合うこと、弱さを補い合うことが難しく感じる一因はここにあるのかもしれません。
だからこそ、戸谷先生の「新しい概念を知ることで、その息苦しさから解放される」という言葉が心に響きました。根付いた価値観を解きほぐすのは決して簡単ではありませんが、まずは「知る」「気づく」ことから始まる——今回の取材は、そんな貴重な第一歩になったと感じています。(株式会社オカムラ 前田英里)
2025年7月取材
取材・執筆=前田みやこ
写真=楠本涼
編集=桒田萌(ノオト)