目の前のタスクに一生懸命になれば幸せになる確率はあがる 「“何者かにならなきゃ”と思う」のをやめよう(澤円さん)
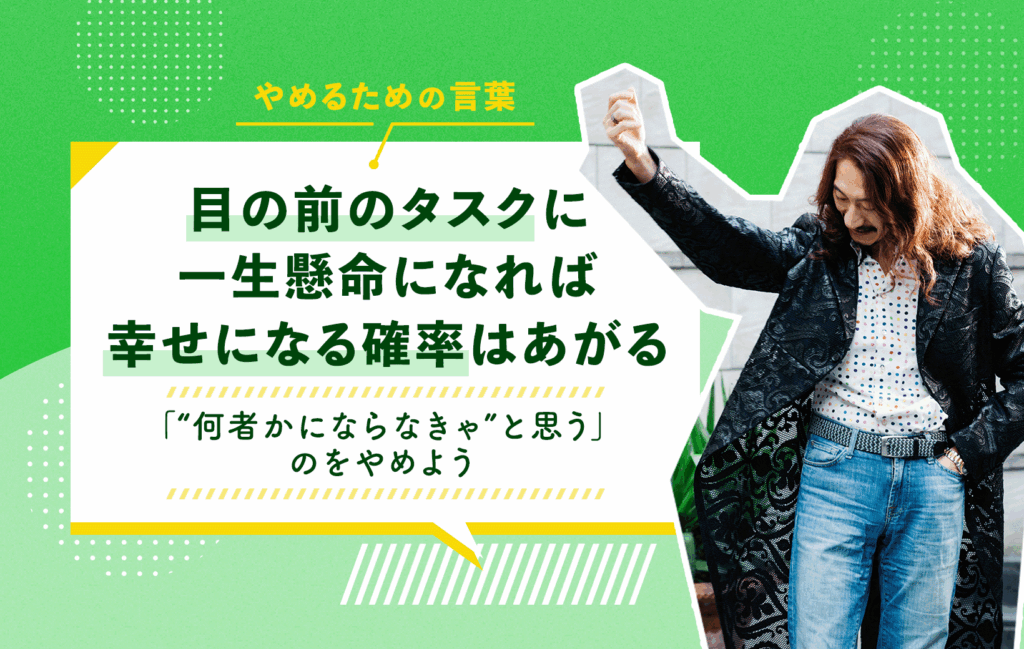
仕事でもプライベートでも、やりたいことは山のようにある。同時に、周りからのいろいろな頼まれごとにも向き合っていくと、いつの間にか予定はいつもパンパンに。この働き方、暮らし方は思っていたのと、ちょっと違う気がする……。そんなときに必要なのは、こだわりや常識、思い込みを手放すことなのかもしれません。連載「やめるための言葉」では、圓窓代表取締役・澤円さんと一緒に「やめること」について考えていきます。
SNSの功罪
2010年代になってから、多くの人がSNSに触れるようになりました。
SNSによって、誰しもが発信者となれるようになり、「バズる」ことで人気が出たり、経済的にも大成功したりする人が出てきました。子供たちの人気職業で2019年には「YouTuber」がトップになるなど、SNSはすっかり仕事のプラットフォームとして認知されるようになりました。
20世紀までは、「何者かになる」というのは、タレントや歌手になる、政治家になる、プロスポーツ選手になる……といったもので、ある意味とても参入障壁が高いものでした。
たいていの場合「何者かになっている人」に触れる機会はテレビが中心で、マスメディアの力によって(時には恣意的に)その人の存在が増幅され、「手の届かない存在」として君臨していました。
その地位にたどり着くためには、容姿端麗であったり、超高学歴あったり、超人的な運動能力が備わっていたりすることが必須条件でした。
「あの人と自分は違う」。そうやって、精神的な線引きがしやすかったのではないかなと思います。(ボクの主観ですが)
しかし、今はスマホで手軽に情報発信をして、めちゃめちゃ有名になる「一般人」が増加してきたことで、「自分も何者かにならないといけないのではないか」と不安に思う人が増えているように思います。
実際のところ、ボクが大学の講義中に「何者かにならないといけないと思っている人は?」と問いかけると、かなりの数の学生が手を挙げます。理由を聞くと、「発信力がなければ、成功できない」という危機感のようなものが共通認識であるようです。
確かに、ネットの世界には多くの成功者が情報を発信しており、その発信力によって成功が手に入っているという相関関係が感じられるのは自然なことですね。
「何者かになった人」はどんな人?
さて、ではどんな人たちが「何者か」になったのでしょうか?
これは一つのパターンに集約させるのはちょっと無理筋かなと思います。それを承知で、ボクの身の回りにいる「20世紀型有名人」とは違う形で広く認知されるようになった人たちについて観察してみました。
その人たちに共通しているのは、「身の回りのことを徹底的にやった人」で、「そのプロセスを言語化した人」です。
例えば、ボクがとても親しくさせてもらっている人の一人に尾石晴さんという女性がいます。この方は、もともと外資系製薬会社でマネージャーをしていたのですが、同時に二人のお子様を育てておられるワーキングマザーでした。
その時にワンオペ育児に追われていた体験を、まずはブログ、次に音声メディア「Voicy」で発信するようになり、たくさんの人々から支持されるようになりました。
彼女は、最初は文字と音声の情報発信だけをしていて、顔も本名も表には出しておられませんでした。(最近はちょっとずつ顔出しもなさっておられます)
ボクは尾石晴さん(晴さん、と呼ばせてもらってます)と非常に親しくさせてもらっていて、個人的にあれこれとお話を聞かせてもらいました。晴さんは、それはそれは聡明ですし、言語化能力も高いですし、「何者かになった人」として認識されるのは自然なことだと思います。
ただ、彼女は突出して何かの特徴があって有名になったわけではありません。「身の回りに起きていることに丁寧に向き合う」という行動の積み重ねが、今の彼女を作ったと思っています。
タスク・フォーカスの考え方
タスク・フォーカス、という言葉をご存じでしょうか? これは、スポーツの世界でよく使われる言葉で「今その瞬間のプレーに集中すること」を指しています。
反対の考え方が「アウトカム・フォーカス」で「ある行動や取り組みの結果として得られる『成果』や『効果』に焦点を当てる考え方」です。
サッカーのPKを例にしてみましょう。
タスク・フォーカスは「ゴールキーパーに遮られない枠の中にボールを蹴りこむこと」に集中している状態。アウトカム・フォーカスは「このPKを外したら、負けが決定して優勝を逃してしまう」ことを気にしている状態です。
どっちがいい悪いという話ではないのですが、今回のテーマに照らし合わせると「タスク・フォーカス」は、自分のコントロールできること(晴さんなら育児と仕事の両立におけるタスク)に集中し、最大に結果を得ようとすることです。
もし、これを「アウトカム・フォーカス」にすると「育児と仕事を有名になるための手段と認識する」という、「手段の目的化」に代わってしまうリスクがあります。
そうなると、「子育てを有名になるための手段にしている」という反発をするような人がどこからともなく出てくるかもしれませんね。
繰り返しになりますが、善悪について議論したいわけではありません。ただ、SNS全盛の現代社会で「ワーママのワンオペ育児を有名になるための手段として使っている」と受け取られた場合、支持を集めるどころかネットリンチに合うリスクに発展しないとも限りません。
もちろん、ネットで攻撃的になる連中を正当化する理由など何もないのですが、そういう魔物をわざわざ召喚するのもくだらないですからね。晴さんの場合、一生懸命にタスクに向き合って、その中での気付きを発信することによって多くの人たちの心をつかんだのかな……って思っています。
ほかにも、ボクがめちゃくちゃ尊敬している仲間であり友人の伊藤羊一さんも、社会人の時にぶつかった壁に必死に向き合い、心が何度も折れた経験を発信することで多くの人たちがファンになった方です。
麻布高校から東大に入り、日本興業銀行に就職……と、どう考えてもエリート街道だった彼が、めちゃくちゃ挫折した経験をどんどん発信し、そのプロセスで卓越したプレゼンテーション能力を身に着け、稀代のベストセラー『1分で話せ』を出版するに至ったわけです。
何者かになろうと思うのではなく、まずは目の前のことに必死になる。そして、そのプロセスを「誰かのためになれば」と思って発信する。これを続けていると、いつの間にやら「何者かになっている」かも知れません。
でもまぁ、何者かにならなくったっていいんですよ。目の前にあることに一生懸命になっていれば、幸せになる確率は必ずアップします。
すべったりころんだりぶつかったりもするかもしれませんが、その時に一生懸命になった人は幸せになる確率がどんどん上がります。
なぜなら、一生懸命な人は周囲の人が応援してくれるからです。一生懸命やっているうちに、誰かが推してくれるようになります。完成品ではなくても、苦労しているプロセスをどんどん見せることで、応援してくれる人がふえるのが、昨今のSNS時代の特徴かなと思っています。
(尾原和啓さんの書かれた「プロセスエコノミー」という書籍にもそのような内容が書かれています)
アイキャッチ制作:サンノ
編集:ノオト





