適切な配慮と過度な萎縮は別のもの。若者を恐れるのをやめよう(澤円さん)
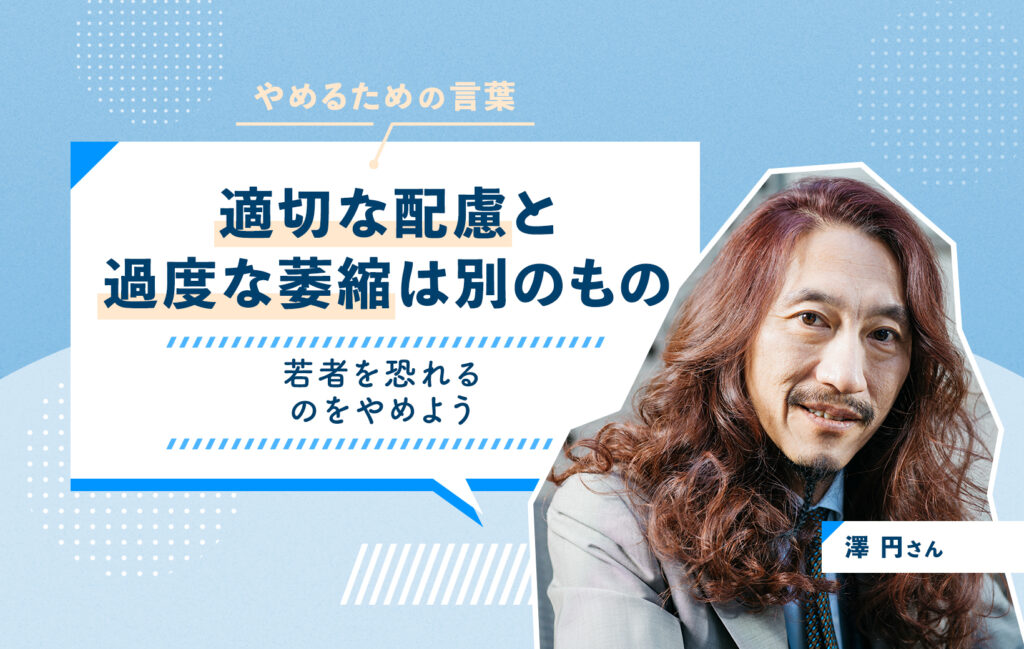
仕事でもプライベートでも、やりたいことは山のようにある。同時に、周りからのいろいろな頼まれごとにも向き合っていくと、いつの間にか予定はいつもパンパンに。この働き方、暮らし方は思っていたのと、ちょっと違う気がする……。そんなときに必要なのは、こだわりや常識、思い込みを手放すことなのかもしれません。連載「やめるための言葉」では、圓窓代表取締役・澤円さんと一緒に「やめること」について考えていきます。
過剰なハラスメント恐怖症?
春。新社会人が職場に加わる季節です。年々、少子高齢化の影響で新卒採用は難しくなり、多くの企業が若い人材の確保に苦労しています。大企業ならまだしも、知名度の低い企業や中小企業にとってはなおさらです。
同時に、「◯◯ハラスメント」という言葉があふれ、必要なコミュニケーションに躊躇する場面も増えてきました。
- 歓迎会はハラスメントになるのか?
- 注意しただけでパワハラと受け取られるのでは?
- 新卒の女性社員と会話するのも怖い……。
こんな声が、ボクの周囲からも聞こえてきます。
また、「難しい仕事を任せるとすぐ辞めてしまうのでは……」と気を使いすぎて、簡単な作業ばかり振ってしまうケースもあるようです。
もちろん、ハラスメントは決して許される行為ではありません。相手の尊厳を損なうような言動を避けるのは大前提ですし、過剰な業務負荷をかけることもNGです。
けれども、恐れるあまりに会話を避けたり、成長につながらない仕事しか任せないような状態は、若手にとっても企業にとってもマイナスです。適切な配慮と過度な萎縮は別のもの。その違いを見極めながら、丁寧な関わりを続けることが必要です。
「若者」とひと括りにするのをやめる
今もなお、新卒を一括で扱うカルチャーが残っている企業もあります。日本の新卒一括採用や終身雇用の慣習が、年次で人材を階層化しやすくしているのでしょう。
たとえば、「おい、そこの24年(2024年度入社)」というような呼び方。冗談かと思いきや、今でも耳にすることがあります。もちろん、これは論外です。
たとえここまで極端ではなくても、「若い世代はこうだから」と年齢や入社年次で一括りにしてしまうこと自体が、相手への理解を粗くし、信頼関係を築きづらくしてしまいます。
デール・カーネギーの『人を動かす』には、こんな言葉があります。
「人の名前は、その人にとっては、どんな言葉よりも甘美で大切な音である」
— “A person’s name is to that person the sweetest sound in any language.”
名前を呼ぶだけで関係が深まるわけではありませんが、「その人に個人として向き合おう」という意識こそが、相手の信頼を得る出発点になります。
フラットな関係を前提に。「恐れ」から「信頼」へ
ボクは今年で56歳になります。大学で教員をしていて、先日初めての卒業生たちを社会に送り出しました。彼ら・彼女らはいわゆる「若者」として新しい環境に飛び込んでいったわけですが、ボクは彼らとできる限りフラットな関係でいたいと思っています。
もちろん、学生時代は教員と学生という構造的な違いがありました。でも社会に出た今、一人の社会人として対等に向き合いたいのです。
それには、こちらがことさら自分を「上」に見せる必要もないし、「教えてあげなきゃ」と構える必要もありません。むしろ、「自分の知らないことを学ばせてもらう」くらいの気持ちの方が、よっぽど楽で建設的です。
とはいえ、これは理想論かもしれません。「そう思っているあなた自身がバイアスに気づいていないのでは?」という指摘もあるかもしれません。それでも、「フラットであろう」と意識すること自体が、関係性の質を変える一歩になると信じています。
若手に対して、どこかで「なめられたくない」と感じる気持ちは、年齢を重ねた側に自然と芽生えるものかもしれません。だからこそ、入社年次や役職に頼りたくなる。でも、そうした構造に依存するほど、本質的な信頼関係からは遠ざかってしまいます。
若い人たちにどう向き合えばいいのか。答えはシンプルです。
彼らを「一人の社会人」として扱い、信頼する。
そして、自分の不安や恐れに気づきつつ、それに振り回されないようにする。それだけで、コミュニケーションの質も、働く環境も、大きく変わっていくはずです。
アイキャッチ制作=サンノ
編集=ノオト





