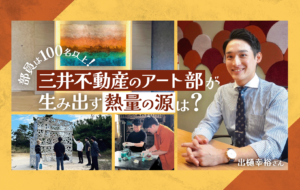「空き壁」をキャンバスに場を変える。ミューラルアートでまちの風景をつくるWALL SHARE・川添孝信さんが生み出すもの

壁に描かれているアート作品「ミューラル」。このプロデュースを事業にしたのが、川添孝信さんです。大学卒業後に自動車メーカーの営業、IT企業を経て、2020年にWALL SHARE株式会社を起ち上げました。
海外旅行をする日本人たちがミューラルの前で幸せそうにしている姿をSNSで見て、「日本にもニーズがあるのでは」と考えるようになったという川添さん。
かつてない仕事をどうやって事業として育てたのか。そして、ミューラルがまちなどの空間にもたらす効果とは。川添さんにお話を聴きました。

川添孝信(かわぞえ・たかのぶ)
1990年、兵庫県神戸市生まれ。大阪市此花区在住。大阪体育大学卒業後、ドイツの自動車メーカー「フォルクスワーゲン」の新車営業に従事。IT企業などを経て2020年4月にミューラル(壁画)を制作・プロデュースする「WALL SHARE株式会社」を設立。
営業職時代に海外の壁画に影響を受けた
川添さんは、以前は企業の営業をしていたそうですね。


川添
フォルクスワーゲンの新車営業をしていました。
でも、もともとは教師になりたかったんです。教員免許も取得していました。
それが、どうして自動車の営業に?


川添
大学4年生の頃に東日本大震災のボランティアを経験したんです。そこでさまざまな人と出会い、「自分は未熟だ。まだ子どもにものを教えていい人間になれていない」と感じてしまって。
それで、営業職を希望しました。小学校から大学までずっとサッカーをやっていたので、「競う仕事ならば向いているのではないか」と考えたからです。

営業成績はいかがでしたか。


川添
入社後、1200人ほどの営業担当者がいるなか、販売台数で10位前後に3度入りました。
すごいですね!
どのようにして顧客を獲得したのですか?


川添
「お客さん以上、友達未満」を心がけました。営業担当者って、態度が固くなりがちじゃないですか。でも、自分はお客さんという感覚で接するのではなく、もっと仲よくなろう、と。
営業って究極に言うと、ものを売るだけではなく、「仲よくなる」「その人を好きになる」ためにやるのだと思うんです。
それに、僕はもともと人が好きで。長所を聞かれたら「友達が多いこと」だと答えています。当時のお客さんとは現在も付き合いがあることも多いですよ。
素敵ですね。ミューラルに関心をもったきっかけはなんですか。


川添
海外のミューラルを現地で鑑賞した体験が大きいですね。新車販売の営業成績がよいと、メーカーがご褒美旅行へ連れていってくれたんです。
それでドイツはもちろん、ロサンゼルスや香港など、さまざまな都市を訪れました。そこで見た、世界のアーティストたちが描いた壁画にすごく影響を受けています。
当時からアートに関心があったのでしょうか。


川添
もともと学生時代からHIP-HOPをはじめとするストリートカルチャーが好きでした。ラップだったり、DJだったり、クラブファッションだったり。
そのなかでも特に、日本語のラップと「グラフィティ」と呼ばれる壁に描くカルチャーに惹かれました。
ミューラルとグラフィティの違いはどこにあるのでしょう。


川添
大きな違いは、グラフィティは無許可で描かれているもので、ミューラルは許可を得て描かれる点でしょうか。
ミューラルは許可を受けているので、壁一面を利用して大規模に展開し、デザインも緻密なケースが多いです。
ミューラルで起業しようと思われたのは、どうしてですか。


川添
僕らが20代半ば頃、Instagramが流行しはじめました。
そこに、海外旅行をする日本人の画像がどんどんアップされ、みんなミューラルをバックにVサインしたり手をつないだり、めっちゃ楽しそうにしていたんです。
その画像を見たとき、「日本でもミューラルのニーズを生み出せるのではないか」とひらめきました。

川添
日本だと、「アート=難しいもの」と捉えられる傾向にあります。
でもミューラルだったら、もっと身近なアートになるんじゃないかって。
ミューラルのどういったところがよいと思われましたか。


川添
まちの風景をガラッと変えてしまう点ですね。ミューラルはアート作品としては破格に大きく、それだけにインパクトも強い。壁一面のアートが放つパワーはやっぱりすごいですよ。
よい壁を求めて「壁営業」する
そうして立ち上げたのが、WALL SHARE株式会社ですね。
具体的に、どのような会社ですか。


川添
クライアントから依頼を受けて、アーティストをキュレーションし、これまで使われていなかった「空き壁」にミューラルを描く会社です。
今日までに世界中からおよそ80名のアーティストが参加しており、プロジェクトや壁のサイズなどに応じて、アーティストをキュレーションして進めていきます。
アーティストはどのように発掘しているのでしょうか。


川添
発掘している、という意識はまったくありません。
会社員の頃も、休日は全国いろんな場所のミューラルを見に行ったり、SNSなどで世界中のミューラルをチェックしたりなど、本気でハマっていたので、アーティストはだいたい知っているんです。
だから、常にリスペクトしているアーティストに依頼しています。むしろ我々の方が応援してもらっているという感覚です。

ミューラルを創りだすためには、まず壁が必要ですよね。


川添
そうなんです。なので、常に「よい壁はないか?」という意識でまちを歩いています。一時期は週に1回、よい壁の情報を共有する「壁定例会議」を社内でしていました。
そして、「こちらの壁を使わせていただけませんか?」と、壁の所有者(大家さん)に壁営業をします。
「壁営業」という言葉を初めて耳にしました。
建物の持ち主に「壁を使わせてもらえませんか」と依頼して、使わせてもらえるものなのでしょうか?


川添
驚かれますし、最初は怪しまれることもあります(笑)。たいていは門前払いです。急に「壁に絵を描かせてくれ」って、いったいどんな依頼なんだよって自分でも思います。
そうですよね……。


川添
それでも、ちゃんと交渉を進めていけば、描かせてくれる方がいるから、こうして成り立っているんです。
ただ「WALL SHARE」のように、まちにある壁のプラットフォームになっている会社は日本にはまだまだ少ない現状です。
なので、ミューラルを求める企業からの問い合わせはどんどん増えてきている状況です。
ミューラルがまちの景色を変えて活性化する
SHARE WALLにはどのような事例があるのでしょうか?いくつか教えてください。


川添
手ごたえを感じたのは、リラクゼーションドリンクブランド「CHILL OUT」(チルアウト)のミューラルをつくったときです。
オープンイノベーションのプロダクトを通して通じて出会い、新たなプロモーション施策の一環として、WALL SHAREの提案を採用していただきました。
会社は初めから順調でしたか?


川添
いいえ。起業してすぐにコロナ禍による緊急事態宣言が発令されて、半年間は仕事がまったくない状態もありました。
そんなとき、大阪・新世界のくら寿司が「コロナで気持ちが沈んだまちに活気を取り戻したい」と、店舗の壁にミューラルの制作を依頼してくださったんです。くら寿司にとって、すごいチャレンジだったと思います。
ミューラルを描くのは屋外の壁だけですか。


川添
オフィスの壁も手掛けています。
たとえば、三菱鉛筆株式会社さんのオフィスには、自社製品であるポスカを使って、フロア3階分のミューラルを描きました。
-1024x768.jpg)
ポスカで壁に絵が描けるんですか!


川添
ポスカって日本では文房具という位置づけなのですが、海外だとアートの画材としてすごくステージが高いんですよ。アーティストにとって最高のツールなんです。
オフィスにミューラルがあることで、社内の雰囲気は変わるのでしょうか。


川添
自社製品を用いた大きなアートが描かれることで社員も自社を誇りに感じるでしょうし、表現豊かな社内空間のなかにいると新しいアイデアも浮かびやすいのではないでしょうか。
オフィスアートの需要はこれからもっと増えてくるでしょうね。

川添
ちなみに、壁以外の事例もあります。岡山県真庭市でのプロジェクトでは、公共のスケートボード広場にアートを描きました。
アーティスト・SUIKOさんの作品で、1,000平米あります。日本に現存する地上絵としては、最大級だといえます。

このような広大な作品が、どのような過程を経て完成したのでしょうか。


川添
真庭市の地域おこし協力隊のメンバーにアツい想いを持つ人がいて、「古いスケートボード広場を活用して、もっと人が集まる場所にしたい」という申し出により実現しました。
まちを変えたいと考えている情熱的なキーマンが一人いるだけでも、プロジェクトは成功に向かって動き始めるんです。
ミューラルがまちおこしにもつながってゆくのですね。


川添
そうですね。さまざまな場所にこういう実績を増やしていくことが、今後は重要だと考えています。
「WALL SHARE」のオフィスがある大阪の此花区にも、たくさんのミューラルがありますね。これは企業や行政からの依頼ですか?


川添
「ミューラルタウンコノハナ」プロジェクトは、最初は自分たちの自己資金を投じて始めました。自分が暮らすまちを「身近にミューラルがあるまち」に変えたかったんです。
いま、同エリアには16名の海外アーティストによる23カ所のミューラルがあります。日本に描きたいという問合せも多く、まだまだ増えていく予定です。

川添
他都市からやってきた人たちがアートを巡りながら、その途中でお茶したり、買い物をしたり、銭湯へ行ったり。経済効果はもちろん、まちの人とのコミュニケーションも生まれやすくなります。
先日オープンしたオフィス兼珈琲店「壁珈琲」は、このプロジェクトの拠点でもあります。今後は観光客や地域の方に向けて、ミューラルツアーなども企画していきたいです。

現在も、「ミューラルタウンコノハナ」プロジェクトは自費で行っているんですか?


川添
僕たちの活動に対する想いに共鳴してくださった富士フイルム株式会社が協賛についてくださっています。

直接的な広告ではないミューラルに、企業が協賛するメリットは何なのだと思いますか?


川添
世の中に溢れる広告手法ではなく、アートをはじめとする文化に企業が、協賛というかたちで伴奏するのはシンプルにカッコいいし、そのスタンスはユーザーにも届くと思います。
ましてや、まだ日本ではニッチなミューラルへ協賛をいただいています。
僕たちが成長した先には、先方の投資に対して良いお返しをお渡しできるのではないかと、プロジェクト運営する側としても良いモチベーションにつながっています。
ミューラルがあることによって、此花区のまちにはどんな影響があったと思いますか?


川添
徐々に、ミューラルを目的にこの辺りに初めて足を運んでくれる人がいたり、まちの人からも「明るくしてくれてありがとう!」などのお声をいただくことも増えたりしてきました。
ちなみに、まちの中にとても目を惹く大きなアート作品があることに、抵抗感を示す住民はいませんか?


川添
不快に感じる人はもちろんいます。まちの景色の変えることをしているので、賛否はあるでしょう。
でも、全員が100点をつけるのは面白いことではない。賛否があってこそ新たな気づきや刺激になる可能性もあると思います。
このプロジェクトについても、ミューラルでこのまちをより良い場所にしたいというゴールはぶれていないので、ポジティブな結果を目指して取り組んでいきます。
こだわりは「超・アーティストファースト」
ミューラルをプロデュースするうえでのこだわりはありますか?


川添
大前提として「超・アーティストファースト」です。
彼らにとっては人生の一大作品になりますし、絵を描くことに日々向き合っているアーティストに委ねた方が、結果的に良い作品になることが大いにあります。
確かに、企業色を押し付けず、アーティストの挑戦に賭けている方がカッコいいと感じます。


川添
企業色が強いと、見る人が見ると押しつけがましいな、とわかっちゃうんです。
とはいえ、クライアントにとっていいものを作るのも前提です。クライアントのビジョンをしっかりキャッチアップして、アーティストの表現とのあいだを取り持ってゆくのが自分たちの役割だと考えています。
そのビジネス感覚は、営業職時代の経験が役に立っていそうですね。


川添
めちゃめちゃ役に立っています。新車営業をやっていた頃の「お客様以上、友達未満」というポリシーは現在もずっと胸の中にあります。
ミューラルはアーティスト、クライアント、壁の所有者、周辺住民の理解がないと生み出せない。大きな作品になると建設現場さながらの資材や重機が必要になってきます。
それらの交渉は、営業経験がなかったらできなかったかもしれません。
誰とでも仲よくなれるコツはありますか。


川添
「素」でいること、愛をもって接することです。僕はどんな大企業でも、いつものこのトレーナー姿で行くんですよ。お互い「素」でいきましょうという気持ちで。


川添
そして、「マジで好きなカルチャーなんだ」という純粋な気持ちを忘れないこと。実際、死ぬまでこの仕事をやるつもりなので。そうすると、相手に気持ちが伝わるんです。
今後の展開を教えてください。


川添
いま、海外からのオファーや打診が増えています。先日、海外の政府からも問い合わせをいただいて。ミューラルにまちを変える力があることが逆輸入のように海を越えて伝わっています。
「壁がある場所ならば、どこへでも」という気持ちで、これからもやっていきたいですね。
今日は本当にありがとうございました。今から此花区のミューラルを鑑賞して帰ります。



【編集後記】
大阪にこんなワクワクする街があるんだ!と実際に訪れてみて、まずは驚きが隠せませんでした。
「空き壁」をキャンバスに変える——そんな発想から生まれたミューラルアートは、街の風景に新たな息吹を吹き込んでいます。川添孝信さんが率いるWALL SHAREは、使われていなかった壁にアートを描くことで、建物やそこに面する道、空間の価値を再定義し、街に彩りと物語をもたらしています。
アートがあることで人の流れが生まれ、地域への関心や誇りも育まれていく。街に暮らす人、訪れる人、通りすがる人——誰にとっても、その一瞬が特別な体験や未来に向けた新たな種を生み出すことにつながるのではないでしょうか。
この取材で、改めてアートと空間の組み合わせが街・地域にもたらす可能性をひしひしと感じました!
(WORK MILL編集長/山田 雄介)
2025年2月取材
取材・執筆=吉村智樹
写真=木村華子
編集=桒田萌/ノオト