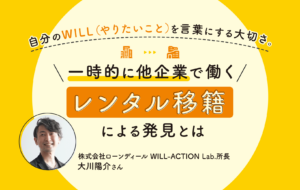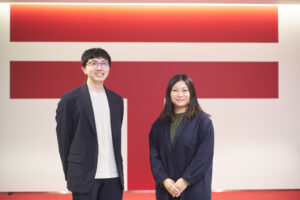「会社人」から「社会人」へ。15年間の越境で見えた、これからの働き方と社会とのつながり方(NPO法人二枚目の名刺・大山みのり)

自分の人生をどう生きたいか、自分らしい働き方とは何か。時代が大きく変化するなか、自分自身に問いかける機会は増えました。そんな問いへの一つの答えが、「二枚目の名刺」かもしれません。
本業とは異なる立場で社会に参画する活動を「二枚目の名刺」と定義し、その機会を提供してきたNPO法人二枚目の名刺。構想開始から15年以上にわたり、多くの社会人の「越境」を支援してきました。
創設メンバーの1人である理事の大山みのりさんは、本業では公認会計士として活躍する傍ら、団体の運営を支え続けています。
副業やパラレルキャリアが当たり前になりつつある今、活動の原点や、この15年間で感じてきた社会の変化、そして未来への展望を伺いました。

大山 みのり(おおやま・みのり)
NPO法人二枚目の名刺 理事。公認会計士。大山みのり公認会計士事務所代表。1999年に公認会計士試験に合格後、中央青山監査法人に入所。2009年、NPO法人二枚目の名刺の設立に参画。2015年に、公認会計士事務所を開業。2016年よりグロービス経営大学院にて講師を務める。
NPOと社会人を結ぶ、「Win-Win」なプロジェクト
まずは、現在の「二枚目の名刺」が提供されている活動についてお聞かせいただけますか?


大山
私たちの主な活動は、社会人とNPOをつなぐ「サポートプロジェクト」の運営です。多様な業種・職種の社会人が5人前後のチームを組み、3〜4カ月の期間でNPOなどの団体と協働し、その事業推進を支援しています。
スキルや経験を活かして社会課題の解決に取り組む、プロボノ活動ですね。単なる副業や趣味ではなく、一人ひとりが大切にする「こんな社会になったらいいな」という価値観を、当事者意識をもって形にする機会をつくりたいと思っています。

なるほど。参加者とNPO、双方にとってのメリットがありますね。


大山
はい、それが一番大事なポイントだと思っています。
単に社会に価値を提供するだけでなく、それが自分自身の学びや成長につながる「双方向性」を重視しているんです。
過去のプロジェクト後のアンケートでは、参加者の94%が「自分自身の変化・成長」を実感したと回答しています。
数字にも表れている通り、大きな成長機会になっているのですね。


大山
一方、NPO側も83%が「団体活動に何らかの変化があった」と答えています。
サポート先と参加者が互いに価値を高め合う、Win-Winな関係を築くためのハブとして、二枚目の名刺がプラットフォームになれていたら、嬉しいですね。
いい関係を作るためには、参加者がどんな問題意識をもっているのかも重要ですよね。
どうやってマッチングを行うのでしょうか?


大山
まず「Common Room(コモンルーム)」という説明会兼マッチングイベントを定期的に開催しています。
ここで、NPOの方から団体が抱える課題や参加者にやってほしいことをプレゼンしてもらい、それに興味を持った社会人が参加を申し出て、チームを組んで活動を開始する流れですね。
顔を合わせてマッチングできることで、信頼感も高まりそうです。


大山
そうですね。その後、3〜4カ月のプロジェクト期間は週1程度で参加者同士の打ち合わせをしたり、個別で課題に取り組んだり。中間報告と最終報告を通じて、ゴールを目指します。
アウトプットの形式は、提案書のようなレポートから、実際に使えるツールやフォーマットまで、NPOの課題に合わせてさまざまです。

専門性やスキルセットを問わず、多様な人々が協働するなかで、難しさもありますよね。


大山
たしかに、企業とNPOでは仕事の進め方やコミュニケーションのスピード、使う言葉も違いますが、3カ月の間で徐々にわかってきます。
その違いも、少しずつ慣れていくんですね。


大山
とはいえ、それでもうまくいかない時もあります。そのため、「デザイナー」と呼ぶ伴走役のメンバーがサポートに入ります。
このデザイナーは、以前プロジェクトに参加した経験者がほとんど。自身の経験から「こうやるとうまくいくのではないか」と助言することで、チームの円滑なコミュニケーションやプロジェクトマネジメントを支援します。
確かに経験者の伴走があると、安心して挑戦できますね。


大山
そうなんです。だからこそ、私たちは参加者がもっている専門性よりも「挑戦してみたい」という思いを重視しています。
ちなみにデザイナーも「運営に回りたい」と手を挙げてくれたメンバーで構成されており、この「経験の循環」は私たちの活動を支える大切な要素です。
立ち上げの原点は、留学先で出会った仲間たちの「思い」
2009年設立とのことですが、そもそも活動を始められたきっかけは、どのようなものだったのでしょうか?


大山
原点は、NPO法人二枚目の名刺・代表の廣 優樹(ひろ・ゆうき)をはじめとする立ち上げメンバーが、留学先のビジネススクールで得た「越境体験」です。
当時、彼らはベトナムの農業支援プロジェクトへ参加したのですが、そこで本業の垣根を超えて挑戦した経験が大きな学びになったそうで。それが、二枚目の名刺のサポートプロジェクトを考えるきっかけになったそうです。
大山さんご自身はどうして二枚目の名刺の立ち上げに関わることに?


大山
実は、私も同じ学校に通っていたことが縁になっていて。ただ実は、当時の私は社会課題への関心はそこまで高くありませんでした。
会計士として留学していたので、職業柄ファイナンスなどを学びたいと思っていたんです。でも、留学先のイギリスで出会ったアフリカやインドからの留学生たちの影響を強く受けまして。
どんな影響を?


大山
彼らは「ここで学んだことを自分の国に持ち帰って、社会を良くする事業をしたい」と熱く語るんです。
それを聞くうちに、「自分も何か社会のために動かなければいけないんじゃないか」と考えるようになっていって。
そんな課題意識を持って帰国したタイミングで、廣たちのアイデアを聞き、「面白い、やってみたい」という気持ちで関わりはじめました。
当初は、どのような活動からスタートされたのですか?


大山
最初は本当に何もなくて(笑)。私たち4人で「会社員と社会課題をつなぐコンセプトを紙にして、いろんな場所で説明する」ところからのスタートだったんです。
手探りながらも、「二枚目の名刺」のコンセプトを社会に広める活動を始めました。
15年間で見えた、社会と個人の「越境」の変遷
今は複業やパラレルワークも当たり前になってきました。とはいえ、設立当時の2009年はまだ「二枚目の名刺」というコンセプトが一般的ではなかったのではないでしょうか?


大山
まさにその頃は、まだ「社会貢献=寄付・ボランティア」を思い浮かべる人も多い時代でした。
そうですよね。その中で、どうやって二枚目の名刺の活動内容を伝えていったのでしょうか?


大山
特に強調していたのは、2つのポイントです。
まず、自分のスキルや得意なことを活かした「自分らしい貢献」という方法を作りたいと考えていたこと。そして、もう一つはその経験が自分自身の学びや成長にもつながるという「双方向性」を重視したことです。
このWin-Winの関係は、私たちの活動を支える背骨になっていると思います。
なるほど。この15年間で、組織や活動、そして社会の受け止め方にはどんな変化がありましたか?


大山
一番大きな変化は、社会全体の価値観が私たちの活動に追いついてきたことですね。
立ち上げ当初は「二枚目の名刺を持つ」と言うと、「勤め先に怒られないんですか?」と聞かれたり、知見が流出するのではないかと警戒されたりすることが多かったんです。
どちらかというと、隠れてやるべきこと、おおっぴらにすべきではないという雰囲気でした。
複業が当たり前になった今だと、あまり考えられないですね……!


大山
当時は「社員が社外活動に興味を持つと、会社を辞めてしまうのではないか」と懸念されることがあって。
越境を経験していない企業ほど、そうした「食わず嫌い」的な恐怖感を抱きがちという傾向もあるようです。
たしかに、未経験の取り組みに対して抵抗感を持つ企業は少なくなさそうです。


大山
でも、実際に越境プログラムを導入した企業からは、「逆に社員のロイヤリティの向上につながる」という声もあるんです。
「学びを持ち帰ってくれた」という実感や、社員が「こうした機会を与えてくれる会社で長く働きたい」と感じてくれたり。
そうやって企業が人材を育成するハブとして活用してもらえるよう、越境の価値を丁寧に説明しています。
長年の積み重ねの結果ですね。


大山
ありがとうございます。今では、日頃の会話の中で「他にもこんなことをやっています」といった話が出ても違和感はありませんよね。
「二枚目の名刺を持つことが当たり前の社会を作りたい」という私たちの当初の思いが、少しずつ形になりつつあると感じています。
嬉しい変化ですね。ちなみに、参加者側にも変化があったのでは?


大山
大きく変わりましたね。当初は本業に勤めている会社員、特に20〜30代の若手の方が中心で、「会社人から社会人へ」という変化を志す方が多かったですね。
それが今では、フリーランス、早期退職されたシニアの方、学生など、参加される方自体が非常に多様になりました。
いろいろな方が「二枚目の名刺」を持つのが当たり前になっているんですね。
参加する方はどんな学びや変化を感じているんでしょうか?


大山
具体的な変化としては、まず「視座が広がった」「社会の広がりを持って物事を考えられるようになった」といった自己変容の声。
また、ビジネススキルに結びつく変化も多く、多様なメンバーとのプロジェクトをやり遂げるなかで、コミュニケーションやチームビルディングのスキルが向上したという声も多いです。
すごいですね。


大山
NPO側からは、「外部の視点やビジネススキルが入ることで組織に新たな変化が生まれた」「客観的な視点から自分たちの活動を可視化してもらったことで『こんな価値があったんだ』と再認識できた」という声も多くて。
プロジェクト後アンケートの結果、82%の方にアウトプットに満足いただいています。
「二枚目の名刺」だから、無理なく続けられる機会をつくる
運営面でも、立ち上げ当初はご苦労があったのでは?


大山
正直、この15年のうち最初の半分くらいは、運営面でも試行錯誤の連続でした。
まず、立ち上げメンバーもみんな、本業と兼業でやっているため十分な時間がとれず、やりきれないことも沢山ありました。
でも、私たちは「一枚目の名刺を言い訳にしない」と決め、お互いが融通し合いながら活動を続けてきました。


大山
そうした自分たちの経験から、サポートプロジェクトの期間も調整しました。
兼務をしている都合上、長すぎると途中で疲れてドロップアウトしてしまう可能性もある。なので、しっかりやりきったという達成感と続けやすさの両方を加味して、現在の3カ月という期間設定に至りました。
なるほど。継続できるバランスは重要ですね。


大山
ちなみに、NPO法人二枚目の名刺の運営メンバーもほとんどが兼業の方なんです。気づけば、60名以上が関わってくれています。
大所帯になってますね!


大山
今は以前と比べて本当に沢山のことができるようになりました。また、参加者のバラエティも豊かになり、シナジーが生まれるようになったと感じています。
シニアの方は豊富なご経験からチームをまとめるコミュニケーションハブとして存在感を発揮してくださったり、学生の方は社会人とのフラットなプロジェクトを通じて貴重な経験を積んだり。
素敵ですね。
大山さんご自身も、公認会計士という本業と両立されてきたなかで、印象的な出来事はありましたか?


大山
私自身が最初にサポートプロジェクトに参加したのは、助産師の方が運営されている団体でした。普段は会計士として決算を見るような仕事をしている私が、マーケティング的な課題に取り組んだのです。
チームメンバーも多様な企業から来た人たちで、やり方から手探りで進め、最終的にゴールを達成できたことが大きな成功体験となりました。


大山
この経験は、15年経った今もずっと私の背中を押してくれています。
特に助産師の方々との出会いは強烈に記憶に残っていて。当時の私はまだ出産を経験していませんでしたが、後に自分に子どもができたことで、あの経験の解像度がより一層高まりました。
そして、当時のサポートプロジェクトの中で、「あなたから刺激を受けた」と助産師の方に言ってもらえたことも、活動を続ける大きな活力になっています。
誰もが「担い手」になれる未来へ
最後に、今後の展望を教えてください。


大山
これからの社会は、労働人口が減っていくという課題に直面します。そうした時代だからこそ、優れた一部の人だけでなく、誰もが社会的な課題解決の担い手になっていけるような、そんな社会を目指していきたい。
それが、この活動を続けていく私たちの使命だと思っています。
誰もが、ですか。とても心強いメッセージですね。


大山
はい。そのために、私たちは多様な人々が「この活動は自分にとって良い機会だ」と感じられるストーリーを発信していくことが役割だと考えています。
学生、シニア、会社員。それぞれの立場や価値観に合わせて、「どんな学びや成長があるのか」を伝え、挑戦への一歩を踏み出すきっかけを提供していきたいです。
「思い」を大切に、ですね。


大山
もし本業以外にも社会と関わってみたい、挑戦してみたいという思いが少しでも芽生えた方がいらっしゃれば、ぜひその気持ちを大切に一歩踏み出してみてほしいです。
その一歩が、きっとご自身の人生と社会を豊かにするきっかけになるはずですから。

2025年7月取材
取材・執筆=安心院彩
撮影=小野奈那子
編集=鬼頭佳代/ノオト