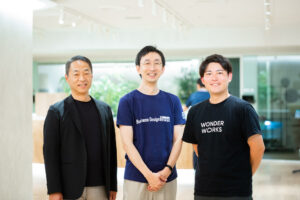NTTテクノクロスの130人以上が参加する社内共創コミュニティ「First Penguin Lab」。自主活動がアウトプットにつながる運営の秘訣とは

会社の中で自主的な活動を行いたいけど、どうしても本業優先になりなかなか続かない。そう悩むビジネスパーソンが多いのでは。
そんな中、社員個人の趣味が全社の半数以上を巻き込む大イベントに発展したり、実際にアプリケーションの開発に至ったりと、自主活動が次々と形になり、それが会社全体の風土にいい影響をもたらしている企業が、NTTテクノクロス株式会社。
同社が運営する実践コミュニティ創出プラットフォーム「First Penguin Lab(ファーストペンギンラボ)」は、ラボと呼ばれるコミュニティを生み出す場になっており、介護や育児と仕事の両立を探究するラボや業務手順の改善に取り組むラボなど、社員のアイデアをもとに次々に共創が生まれています。
ボトムアップ型のプラットフォームが継続されるのは、どうしても難しいものです。しかし、なぜNTTテクノクロスではこの活動が続いているのか。運営の仕組みや、活動がアウトプットにつながるまでの工夫について、同社の社員でFirst Penguin Lab事務局の担当者である福島隆寛さん、森本龍太郎さんに話を伺いました。
自由で多様な場所をデザインするための実験場
NTTテクノクロスでは、社員が自由にアイデアを出し合い、それにチャレンジする共創コミュニティ「First Penguin Lab(ファーストペンギンラボ)」を運営されています。
改めて、どんなコミュニティでしょうか?


福島
まずNTTテクノクロスは、2017年にNTTグループの2社の合併、1社からの事業譲受で生まれました。「First Penguin Lab」は、3社それぞれの事業の強みをかけ合わせてイノベーティブな組織文化を醸成する目的で発足しました。
経営企画部発信でスタートした取り組みで、部署を超えた交流を生む狙いがあったそうです。

合併後の社内交流を活発化する目的だったんですね。First Penguin Labの活動はどのような効果がありましたか?


森本
第一に、困ったときに社内で相談できる横のつながりが増えました。
例えば、合併当初は、ある仕組みはA社のルールを踏襲していて、他の会社出身の人にはわからないことがよくありました。
そんなとき、「じゃあ、First Penguin LabにいるA社出身の人に聞いてみよう」という行動パターンが生まれて、そのおかげですぐに解決したことが何度かありました。

First Penguin Labの方たちが社内のハブのような役割になっているんですね。


福島
8年ほど運営しているので、社内のさまざまな部署にメンバーが散らばっています。
何か困ったことがあれば、別の部署のラボ仲間に助けてもらうこともあります。
学校の部活動のような連帯感がありそうですね。クラスが違っていても通じ合っているような。


森本
近い部分がありますね。会社なので組織異動がありますが、First Penguin Labにはずっと所属している状態ですから。
「ラボ」はいつでも立ち上げ可能、135名が参加
First Penguin Labはどのように運営されているのでしょうか?


福島
私と森本の二人がメインで事務局を担当しています。初期は1・2期とメンバ募集の期間を区切っていましたが、今はやりたい人は事務局に直接伝えたり、メッセージを送ったりしてもらうだけでスタートできます。
社内のチャットツールにFirst Penguin Labのチャンネルがあり、そこでやり取りをしています。累計で135名ほどが参加しています。
参加者は自由に「ラボ」を立ち上げられるそうですが、どのくらいの数がありますか?


森本
1年以上活動したものだけを数えると30前後です。
First Penguin Labの活動から生まれたアウトプットについて教えてください。


森本
例えば、私も開発に携わった「虹予報ラボ」。虹が出るタイミングを予測するプログラムを作っています。
虹って見られたらうれしいけど、なかなか見る機会が少ないですよね。だから、アメダスや雲の情報から、虹が見える条件が揃っているかを計測して、社内向けのチャットツールに通知する仕組みを作りました。

虹の発生を予測するなんて、心が和みそうですね。
事務局のおふたりも、何かのラボに参加しているんですね。


森本
そうですね。興味を持ったものがあれば、ラボの活動にも参加しています。その方が参加者の気持ちや悩みもわかりますから。

福島
私はesportsラボを設立しました。
当社では全社のeスポーツ大会を毎年開催していますが、元々はFirst Penguin Labのラボから始まったイベントで、今では会社をあげての大規模なイベントになりました。
当社の社員数は2000人弱ですが、毎年半数を超える1000人以上が参加しています。


すごいですね……!

え! 6人で1000人規模のイベントを運営しているんですか?


福島
当日の運営自体は30人ほどの方に手伝ってもらって、インカムをつけながらイベント運営をしています。
全社のイベントのほかに、近隣の大学に声をかけて、教員&学生対社会人対抗戦をやったり、他の企業に声をかけて企業の対抗戦もやったりしています。
外部の人と対抗戦をすると、社内の結束が高まりそうですね。


福島
みんなで練習をするので、部署を超えた縦・横・ななめの人脈づくりにもつながっています。その人脈を生かして、オンラインでも盛り上がるためにesports大会応援アプリケーションも作りました。
勤務時間内に活動できて、プロセスを重視するルール
運営する上で、何らかのルールは設けているのでしょうか?


福島
4つのルールを設けています。
1. 社員の自主的な活動を尊重する
2.事務局が活動を支援する
3. 勤務時間内の活動を可能とする
4.プロセスを重視する
それぞれのルールの意図を教えてください。


福島
「1. 自主的な活動を尊重する」を設けた理由はシンプルです。自分の興味・関心から「これ、やってみたい!」と始めた方が、ポジティブにイノベーティブなことができるからです。
「2. 事務局が活動を支援する」は、そもそも参加者はみんな本業があり、上司や同僚などと業務調整を行いながら参加しているわけです。
そのため、ラボの活動と両立できるよう事務局から声をかけたり相談に乗ったりするなど対話を行うと共に、活動のPRなど周囲の人への理解促進に取り組んでいます。
確かに、自主的な活動だからこそ、本業を優先してなかなか続かない……なんてこともありそうです。それを事務局がフォローする仕組みになっているんですね。


福島
「3. 勤務時間内の活動を可能とする」は、たとえば時短勤務の人が何か活動をしたいと思っても勤務時間外の活動にするとラボに参加できません。もちろん勤務時間内での活動もなかなか厳しいと思いますが、上司との相談で時間を捻出できる可能性はあります。
それに、業務時間内で活動している方が、今まで会社の中になかった事柄を会社に持ち込みやすいです。
業務時間内で活動していると、なぜ持ち込みやすいのでしょうか?


福島
会社外の活動を「面白いので会社でもやりませんか?」といきなり持ち込むより、まず社内活動であるラボで取り組んでから、「いい取り組みなので、会社の施策にできませんか?」と提案する方がスムーズに進みます。
個人の関心事をまずはラボで試してみて、そこから会社に提案することもできるんですね。


森本
「4. プロセスを重視する」は、失敗してもいいから、とにかくやることを重視してほしいから設けました。
成果を重視すると言われたら、実現可能性のあることしかやらなくなってしまい、チャレンジが生まれにくくなりますから。

会社の中でやりたいことがある人は、まず所属してみる
参加者の方にとって、First Penguin Labに所属することにどんな良さやメリットがありますか?


森本
若手であれば本業をしながら、業務時間内にラボの活動もするので、スケジューリングやマネジメントの訓練やチャレンジにもなります。

福島
個人と会社側それぞれのメリットがありますね。
会社側は、社員にチャレンジの習慣をつけて文化を変えていけるというメリット。
社員側は楽しいことを会社の中でやれて、部署を超えて、社内でつながりをつくれるというメリットがあります。
First Penguin Labに所属している人たちの年齢や職種などの傾向はありますか?


福島
当社はエンジニアが非常に多い会社なので、やはりエンジニアが多いですね。他には営業やスタッフ部門の人もいます。

森本
最近、中途採用で入社したばかりの社員が「もっと会社について知りたくて」と入ってくれるケースも多いです。
「〇〇をやりたい」と周囲に話したら「First Penguin Labならできるんじゃない?」と教えてもらった人もいました。
社内の認知率もかなり高そうですよね。そして、好奇心旺盛な人が集まりそうです。


福島
初期のメンバーは、「何かよくわからないけどやるか」というイノベーター気質の人が多いですね。今は「面白そう」と認識して入ってくる人が増えている印象です。
前職の仕事の経験を、この会社でも活かせたらと考えて、アイデアを持ってきてくれる人もいました。

森本
年齢は30~40代が多いです。業務でリーダーをしているなど、仕事や時間の調整ができる人が多いかもしれません。
若手は目の前の仕事で精一杯なので少ないですが、仕事を覚えてくると、周りを見る余裕ややりたいことが出てくるのかなと思います。
ボトムアップの活動が上層部に応援されるための工夫
First Penguin Labの活動は想定よりも広がっているそうですね。その要因は何でしょうか?


森本
事務局として意識しているのは、型にはめず、適度に緩く、つかず離れずの距離感でいることですね。でも、きちんと支援もする。

福島
「絶妙な緩さ」は大事にしていますね。
事務局として、コミュニケーションの面でどんな工夫をしていますか?


森本
自主性に重きを置いているため、管理はしていません。それぞれがモチベーションをもって進めてもらうのが一番だと思っています。

福島
私は事務局としてというより好奇心で「最近何か面白いことない?」と声をかけちゃっています。雑談している中で何か解決したり、生まれたりすることもあります。

森本
あと、定期的にみんなで集まる発表会のような場を設けています。そういった機会を設けて活動にリズムを生み出しています。
運営面で難しい点はありますか?


福島
やはり人間関係でしょうかね。
確かにプラットフォームにも100人以上いらっしゃると、人間関係の齟齬が発生することもありますよね。


福島
この手の活動では、誰も「こうしてください」とは言えません。だからここはもう、地道に対話をするしかないと思っています。
話してもらって、ちょっとすっきりしてもらう。


福島
対話を通してお互いのこだわりポイントがわかったりすると、相手の言っていることが腹落ちすることもあります。熱意があるのは間違いないので、それを大事にしたいと思っています。
話をしていたら、1日が終わっていたなんていう日もたまにあります(笑)。
おふたりも本業がある中で、First Penguin Labの活動にも多く時間を使われている印象です。
そこまでできるのは、それだけFirst Penguin Labの場を大事にしているからですよね。


福島
そうですね。First Penguin Labの活動を続けることで、この会社の未来がどうなるのかな、という興味が大きいです。

森本
僕たちの普段の本業は、お客様から受注したものを作るけっこうガチガチな仕事が多いです。でも、First Penguin Labの活動には答えがなく、自分たちで仮説を立て工夫できるのが面白いですよね。
事務局のお二人が楽しんで取り組まれていることが、First Penguin Labが長く続いている理由なのかもしれないですね。


福島
確かにそうかもしれないですね。このような活動では、中心人物が主管部門から異動したら終わってしまうこともあります。
でも、私たちが異動したとしてもモチベーションがあればFirst Penguin Labは続けることができますし、終わりを自分たちで決めることもできます。

森本
事務局自体もラボのようなものです。常に試行錯誤して、「これはうまくいかなかったら、今度はこうしてみよう」「こうしたらもっと良さそう」と試しながら変化しています。
常に変化し続けているんですね。


福島
こういった活動は社内でメジャーであることがとても大事です。アングラな活動になってしまうと、会社に影響力がないですから。トップに応援されて、ボトムアップで活動が生まれてくる塩梅が大事です。
その塩梅がとても難しそうですよね。ボトムアップの活動だと会社に認めてもらうのが難しいと聞くこともあります。
トップに理解してもらうためのポイントはありますか?


森本
トップが数年で交代することもあり、会社の方向性も変化する可能性があります。そのため、トップが変わるたびに、First Penguin Labについて説明しに行くことは欠かしませんね。
また、First Penguin Labの活動を上層部は理解してくれていても、現場の管理職の中には本業に集中してほしいと考える人もいるわけです。だから、そのときは地道に個別案件で社員の関わり方を調整して、徐々に理解を得られるように努めています。
興味や関心からスタートし、対話を重ねていく「共創」
First Penguin Labは、社内全体のモチベーションアップや社員間コミュニケーションの活性化など、共創を生み出すことにも貢献していると思います。
働く人が自分の個性や強みを、仕事や他者との共創に生かすためのヒントがあれば教えてください。


福島
自分の興味や関心、やってみたいというポジティブな気持ちからスタートするのが一番ですよね。「面白いからやってみよう」と人に話すと、けっこうみんな話を聞いてくれます。
すると、「じゃあ一緒にやろう」という人が現れたりする。それが共創の一歩になるのかなと。そうしてスキルや情報、人脈がどんどんつながれば、誰かが困っているときにナレッジを共有し合えます。

森本
やりたいことがあっても自分ひとりではできない、ほかの人と一緒なら心強いと思っている人は協力者を見つけるといいですよね。
興味や知識を掛け合わせれば可能性が広がります。

福島
違いを生かすのも大事ですよね。「私はこう思うんだよね」「こっちもいいんじゃない」と対話をしながら進めるというか。
今後、First Penguin Labを通してやっていきたいことはありますか?


福島
「日本のイノベーション文化の一端を担いたい」というのが大きな野望です。
まずはこの活動で培ったノウハウを体系化して、それをまとめて書籍化したいですね。
そしてFirst Penguin Labを社外にも応用していきたいです。別の会社あるいは地域に「First Penguin Lab」の支部を設立してもらうとか。
いつかFirst Penguin Lab協会のようなものが設立されたら面白いですね。
え!?


森本
実は、「First Penguin Lab」で商標登録もしているんですよ。
そのうち、「First Penguin Lab」の名称を使ったビジネスが立ち上がるかもしれない。そうやって世の中に広めていきたいですね。
野望が膨らみますね。今日はありがとうございました!

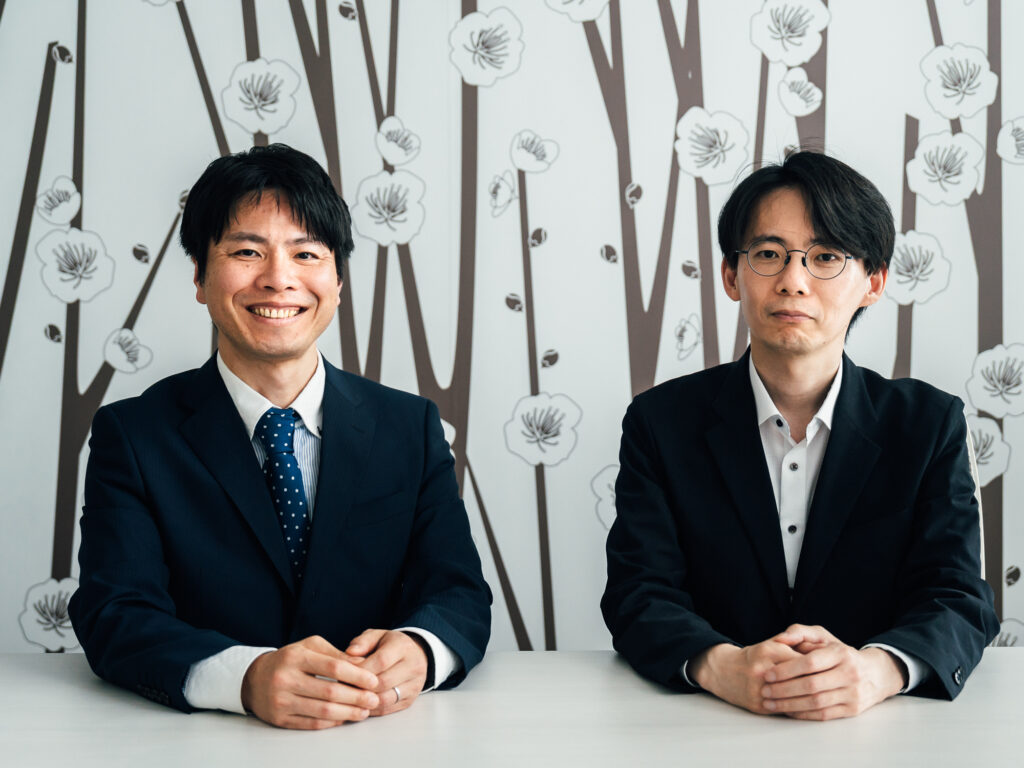

【編集後記】
一人ひとりの「やってみたい」を、すぐ「やってみる」にできる仕組みが企業や組織の中にあれば……。そうは思うものの、言うは易く行うは難し。また、たとえ仕組みがあったとしても、実際に活用・継続できるかは別問題です。だからこそ、「First Penguin Lab」というプラットフォームの形づくる距離感には驚かされました。社員の興味関心を活かしつつ、本業とも良い相互作用を生む、個人と組織との距離感。そして、つかず離れず併走する、ラボ参加者と事務局との距離感。「First Penguin Lab」が形成している「ほどよい距離感」は、チャレンジが生まれやすい土壌をつくり育てていくうえで、大きなヒントになると感じています。(株式会社オカムラ 前田英里)
2025年6月取材
取材・執筆=久保佳那
写真=篠原豪太
編集=桒田萌(ノオト)