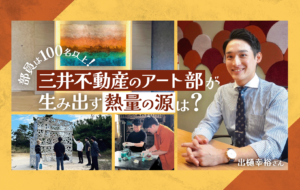仕事のデスクにも感性が宿る。日常美学から考える暮らしの見つめ直し方(研究者・青田麻未さん)

「美学」と聞いて一般的に思い浮かべるのは、芸術作品の鑑賞かもしれません。しかし、その学問が扱う領域は広がり、日常生活も研究対象になってきています。
『「ふつうの暮らし」を美学する 家から考える「日常美学」入門』(光文社新書)の著者である美学者の青田麻未さんは、私たちが身近な生活のなかでいかに感性をはたらかせているのかを教えてくれます。
その営みが、仕事や日々の生活にとってどんなものをもたらしてくれるのか。青田さんに伺いました。

青田麻未 (あおた・まみ)
1989年神奈川県生まれ。2017年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。現在、上智大学文学部哲学科助教。専門は英米系の環境美学・日常美学。著書に『環境を批評する 英米系環境美学の展開』(春風社、2020年)、『「ふつうの暮らし」を美学する 家から考える「日常美学」入門』(光文社新書、2024年)がある。
仕事道具に表れる「感性」と「関係性」
ご著書では、料理、掃除・片付け、椅子、vlog※などの身近な物事を題材にして、「日常美学」を論じられています。美学は身近なところにあるんですね。

※vlog:video blogの略。ビデオ版のブログ。ルーティーンなどを動画にして発信するコンテンツのこと。

青田
はい。何かの事物や出来事に出合うとき、私たちの感性はどのようにはたらいているのか。それを哲学的に明らかにするのが、美学の目的です。
美学とは、原義に立ち返ると「感性の学」と言い換えることもできます。
感性の学……!


青田
日常生活の中での感性のはたらきについて、普段はわざわざ考えることって少ないですよね。ですが、非常に身近なテーマで、1度考えてみると誰にでも関係しているトピックだとわかってくるはずです。
たとえば、仕事に使う道具とも、私たちはそれぞれの感性を通じて関わっています。
仕事に使う道具?


青田
私の場合、仕事をするとき、パソコンが目の前にあり、その左右の隣に考えをまとめるためのタブレットと、2種類の紙ノートも置いています。
2種類のノートは、ぐしゃぐしゃに書く用のものと、決まってきた考えを書く用のものに分けています。それらとタブレットを往復しながら、またパソコンに戻って……。
みなさんもオフィスや自宅の仕事スペースで、自分の作業がしやすいようにものを配置していますよね。こうした道具との関わりによって、仕事という行為がはじめて可能になります。
このとき、私たちは自分の感覚を通じて道具と関わっています。仕事においても、論理や倫理だけではなく感性的な経験が成立していて、これは美学の論題です。
なるほど。


青田
また、道具が自分にとってどういう存在なのか、といったポイントも美学で考えることができます。
たとえば、私は会社勤めではないので、同僚らしい同僚がいないんですね。でも、ノートやパソコン、タブレットこそが、それに値する立場で私と一緒に仕事をしてくれる。
道具であれども、これらと結ぶネットワークこそが美的な応酬であり、このネットワークのなかで私たちはそれぞれの道具の機能美を感じることができる。これも美学の観点の一つです。
私たちにとって、その相手がどういう存在であり機能を果たしているのかが大切なんですね。


青田
でも、時には道具との関係が崩れてしまうこともあります。「今日はノートを1冊忘れてきてしまった」「ペンのインクが切れてしまった」といったことがあると、その関係性における応酬がうまくいかなくなります。
こういう事態は、私たちが、頭というよりも、身体を用いて道具と関わり、仕事をしていることから生じます。つまり、私たちは日常のなかで感性をはたらかせていて、道具や人とのネットワークを構築しているのです。

モーニングルーティーンの動画も日常美学の研究対象に?
「美学」と聞くと、芸術作品のことをイメージしたり、特別な才能を持った人の話のように感じてしまったりしていました。でも、誰にでも関係のあるのですね。


青田
はい。たしかにもともと「美学」という学問がヨーロッパで近代に生まれた頃は、芸術作品が主要な題材として発展していました。
当時は、芸術の社会的ステータスが上がっていった時代。貴族たちが芸術家を庇護したり、教育機関もできたりしていったなかで、芸術について論じる学問として美学も盛り上がっていきました。
なるほど、確かに美学はそういったイメージが強いです。


青田
社会の状況が変わっていくと、学術領域の関心も大きく変わっていくものです。
20世紀後半、環境破壊がひどくなってきたことから、「環境美学」という分野が生まれてきました。
環境美学……?


青田
自然環境、あるいは私たちが住んでいる都市も含めた環境の中で、どうやって感性がはたらくのか。それについて考えよう、という学問です。
つまり、芸術作品だけでなく、環境に対しても同じように感性のはたらきを哲学的に考えることができるわけです。
そもそも芸術と日常生活をはっきりと分ける考え方は、一面的な見方。日常のなかにも、芸術作品を鑑賞するときと同じように、感性をはたらかせている場面がたくさんあるはずです。
だからこそ、料理、掃除・片付け、椅子、vlogなどが題材になるのですね。


青田
そうですね。ただ注意してもらいたいのは、私はいわゆる「ていねいな暮らし」を推奨したいわけではないということです。
ポジティブなものだけでなく、生活のなかで生まれる「これはなんか嫌だ」「不快だ」というネガティブな感情も、感性のはたらきと考えます。
たとえば、私は料理が嫌いです。そこで「私はなぜ料理が嫌いなのか」を掘り下げて考えてみると、日常美学の題材になるのです。
興味深いです!


青田
vlogで見られるようなモーニングルーティーンなどの「ルーティーン」も扱っています。

vlogまで研究の対象になるのは、驚きです。なぜvlogに着目されたのでしょうか?


青田
私が子どもを出産する前に、産婦人科で「育児のやり方が何もわからない」と相談したところ、「今は子育てのvlogがいっぱいあるから見てみて」と言われて。
それがきっかけで、子育てのルーティーンがおさめられたvlogを見始めました。
それもまた、日常の疑問がきっかけになったんですね。


青田
すると、本当にいろんな親子の暮らしがあって。みなさんきれいにビデオに撮られているのですが、自分が実際にやってみるとそんなにうまくいかなかったりもします。そうしたギャップもおもしろいと思いました。
会話や組織から考える日常美学とは
たとえば、働く現場やオフィスにおける仕事なども、「日常」の一つです。
そういったシーンで日常美学の考え方を活かすには、どのようなことができるでしょうか?


青田
人と道具のネットワークと同じように、人と人とのネットワークもあります。
フィンランドの美学者カッレ・プオラッカは、日常美学の領域で「会話」を研究しています。
相手の言ったことに対して、どのように乗っかって、次の展開を作っていくのか。どういうコミュニケーションを私たちは美的によいと、すなわち感性のはたらきによってもたらされる快を与えてくれるものであるのか、と考える研究です。
もう仕事の現場に生かせる研究をしている方がいるんですね。


青田
はい。人と仕事をするときに、自分が一方的に何かをするのではなくて、相手から来た球を打ち返すことで、応酬が生まれますよね。
それは楽しいことでもあり、逆に自分は予定通りにやっていたのにうまく進まなくなることもありますよね。
そうした偶然性を、自分はどう乗りこなすか。さまざまな場面で自分の感性がどのようにはたらいているのか。何を快く感じ、何を不快に感じるのか。
このように感性のはたらきを捉え直してみるのも、日常美学の一つです。
ほかには、仕事への美学の活かし方はありますか?


青田
美学にはさまざまな領域が生まれてきています。
海外では、日常美学の研究を応用しながら、特に会社や組織のあり方について美学的に考える研究も出てきています。組織美学(organizational esthetics)と呼ばれていて。
どんな研究なのでしょうか?


青田
仕事は、機械的で合理的なものと捉えられがちですよね。でも、実際にそういった職場の環境が良いのかというと、そうではない面もかなりあって。
機械的かつ合理的な職場では、人間を脳や精神だけの存在として考えている面があります。しかし、人間は身体を持って生きたり働いたりしている。
システムの側をガチガチに考えるよりも、働いている人、やオフィスを構成しているものが相互に作用で生まれたリズムと感性を職場作りに活かせるのではないか。そんな研究です。
自分の快・不快を、時間をかけて発見する
仕事をしていると、どうしてもマンネリ感を抱くときがあると思います。日常美学の考え方が、助けの一つになりそうです。


青田
個人的な話になるのですが、私は高校時代、職員室で一人ひとりの先生の違った机を見るのが好きだったんですね。
机自体は整然と並べられているけど、それぞれの机にぬいぐるみが置いてあったり、付箋がたくさん貼られていたり、プリントをうずたかく積み上げている人もいたり。
これは、自分だけが楽しんだり、自分に合った方法で仕事をしたりできるための工夫だったのかな、と勝手に思ったんですよね。そこにある道具が、いわゆる「新奇さ」を取り入れてくれている。

仕事におけるマンネリ解消にもつながっている、と。


青田
ただし、一方で「マンネリは本当にダメなのか?」という視点も大事だと思います。
どういうことでしょうか?


青田
今の生活に満足できない原因をよく考えてみると、他人との比較や社会の目を気にしているからであることが多い気がしていて。
たとえば、Instagramで他人の生活を見ていると、信じられないほどきれいな暮らしがいっぱい出てきますよね。YouTubeのモーニングルーティーンのvlogを見て、「自分にはできないな」と思ってしまう。
でも、その生活が本当に自分のしたいものなのかというと、実はそうではないことも多いと思うんです。
そうですね……。


青田
もちろん、生活に改善の余地がある場合もあります。でも、本当はそんなに問題でないことを問題に思わされてしまう構造も、わりとあると思うんですよ。
おっしゃる通りだと思います。では最後に、そうやって他者に惑わされずに生きていけるのか、ヒントを教えてください。


青田
内発性を大事にすることでしょうか。他人に言われたことを鵜呑みにするのではなく、自分のなかの快/不快の基準を探す。社会の大勢が作り出す感性のありかたに流されてしまうのではなく、自分の感性が作り出す世界を意識する。
日常美学の視点を持つことができたら、自分の仕事や生活に対する不満を減らすことにつながると思います。
なるほど。自分の感性を大切にすることで、得体の知れない焦燥感やモヤモヤの解決の糸口も見えてきそうです。


青田
そうですね。焦ったときにとりあえず突き進むのではなく、一つひとつの物事に感性をはたらかせて、時間をかけてきちんと考えることが大切だと思います。
立ち止まるきっかけはなかなかあるものではありませんが、日常美学はその役に立つと思います。
ありがとうございました。

2025年2月取材
取材・執筆=遠藤光太
アイキャッチ制作=サンノ
編集=桒田萌/ノオト