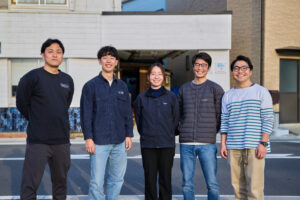未来づくりの主語はワカモノ!「未来共創ドラフト会議in松下記念病院」で共創が生まれる瞬間をレポート

2025年5月17日に大阪府守口市にある松下記念病院で、「未来共創ドラフト会議」が開催されました。
「未来共創ドラフト会議」とは、未来を担う「ワカモノ」たちが、未来を良くするアイデアをプレゼンテーションするイベントです。企業や団体が、その中から注目するワカモノを“ドラフト指名”。社会実装の機会創出を推進するマッチング企画です。
そもそも、なぜ病院がこのようなドラフト会議の場に? そして、実際にどのようなプレゼンが行われたのでしょうか?
今回はドラフト会議のレポートをお届けするとともに、主催した一般社団法人病院マーケティングサミットJAPAN 代表理事の竹田陽介さんと、松下記念病院の村田博昭病院長、前 松下記念病院 経営企画室(現 パナソニック健康保険組合 産業保健センター 事務管理部企画課)の乗替寿浩さんにお話を伺いました。
未来共創ドラフト会議とは
未来づくりのプレーヤーとなるワカモノがアイデアをプレゼンし、監督役である企業や支援者がドラフト指名するマッチングイベント「未来共創ドラフト会議」。
プレゼンを行う “ワカモノ”は、中学生から社会人までのあらゆる世代ですが、年齢の若さではなく「心が生き生きしてやりたいことがある人」を指すそう。
主催しているのは、一般社団法人病院マーケティングサミットJAPAN。病院や医療に関する広報やマーケティングや、各地の病院と他分野企業、行政、各種団体との共創活動を支援してきました。「未来共創ドラフト会議」もその一環で行われたものです。


竹田
病院マーケティングサミットJAPANは、病院を舞台に、人々のウェルビーイングや暮らし、年代や分野、地域を超えた共創を支援してきました。
「未来共創ドラフト会議」は、いわばそんな「ビジョンの共有」の場であり、その担い手が集まり、未来づくりを行うキックオフの場になると考えています。
すでに各地で行っており、“ワカモノ”と監督役の企業とのコラボレーションも多く生まれています。
「未来共創ドラフト会議」の舞台となる松下記念病院もまた、医療提供に限らず、未来のくらしに寄り添う病院として地域の人々や企業・団体との共創活動に取り組み、地域に開かれたイベントマルシェを積極的に開いてきました。そんな病院の姿勢について、村田博昭病院長はこう語ります。


村田
病院は、医療を通して患者様と向き合うことはもちろんのこと、その先にある暮らしも大切にしなければいけないと思っています。
だからこそ、松下記念病院では、本丸の医療行為にとどまらず、「人も地域も健やかにする」ことを大切にしてきました。
そのためには、この病院が地域に広く開かれた場所であることを知っていただかなければいけない。そんな思いで、さまざまな地域向けのイベントを実施してきました。
「人も地域も健やかに」という松下記念病院と、医療×多分野の共創をテーマに活動を行う病院マーケティングサミットJAPANの活動には、親和性があります。実際、乗替寿浩さん(前 松下記念病院 経営企画室)と竹田さんは、これまでの活動を通じて共鳴するポイントがあったといいます。


乗替
僕も常々、病院を通じて、企業や行政、地域、世代を超えたコミュニティの未来をつくりたいと考えてきました。そこで竹田さんに相談し、昨年の「わくわく未来共創カンファレンス」開催に繋がり、今回の「未来共創ドラフト会議」への下地になったんです。
「自分はこれがやりたいんだ」というアイデアを持っていても、実際に行動に移せる人は多くありません。でも、これまでの「未来共創ドラフト会議」では、ワカモノに影響されて「自分も」と感銘を受ける人がいるはず。
そんな、他のイベントでは味わえない体験価値がある「未来共創ドラフト」をいつか松下記念病院でも開催できたらと思っていたので、この日を迎えられて嬉しいです。
プレゼンターの熱い発表に、触発される監督たち
では、ここで「未来共創ドラフト会議」の様子を実際にレポートしましょう。

会場には病院の共創企業や団体、また松下記念病院などさまざまな組織から総勢20名の監督たち、そして観客が集まりました。監督たちは4つのチームに分かれ、ワカモノプレゼンターたちの発表を見守ります。

今回プレゼンする“ワカモノ”は6組で、分野は医療や農業、地域支援などとさまざま。プレゼンターたちに与えられた時間は、1組あたり7分間です。全員のプレゼンが行われた後に、4チームそれぞれが2巡ごとに高評価をつけたワカモノを“指名”する……という流れです。
実際に、どんなワカモノが登場したのでしょうか? 今回は、特に注目を集めた3組を紹介します。
最初に紹介するのは、島根大学医学部4年生の上西凛太郎さん。5浪で島根大学医学科に入った苦労人です。上西さんは、地域医療に携わる機会やナレッジを共有するコミュニティを運営しており、その活動についてプレゼンを行いました。


上西
私たちは、オンラインコミュニティやイベントなどを通して、地域医療に関わるさまざまな知見や知識を得られる場所を設けたいと思っています。
医学部に通う学生たちは、医療に関する専門知識を学ぶことはあれど、その背景にある生活や実態について学ぶ機会は多くありません。だからこそ、このコミュニティでは、実際に地域の皆さんやさまざまな世代や職種の方と関わりながら、多様な視点を身につけられる機会を作りたい。そんな学びの場にしていけたらと思います。
上西さんがこういったコミュニティを運営しているのは、自身が沖縄の離島で育った経験が背景にあるといいます。進路や勉強に関する情報を手に入れることのできない環境で育ったことから、「どんな選択肢があるのかがわからない状態だった」と上西さん。

上西
だから、このコミュニティ活動は、医学部生たちにさまざまな選択肢を提示する「キャリア教育」だと考えています。
熱く語った上西さんには、監督の一人から「サービスを提供する相手の視点に立つという、マーケティング的なポイントを押さえられていて素晴らしい。医療従事者の意識醸成に向けた取り組みに加え、自身の経験を踏まえたプレゼンは非常に説得力がありました」と評価があり、のちにドラフト1巡目で1チームから指名がかかりました。
次にドラフト指名を集めたのは、現役消防士の宮谷英穂さんです。宮谷さんがプレゼンしたのは、自身が共同代表理事を務めている、地域の防災力を高めることを目的とした「一般社団法人予防団」の活動について。
普段から地域に向けた防災訓練や研修会、イベントを開催している宮谷さんは、「防災には地域コミュニティの存在が不可欠」と話します。


宮谷
近い将来発生すると言われている南海トラフ地震は、極めて大きな被害が想定されています。防災力を高める上で欠かせないのが、地域コミュニティです。
僕たちが普段開催している研修会やイベントでは、地域の参加者一人ひとりに防災への意識を高めてもらい、ゆくゆくはみんながそれぞれに地域の防災リーダーとなってもらうことを目指します。
また、地域コミュニティに加えて、産官学民の連携も必要不可欠だという宮谷さん。その中心となる行政で働く公務員こそが、地域や市民と同じ目線に立てるよう、さらに地域活動に入り込んでいく必要性を力説。
宮谷さんが代表理事を務める予防団こそが、そのロールモデルになっていくのだと展望を語りました。その熱に圧倒され、1巡目と2巡目あわせて3チームより指名を受けました。
最後に、中でももっとも多くの指名を受けたのが、現役中学生の古川立夏さん。農業人口を増やすための取り組みを行っています。
いま、農業従事者の7割以上は65歳以上で、農業人口が減っているのが現状です。そこで古川さんは、農業従事者と、農業に携わりたい消費者をマッチングさせ、農業の人口不足を解消する仕組み「SAP」を考案し、プラットフォームを運営しています。


古川
SAPの会員向けに行っている「通い稲作塾SAPきりしま」では、農業に興味のある消費者に向けて、稲作の知識が身に付く体験の機会を提供しています。農業従事者は不足している労働力をまかなうことができ、消費者側は稲作を体験することで、対価として作物を受け取ることができます。
今後は農業人口を増やすだけでなく、耕作放棄地の解消や食料自給率アップにも貢献していきたいと考えています。
課題解決に向けた具体的な取り組みに、ドラフト1巡目で、4チーム中3チームの指名を取りました。
他にも国際協力や介護など、さまざまなジャンルで発表があり、それぞれのワカモノの熱量の高さに、喜びながら頭を抱える監督たちの姿が印象的でした。

また、ワカモノたちの熱い思いに監督たち本人が影響を受けている様子も見られました。もしかすると、この中から実際に何かしらの支援や共創につながる可能性もありえます。

ドラフト会議を終えた後、村田病院長から「みなさんの生き生きとした表情が見られた本当に良かった。これにとどまらず、活動内容をブラッシュアップさせてほしいですね」とポジティブなコメントがあり、ワカモノたちを大いに勇気づけました。
「ドラフト会議は、未来をつくりたいワカモノと、それを応援したい人々をつなぐための一種の演出。実際に賞金の出るピッチコンテストとは異なります。ワカモノのパッションに呼応して大人のハートに火がつくという、未来へ踏み出すための一歩に過ぎないんです」と竹田さん。
このドラフト会議は、ワカモノや監督、オーディエンスの心にある情熱を原動力にし、共創のきっかけをつくる熱い舞台装置なのかもしれません。

2025年5月取材
取材・執筆=國松珠実
写真=古木絢也
編集=桒田萌(ノオト)