世界に向かって“本当の自分”をさらけ出す。万博を舞台に今始まる、ザ・オカムラ座の挑戦

2025年4月13日から開催される大阪・関西万博。各国の英知やアイデアが集結する世界的イベントの幕開きまで、1週間を切りました。
しかし、「万博って、結局何をするの?」「自分には関係なさそう」「興味はあるけど、どうやって関わればいいのかわからない……」と、どこか「他人事」に捉えてしまう人が多いのでは?
その一方、万博に向けて「勝手に」盛り上がり、続々とたくさんの人を巻き込み、共創の渦を生み出している企業・人々がいます。
本連載では、大阪・関西万博に向けて「勝手に」生み出されたムーブメントに着目し、その仕掛け人たちの胸の内を取材していきます。
「ラクワクしようぜ、万博」というメッセージのもと、仕事に遊び心を取り入れ、働く楽しさを伝えるため万博で展示と催事に出展するオカムラ。相手に伝えたい素直な気持ちを交換できる7日間限定のお店「キモチキオスク」では、体験型展示を開催します。

そして、世界中の人たちにその価値観を届ける手段として、2025年4月26日(土)大阪・関西万博で、「ザ・オカムラ座」を公演します。
オーディションで選ばれた12人の社員たちが大阪・関西万博会場の舞台に一堂に集結。言葉を使わず演技やダンスで自己を表現する「ノンバーバル」という手法を通して、同じ毎日を繰り返す12人の会社員が、あることをきっかけに自らの会社における働き方に疑問を抱き、自分の殻を破って解放する様子を披露します。
音楽とダンス中心で構成されたノンバーバルな舞台に立ち、ラップでプレゼンをしたり、アイドルの衣装を着て出社したり、宇宙で仕事してみたり……12人の主役の個性が爆発した働き方を表現します。
今回は、万博で演技を披露する12人のうち3人の社員に集まってもらいました。なぜザ・オカムラ座に参加しようと思ったのか、世界へ向けて伝えたいメッセージとはどんなことかなど、忌憚のないクロストークを交わします。

ワクワクする気持ちに突き動かされて、万博の舞台へのチャレンジを決意

万博のザ・オカムラ座の舞台当日まで、いよいよ1カ月半に迫りました。練習の進み具合はどうですか?


山本
個人練習で1回、振り付けだけやりましたね。僕は今日このあとまた練習があるんですよ。

田村
私も今は個人練習が多いですね。全体練習もあって、みんなで集まって稽古する回もあります。

角井
そうですね。それぞれ業務の合間を縫って練習するので、基本的には個人で曲に合わせてダンスを覚える、いわゆる振り入れをやっています。まだまだこれから詰めていく段階なんですよ。
一般的にイメージする演劇の練習とは少し違うんですね。皆さんは、なぜザ・オカムラ座の舞台に出ようと思われたのですか?


山本
社内公募だったんですけど、それを見たときにすごくワクワクした気持ちが湧いてきて、「このワクワクに乗っかるしかない!」と思いました。それから僕、実は結構闇を抱えて生きてきたんですよ。
闇とは、一体どういうものなのでしょうか……?


山本
今は営業支援を担当しているんですが、その前は営業職に就いていました。当時、仕事が全然うまくいかなくて、ミスを何度も繰り返していたんです。それをごまかすように、毎日無理に楽しそうに振る舞っていた時期がありました。

田村
そんな過去があったんですね……! 意外です。

山本
最近ようやく、その闇も払拭されつつあるんですけどね。ただ、ザ・オカムラ座の企画を聞いたとき、「この機会を通してずっと抱えてきた僕の闇を爆発させてみたい!」と思ったんです。

角井
熱いですね!
田村さんはなぜ応募されたのですか?



田村
私も一番は、ワクワクする気持ちに従いました。あとは、自分の普段の働き方を大勢の方に知ってもらいたいという想いが強かったですね。私はろう者なのですが、同じくろう者として働いている人にはもちろんのこと、普段交流することのない他部署のメンバーにも舞台を見てほしいです。

山本
万博なので、社内はもちろん、社外の幅広い人にも見てもらえる良い機会ですね。

田村
そうなんです、例えば学生にも見てほしいです。学生の頃って私もそうでしたが、ろう者は自分のキャリアを想像するのは簡単ではないと思います。ザ・オカムラ座での演技を通して、そうした若い人たちがキャリアを考えるときの、何かしら参考やヒントになればうれしいです。
角井さんはどうですか?


角井
ダンスや舞台経験は多少あったんですけど、どちらかというともともと万博に興味があって、「万博、見に行ってみたい!」という気持ちが強かったですね(笑)。会社の企画で万博に行けるなら最高だなと思っていて、オーディションを受けてみたところ、幸運にも合格しちゃったんです。
オーディションもあったのですね。そのときの様子を教えてください。


角井
舞台の企画をプロデュースする株式会社人間さんと、オンラインで1時間じっくり面談をしましたよね。

山本
しましたね。僕、事前に志望動機や自己PRなどを盛り込んだ完璧な台本を用意して、全て暗記までして臨んだんですよ。でも面談では全く必要なかった。

田村
私も山本さんと同じです。ありきたりな質疑応答みたいなものはなくて、生い立ちから内面まで応募者のことをじっくり掘り起こすような、自分が丸裸にされてしまうような、とても印象深いオーディションでした。
普段働いている姿をそのまま演じることで、日々の想いをさらけ出す

本番では、皆さんが自分役として、ノンバーバルという言葉を使わない手法で舞台が展開されていくと伺いました。何をどんな風に演じるのですか?


田村
出演者たちが、まさにいつも働いている動きそのものをダンスに取り入れます。名刺交換をするとか、工場のラインの動作をするとか……。私はデスクワークが基本なので、書き物をしているところなどを演じます。山本さんはどんな動きなんですか?

山本
演じるというよりは、表現に近いかもしれません。「主役が僕」というか。一応動きに取り入れたのは、営業支援ということで、あちらこちらに声をかけてまわるみたいな部分ですね。一貫して、ワクワクさせるキャラでありたいとは思っています。
角井さんはどんな演技をされるんですか?


角井
私はオーディションのときに、「長女らしさ」「社会人らしさ」をいつも意識しながら生きているという話をしたので、なんとなくそれを意識して演技しようということになりました。動きとしては、先輩の後ろでメモを取ったり、コピーを取ったりしてそれを道端にぶちまけちゃうみたいな、少しコミカルな雰囲気だと思います。

田村
構成も凝っているんですよ。今はまだ一幕しか練習していないんですが、二幕、三幕と進むにつれて、自分の内面をどんどんさらけ出していくような演出になっています。
舞台を通して、これまでに感じてきたモヤモヤや葛藤をさらけ出し、乗り越えることはできそうでしょうか?


山本
「僕が営業時代にしてきたたくさんのミスに比べたら、みんなの抱えている悩みなんてたいしたことないよ!」という境地まで、最近ようやくたどり着くことができたので、それを表現して見る人を力づけたいですね。特に、今僕が営業支援をしている若い営業メンバーに、「大丈夫?」「何か助けられることある?」と自分なりに手を差し伸べたいという思いが強いです。
闇を経験してきた山本さんならではの表現ですね。角井さんは、アイドルに憧れを抱いていると聞きました。


角井
そうなんです。大学卒業後の進路を考えていた頃に、オーディション番組に勇気づけられた経験があって。アイドルを含め、表舞台に立って人を元気づける仕事って素敵だな、と思ったことはありましたね。でも実際には、大学を出て就職して……という安定した道を選びました。

山本
そのときに葛藤はなかったんですか?

角井
一時期は人とは違う道を選ぶことに憧れを持っていました。でも私、結構着実な方を選ぶ性格なので、最終的にこの環境にいることに後悔はないんです。だからこそ、今回のダンスを通して、そのときに挑戦できなかったことを思い切りぶつけてみたいな、と考えています。

田村さんはどんなことをさらけ出してみたいですか?


田村
ろう者が聴者社会の中で仕事をする上で、やっぱり難しいなと思うことはあります。私は学生時代、ずっとろう学校に通っていて、就職して初めて聞こえる人たちの文化の中に入ったんですね。そこでカルチャーショックを感じたことがあって……。

角井
どんなことだったんですか?

田村
ろう者は結論ファーストで話したり、婉曲表現を避けて直接的な言い回しにしたりする人が少なくありません。でもそれは日本人の聴者からすると驚くかもしれません。もしかしたら私も今まで「ストレートな物言いをする人」と思われたことがあるかもしれないですね。

山本
たしかに直接的、または露骨に言うのを避けて、曖昧な表現を好む人も多いですね。

田村
だから、入社当時は同僚のたわいもない会話がよく分からなくて。「で、結局何を言いたかったんだろう?」って思うこともしばしばありました。言われた方がその言葉の真意を察する聴者の文化、コミュニケーションが当時の私は分からなかったです。そういう文化の違いも含めて、ろう者の感じている世界を表現してみたいなとは思っています。
個性を知り認め合うことで、もっと働きやすい社会は実現できるはず

皆さんの想いや表現しようとされていることがイメージできてきました。当日への意気込みを聞きたいです。


角井
若手社員代表として、これからオカムラへ入社してくる人、あるいは自分の夢を追いかけている若者に向けて、「これからいくらでもチャレンジできるんだ」という夢やエネルギーを与えられたらうれしいです。私がアイドルからたくさん力をもらってきたように、今度は私がそういう存在になれたらと考えています。

山本
いいですね。僕はやっぱり同じ職場で働いているメンバーに、「なんかワクワクしてるおじさんがいるぞ」「こんなヤツが一人くらいいても面白いな」と感じてもらえたらいいなと思っています。なにかあったときに、気軽に相談できるメンバーがいることを知ってもらいたい。あとは、過去に迷惑をかけた人たちに、「今は楽しくやっています」と伝えたいです。
田村さんはいかがですか?


田村
私は「オカムラの中でろう者」という面で見れば、一見少数派・マイノリティですが、どんな人でも多数派の面、少数派の面はあると思います。多数派の意見ばかりに目が向きがちにならないよう、一人ひとり「個人」として見ることが必要だと感じます。

山本
社内にはいろいろな人がいるんだということが、もっと浸透していけばいいと僕も感じています。それは外見的なことだけじゃなく、性格や得意不得意みたいな特性もそう。それぞれが別の人間だということが認知されたら、ミスが許容される温かい職場になると思うし、みんながもっと働きやすくなりますよね。

角井
そうですね。今の時代、いろいろな働き方があるということは世間で浸透しつつあるけれど、田村さんと一緒に活動することで、より私の中でそれを実感できたのはすごくいい機会でした。

田村
ちょっとスケールは大きいかもしれませんが、ザ・オカムラ座を通して、世界中に向けて「日本にはこんな働き方もあるんだよ」「多様な人がいて、それぞれがこんな風にがんばっているよ」ということを伝えられたらいいなと感じています。
職場にもっと余白があったっていい。オカムラだからこそ世界に発信できること
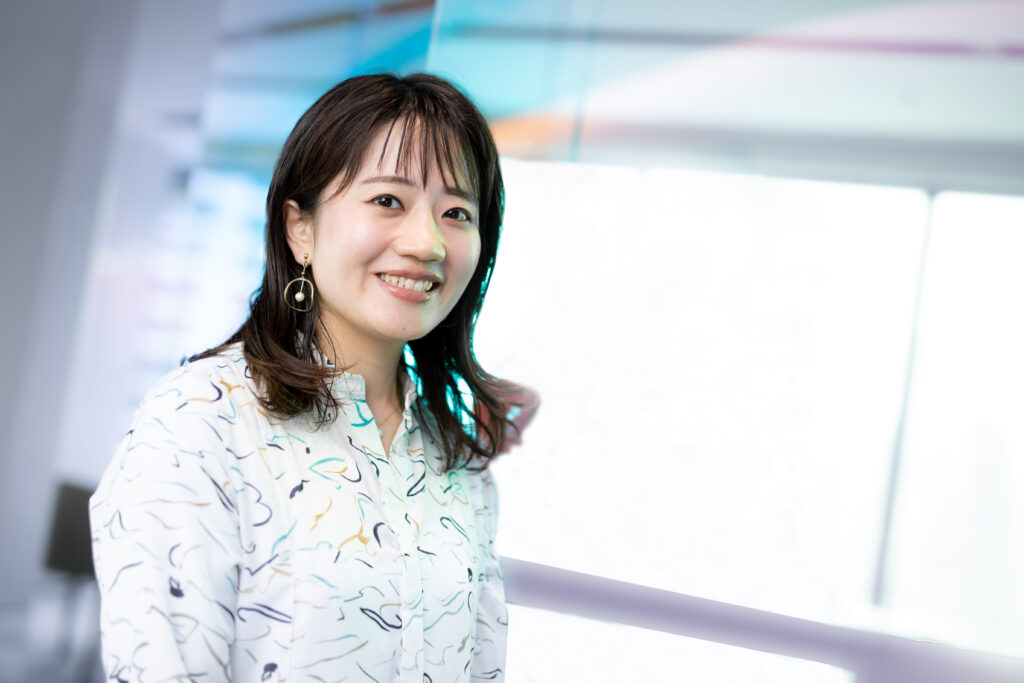
今回のザ・オカムラ座を統括している岡本 栄理さんに万博の出展を決めた経緯を聞きました。
岡本さんが万博の出展を企画することになったきっかけを教えてください。


岡本
オカムラは万博の機運醸成公式イベント・EXPO PLL Talksの枠で「ラクワクしようぜ、万博」というイベントシリーズを2025年日本国際博覧会協会と共催で開催し続けていたんです。その縁から、今回催事出展の枠をいただきました。「ラクワク」は「ラク=楽しい」+「ワク=WORK」を組み合わせてつくった言葉なんですね。ここには「仕事って面倒な一面があるけど、遊び心を持って楽しむことが大事だよ」という意図が込められていて。
仕事=ちょっと面倒なこと、みたいな価値観って世界共通だったりしますもんね。


岡本
そうなんです。「仕事は大変な一面もあるけど、楽しんだもの勝ちでもあるよ」と伝えたくて。
なぜ演劇という手法を選んだのでしょうか。


岡本
世界中の人に伝えるためにはノンバーバルである必要があります。そこで、言葉はなくても、音楽を用いたり人が体を動かしたりすることで、「面白そうだから立ち寄ってみよう」と思ってもらえるステージづくりを考えた結果、演劇にたどり着きました。
演劇の内容はー企業の社員が挑戦するのは、前衛的な試みかも……? と感じましたが周囲の反応はどうでしたか?


岡本
オカムラって、外からも中からも、少し堅い会社だと思われているんですよね。でも実は「やってみたい」と言えば、まずは腰を据えて話を聞いてくれる一面もあるんです。プレゼンを聞いた社長や役員からは、「全事業部、全グループ会社も巻き込んでいいから、思い切りやってみなさい」と言ってもらえて驚きました。自分でもどうなることかと思いましたが、オカムラには挑戦を後押ししてくれる社風があるんです。
素敵ですね! 社内公募を実施したとのことですが、思うように応募者は集まりましたか?


岡本
想定の10倍以上集まりました(笑)。演者や当日の運営、裏方を含め、108人の方が応募してくださって、皆さん「この機会に自分を変えたい!」と熱い気持ちをぶつけてくれて驚きました。オーディションの結果、12人を選出しましたが、ぱっと見ではわからない内面のユニークさが際立っている方ばかりです。
ザ・オカムラ座を通して、見る人にどんなことを伝えたいですか?


岡本
世界的に見ても、日本の働き方ってあまり健全ではないように映りすぎているな、と感じていて……。でも実は良いところもたくさんあると思うんです。オカムラという会社自体が「共同の工業」を掲げて創立されましたが、一人ひとりがいいものを持ち寄ることで、きっと素敵なものを生み出すことができるはずなんですよね。
オカムラだからこそ、世界に向けて発信できることがあるんですね。


岡本
はい。これまでの働き方には、良い面も悪い面もあるかもしれないけれど、これを機に少し立ち止まって考えてみようよと。職場にもっと余白を持ち込んでいいんじゃないかな、ということを伝えたいです。その先に、個性が際立った創造性の高い働き方が生まれるんじゃないかな、と期待しています。
出演者3人の仕事や社会に対する熱い想い、そして統括である岡本さんの「一人ひとりがいいものを持ち寄れば、きっと素敵な世界が待っている」という信念。きっとザ・オカムラ座の舞台をより説得力のある、魅力的な舞台として形にしてくれるはずだと感じました。2025年4月26日の公演に向け、自らのアクトに磨きをかけていく出演者から目が離せません。
2025年3月取材
取材・執筆:波多野友子
撮影:齋藤大輔
編集:人間編集部/南野義哉(プレスラボ)












