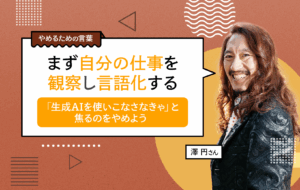AIと人間が共存するには? サンフランシスコの最前線から見える、AIが生み出す未来と“リアル”の価値(btrax CEO・ブランドン・K・ヒルさん)

AIの進化は、私たちの働き方にも変化をもたらしました。AIに仕事をサポートしてもらっている人もいれば、「AIに仕事を奪われるかも」と戦々恐々としている人もいるのではないでしょうか。
今回、最新のAI活用事例やグローバルなAIトレンドについて話を伺ったのは、サンフランシスコを拠点にデザインコンサルティングを手掛けるbtrax(ビートラックス)CEO、ブランドン・K・ヒルさん。2025年9月に世界最大級のAIコミュニティ「The AI Collective」の日本代表に就任され、AIとデザインの最前線を日本に伝える活動をしています。
AIと人間が共存するにはどうすればいいのか? AIからイノベーションは生まれるのか? AIと人間の関係性について、ブランドンさんが描くビジョンを伺いました。

Brandon K. Hill(ブランドン・K・ヒル)
サンフランシスコ州立大学デザイン科卒。デザインコンサルティング会社ビートラックスの創立者・CEO。サンフランシスコ市の政府のアドバイザーを務めるほか、Tech in Asia、Web Summit、RISE Conferenceを含める数多くの国際カンファレンスに登壇。また、経済産業省「始動 Next Innovator」、J-StarX、Startup Weekendで公式メンターや九州大学フェローを務めるなど、日米をつなぐ次世代支援に取り組んでいる。世界最大のAIコミュニティ The AI Collective 日本代表。
アメリカは「どう作るか」、日本は「どう使うか」
「The AI Collective」とは、どんなコミュニティなのでしょうか?
私が拠点にしているサンフランシスコは今、AIスタートアップがものすごくたくさん設立されています。AI関連のイベントも、毎日4~5件は開催されていますね。ただ、イベントではエンジニアが最先端のテクノロジーについて話すことがほとんど。私はデザイナー出身の人間なので、難しすぎることも多くて。
その中で「The AI Collective」のイベントは、とても話がわかりやすかった。「このサービスを日常生活にこう役立てています」など、普通の言葉でAIの知見を共有するコミュニティだったんです。
もともと「AIが難しいからお互い教え合おう」とホームパーティーを開いたことが設立のきっかけらしく、口コミで人が集まり、今では世界80都市以上で活動するコミュニティにまで成長しました。何度か参加するうち、日本ではまだ「The AI Collective」が開催できていないと知り、手をあげて代表になった形ですね。

すでに日本でも、キックオフを含めて3回のイベントを開催されたと聞きました。日本とアメリカ、AIの活用に違いを感じる点はありますか?
アメリカでは「どう作るか」が注目されるのに対し、日本は「どう使うか」についての関心が集まっているように思います。日本でも生成AIを使う人は急激に増えていますし、「アメリカの次にユーザーが多いのが日本」というAIスタートアップも少なくありません。
その一方で、日本で作られたAIサービスは非常に少ない。作る側ではなく、受け手側になっている。そこはもったいないなと思います。
日本発のAIスタートアップで、ブランドンさんが注目されている企業はありますか?
アニメ制作のAIプラットフォームを作る、AiHUB株式会社です。自分たちでアニメ制作を行うほか、アニメ制作会社向けのAIツールも提供している。まさに日本ならではの取り組みですよね。
アニメ産業は世界的にも急成長していますし、「AI×アニメ」はまさにトップとトップの掛け合わせです。ただ……、今のアニメ配信サービスのトップ3は、Netflix、Amazonプライムビデオ、Crunchyrollですべてアメリカ発。結局、アメリカにお金が流れているんですよね。そういう点では、日本企業にはもっと頑張ってほしいです。
「AIを使うデザイン会社」になるために決めたこと
ブランドンさんの専門分野であるデザイン領域では、AIはどのように活用されているのでしょうか。
生成AIの出力の中で、特にインパクトがあるのが画像と動画ですよね。最近は実写と見分けがつかないほどリアルなものも出てきています。
ただ、デザイナーやクリエイターにとっては、生成AIの出力をそのまま成果物として使うことはできないんです。アイデア出しやラフ案のレベルならまだ使えますが、最終的なアウトプットはまだ人間が手を加える必要がありますね。

生成AIの出力を最終的なアウトプットにできないのは、どういった理由があるのでしょうか。
2つあります。1つは、受け手が違和感を覚えること。AIで作られたものは、見る側にもなんとなく伝わるもの。「これAIで作ったよね」という言葉には、「手を抜いている」というニュアンスが含まれます。
逆に「これAIなんだ、すごいね」と言われても、それはAIがすごいのであって、クリエイターがすごいわけではない。どちらにせよ、「AIで作られたもの」と思われた時点で、クリエイターにとっては“負け”なんです。
もう1つは、細かな修正が難しいこと。AIの出力は、クリエイターにとって「なにか足りない」と感じることが多いんですね。間の取り方とか、画角とか。
でも、AIにプロンプトで修正を指示しても、指示するたびに違うところが変わってしまったりする。そうなると何度も何度も修正指示を繰り返すことになり、スケジュールの目処が立たなくなってしまいます。
わかります。「ここだけを直してほしいのに!」とイライラしたりしますよね。
先日、AIの映像制作を専門にしている広告会社と話したんですが、「AIと実写の映像を融合させるといい」と言っていましたね。既存の映像を読みこませて、その前後のシーンを作ってもらったりするそうです。元の映像が実写なので、見ている方も違和感が少ないのだとか。ハリウッドのCGに近い感覚ですよね。
なるほど。ブランドンさんがCEOを務めるbtraxでも、AIを活用されていますか?
まさに2025年の夏に「AIを使うデザイン会社になろう」と決断したところです。AIを使うのか使わないのか、会社としてきちんと方針を定めないとスタッフも不安になりますし、隠れてAIを使うことによるリスクもありますから。
AIの使用にあたってはガイドラインを作り、スタッフに説明しました。内容はこの5つです。
① 業務フローにAIを積極的に使う
② ツールのリサーチは継続的に行う
③ AIを前提としたUXデザインプロセスを導入する
④ AIエンジンに認知されるブランディングをする
⑤ AIのコミュニティを作る
①②は業務効率化の取り組み、⑤はThe AI Collectiveですね。③はメルカリを例に説明しましょう。メルカリでは出品する商品の画像をアップロードすると、AIが画像を認識して自動的に説明文を書いてくれる機能があります。メルカリ自体はAIツールではありませんが、AIがユーザー体験を向上させているわけです。
こうした取り組みは、今後当たり前のものなってくるでしょう。デザイン会社としては、AIを前提にしたUI/UXを設計できるようにならなくては、と考えています。
④はAIに向けたブランディングの話です。AIに「銀座でおすすめのお寿司屋さんを5つ教えて」と聞いたら、5つの候補が出ますよね。この5つの中にクライアントの寿司屋が入れるようにしよう、というものです。
AIに向けてプロモーションをする……ということですか?
その通りです。これまではGoogleの検索結果に出るためのSEO(検索エンジン最適化)が重視されていましたが、今はAIの検索結果に出るためのAIO(AI検索最適化)の時代になってきています。AIに向けてのブランディングは、今後ますます重要になるでしょうね。
こうしたAI使用のガイドラインを作ることは、他の会社でも大事になってくるでしょうね。
これまではCTO(最高技術責任者:Chief Technology Officer)が目利きとなって、新しいツールの導入などを決めていました。今後はそれのAI版となるCAIO(最高AI責任者:Chief AI Officer)が重要になるだろうと言われています。
CAIOの役割は人事部長に近いんです。どんなAIを採用して、どこに配置して、どういう役割を担ってもらうか……という話ですから。それにはAIに対する知識だけでなく、自社サービスの理解や、導入効果の予測、セキュリティリスクなど、考慮すべきことが多岐に渡ります。ですので、これをこなせる人材の確保が課題なんですね。
総務部、人事部など、それぞれの部署の専門性とAIの知識の両方を持った人が必要です。1人ではとても無理なので、今後は1つの独立した部署になるかもしれません。
人間ができるのは「責任を取ること」「信頼を築くこと」
サンフランシスコで、オフィスでの業務にAIを取り入れている事例はありますか?
サンフランシスコの行政機関では、2025年の春から従業員3万6000人全員がMicrosoftのCopilotを使って業務を行っています。
他にも、MicrosoftやGoogleのサービスは多くの会社が使っていますから、これにAIをつなげれば、議事録の自動生成や、プレゼン用のスライド作成などのサポートもやってもらえる。この辺りは基本的なところなので、あくまでここはスタート地点でしょうね。
「AIに仕事を奪われるのでは」と不安に思う声も聞かれます。AIと人間が共存するには、どのようなことを心がければよいのでしょうか。
AIの進化は不可逆的なもので、「仕事を奪われるから」と抵抗できるようなものではありません。であれば、人間の役割を考えるべきだと思います。人間にできてAIにはできないこと。私は「信頼関係を築くこと」と「責任を取ること」だと思うんです。人間同士で信頼を積み重ね、うまくいかなかったときはきちんと責任を取る。AIは「すみません」しか言いませんからね(笑)。
あとは、営業や建築など、オフラインの仕事はまだ人間がやることですよね。そういえばサンフランシスコには、AIに営業をやらせるサービスがあるんですよ。ビルボードに「Still Hiring Human?(まだ人間を採用してるの?)」とあって、成功報酬の金額など書いてあるんです。メールを出したりアポを取ったりをAIがやって、その後の実際の外回りは人間がやる。

オンラインとオフラインで、AIと人間を住み分けているんですね。
そのせいか、最近はAIが書いた営業メールが本当に多くなりました。AIが書いたメールって、文章がなめらかすぎて逆に「AIだ」とわかるんですよね。営業電話もAIからかかってきますよ。
この前かかってきた電話も声がAIっぽくて、雑に話していたら本当に人間でびっくりしました。単純にAIっぽい声の人だったみたいです(笑)。
区別がつかないほどAIが進化しているわけですね(笑)。ちなみに、エンジニア職はどうでしょうか。
サンフランシスコではエンジニアの求人が減っています。特に若い人たちの仕事が見つからない。MITを卒業した優秀なエンジニアなのに、仕事が見つからないからバイトを2つ掛け持ちしているとか。厳しい話をよく耳にします。
そういう人たちは、就職先を見つけるか、自分でスタートアップを立ち上げるかの二択しかない。だから、毎日必死にAI関連のイベントに出かけて情報交換したり、自分を売り込んだりしているわけです。イベントが連日満員なのは、そうしたエンジニアが多いからでもあるんですね。
それこそ、AIに履歴書を書かせたり、企業にメールを出させたりしていそうですね……。
それは実際に行われているんですよ。そして、企業側もAIでフィルタリングしたり審査したりしている。AIがメールを送ってAIが却下する、冗談みたいな状況が本当に起こっています。
面接も、オンライン会議ツールを使うのはもう当てにならないんです。相手からの質問をAIに認識させて、模範回答を自分の画面上に出力するなど、AIの力を借りることができてしまいますから。完全にオフラインの対面面接でないと、その人の本当のことがわからない。AIが発達しすぎたためにテクノロジーを禁じるという、奇妙な世界になってきていますよ。
AI時代に再び高まる「リアルの価値」
ということは、AIが発達しすぎたために、逆に“リアル”の価値が高まっている……と言うことでしょうか。
間違いないでしょうね。サンフランシスコのAI関連イベントも、オンラインイベントはほとんどなくなっています。
その代わり、ニューヨークやマイアミといった、遠方からの参加者が増えているんですよ。1週間くらい滞在して、テーマパークのように毎日いろんなイベントを巡るわけです。イベントがすべてオフラインなので、その場所にいること自体に価値が生まれてきているんですね。
「そこでしかできない体験」を求めていると。
そういう意味では、世界で一番人口が多い都市である東京こそ、こうしたイベントに向いているはずなんです。サンフランシスコなんて、80万人しかいないんですから。

確かに、ポテンシャルはすごくありそうです。
今後、日本の「The AI Collective」で開催するイベントでは、「AI×産業」をテーマにしたいと考えています。特にやってみたいのは、医療や農業、教育など、テクノロジーとは距離がある産業。そうした分野と超最先端の技術を組み合わせたところに、イノベーションが生まれると思っています。
単純に疑問なのですが、AIからイノベーションは生まれるものなのでしょうか? 「イノベーションを起こす」「新しい価値を創造する」というのは、人間だからできることのような気がするのですが……。
それは非常に面白いトピックなんですよ。
私たちbtraxでは、デザイン思考を使った新規事業立ち上げのサポートをずっとやってきました。デザイン思考はイノベーションを生み出す考え方のひとつなんですが、10年近くやってきて分かったのは「デザイン思考だけではイノベーションは生まれない」ということ。むしろ、これをやろうとしている人たちに、強烈なパッションがあるかどうかのほうが重要だったんですね。
デザイン思考をAIに置き換えても同じことが言えます。いくらAIがイノベーティブなアイデアを出してきたとしても、それを押し進める人間に強い情熱がなければ、面白いものはできません。教科書をただなぞるだけでは、イノベーションは生まれないんです。
なるほど……。AIが模範解答を出してしまうと、パッションも保ちにくいかもしれませんね。
それはあると思います。手品のタネを先に見せられたら、ワクワクしないじゃないですか。「もしかしたらすごいものができるぞ!」と興奮していたのに、AIに「すでに先行事例があります」と言われたら、やる気がなくなるのも当然です。イノベーションって、思い込みと勘違いから生まれるところがありますからね。
これはどうすれば解決するのでしょうか?
「AIをいったん使わない」というのがおすすめです。「The AI Collective」を最初に立ち上げた、チャッピーという人がサンフランシスコにいます。コミュニティには3000人ぐらい運営がいて、みんなSlackでやりとりしているんですけど、ここ最近チャッピーと連絡が取れなかったんです。
どうしたのかと思ったら、3カ月間あえて完全にオフラインにして、「AIとつながないことで何が見えるだろう」というチャレンジをしていた、と。その間、大自然と触れあっていたらしいですよ。最先端を走る人があえてそうしている、というのが非常に示唆的だなと思います。
ここでもリアルの価値が向上しているんですね。
そうですね。昔の文豪が旅館にこもる、みたいな感じでしょうか(笑)。
でも、こういうことが必要になる時代になるかもしれません。日常ではAIを使っていくけど、一時的に遮断する時期もちゃんと作る。その両方を考えていかないといけないのではないでしょうか。

2025年10月取材
取材・執筆=井上マサキ
撮影=栃久保誠
編集=鬼頭佳代/ノオト