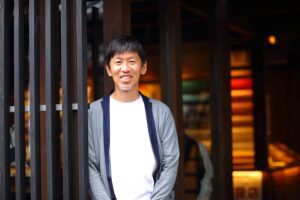経営に「顧客視点」だけでなく「従業員視点」を。カルチャーモデル起点の組織づくり

「いい会社」をつくりたい。
これは、組織開発に関わる誰もが、常に思うことでしょう。では「いい会社」とは、どんな会社を指すのでしょうか。
2020年にAlmoha LLCを立ち上げ、スタートアップ企業を中心に組織開発やカルチャー醸成の支援に取り組む唐澤俊輔さんは、「いい会社とは、従業員の期待値と現実の環境にギャップが少ない会社」といいます。そして「ギャップを生まないために、組織のカルチャーを言語化する必要がある」と。
これまで、日本マクドナルド、メルカリ、SHOWROOMで組織開発に取り組み、カルチャーづくりに奔走してきた唐澤さん。なぜ、組織開発においてカルチャーを重視するのでしょうか。
本企画は、前編と後編に分けてお送りします。前編のテーマは「カルチャーモデルがもたらす影響」について。カルチャーに基づく組織開発を続け、そこで見てきた景色とは――。
カルチャーがつくり出すのは「いい会社」
WORK MILL:2020年8月に出版した著書『カルチャーモデル 最高の組織文化のつくり方』において、事業における「ビジネスモデル」の対となる概念として「カルチャーモデル」の重要性を説かれていますよね。まずは、この「カルチャーモデル」について、お伺いしてもよろしいでしょうか。
唐澤俊輔さん(以下、唐澤):はい。カルチャーモデルとは、組織文化や企業風土、つまりカルチャーを言語化し、体系化したものです。

―唐澤俊輔(からさわ・しゅんすけ)
大学卒業後、2005年に日本マクドナルド株式会社に入社し、28歳にして史上最年少で部長に抜擢。経営再建中には社長室長やマーケティング部長として、社内の組織変革や、マーケティングによる売上獲得に貢献、全社のV字回復を果たす。2017年より株式会社メルカリに身を移し、執行役員VP of People & Culture 兼 社長室長。採用・育成・制度設計・労務といった人事全般からカルチャーの浸透といった、人事・組織の責任者を務め、組織の急成長やグローバル化を推進。2019年には、SHOWROOM株式会社でCOO(最高執行責任者)として、事業成長を牽引すると共に、コーポレート基盤を確立するなど、事業と組織の成長を推進。2020年より、Almoha LLCを共同創業し、人・組織を支援するサービス・ツールの開発を進めつつ、スタートアップ企業を中心に組織開発やカルチャー醸成の支援に取り組む。
唐澤:企業が培ってきたカルチャーの多くは、明文化・言語化されていません。カルチャーはあいまいで定義することが難しいため、可視化しにくいのです。目には見えないカルチャーがいつしか従業員の体に染みつき、暗黙知として共有されている会社も少なくないでしょう。
ただ、カルチャーが言語化されていないと、認識のズレを引き起こす可能性があります。「入社してみたら、思っていたイメージと違うことがわかった」といった、従業員が設定していた期待値とのギャップが発生しうるのです。
組織と従業員の期待値ギャップを減らすには、カルチャーを可視化し、社内外に浸透させなければなりません。私は、誰もがその人にとっての「いい会社」で働けるよう、組織は「どういうカルチャーを従業員に提供するか」を言語化して掲げることが重要だと考えています。
WORK MILL:「いい会社」であるために、カルチャーモデルを推進するべき、と。ただ、「定義しにくい」とおっしゃったように、カルチャーを言語化するのは簡単なことではないと思います。
唐澤:その通りです。一からつくるのが難しいために、グーグルやスターバックスといったカルチャーが称賛されている会社にならい、自社のカルチャーを無理につくろうとす組織もあります。また、「うちはグーグルじゃないからできない」と感じてしまう組織もあるでしょう。成功事例にとらわれた結果、ちぐはぐなカルチャーができたり、カルチャーの言語化に一歩踏み出せなかったりするのです。
成功事例を参考にすることは重要ですが、それよりも目をつけるべきは、それぞれの組織がもつよさです。私のルーツである日本マクドナルドもメルカリもSHOWROOMも、それぞれに違うよさがあり、違う強みがあります。例えばマクドナルドは、マニュアルを徹底してつくり、現場でオペレーションを改革し続けることが成功への道でした。
すべての組織が、グーグルのカルチャーを掲げても、成功するわけではありません。勝ち筋は、それぞれの会社のなかにあります。
ただ、共通して言えるのは、一貫性があるということ。ビジョン・ミッション・バリューを柱にカルチャーを醸成して、社内制度もカルチャーに紐づけて設計する。自社に反する考えは体内(組織内)に入れず、体内をめぐる血(カルチャー)を強く濃くしていく。こうして、一貫性のあるカルチャーモデルをつくることが重要です。
変化が多いこの時代に、カルチャーが重要なワケ

WORK MILL:カルチャーを掲げていない組織が多いなか、なぜ唐澤さんはカルチャーを重要視するのでしょうか?
唐澤:事業がうまくいっているときは、カルチャーが言語化されていなくても気になりません。しかし、業績が落ち込み、変革の必要性が出てくると、カルチャーという前を向いて歩くための指針がない組織はつらくなるからです。
カルチャーが明文化されていないと、行動が個人に依存し、意図しない組織文化になってしまうことがあります。例えば、2015年に起こった東芝の不正会計問題。東芝が利益を水増しし、違法な会計処理をしたことが明らかになりました。
なぜこのような問題が起こってしまったのか。第三者委員会は、特定の個人が問題を隠蔽しただけではなく、組織ぐるみの企業文化の問題だったといいます。「上司に意見しにくい雰囲気」「利益を少しでも減らせないプレッシャー」といった見えない空気感があり、それがカルチャーとして作用し、取り返しのつかない事態を招いてしまったのです。
暗黙知として存在するカルチャーは、必ずしもいいものばかりではありません。そこで、めざすべきカルチャーを可視化することで、個人の行動をカルチャーに律し、その結果として組織を改革していけるでしょう。
あとは、雇用の流動性が高まっていることも、カルチャーを重視するべきと提唱する理由の一つです。
WORK MILL:雇用の流動性ですか。

唐澤:「終身雇用制度」が終わりつつある今、組織のあり方が変わって、一社で働き続けることが難しくなり、雇用の流動性が高まっています。すると、これまで新卒で入社したプロパー社員のなかで共有されてきた暗黙知のカルチャーが中途社員に伝わらず、認識のズレにつながるのです。
働くなかで既存社員の背中を見ながら、数年かけてカルチャーに対する理解を深めていったこれまで。しかし変化が多いこの時代、即戦力として採用した中途社員が、組織になじむのを待つ余裕はありません。中途社員がすぐにパフォーマンスを出せるよう、体制を整えておく必要があります。
中途社員に向けて、オンボーディングやビジョン・ミッション・バリューの共有をし、「会社が何者で、どういった行動基準や価値基準が『ウチらしい』のか」をすぐに認識してもらい、即座に行動できるようにしなければなりません。
WORK MILL:唐澤さんは、カルチャーモデルで従業員に対する投資を重視していますが、同じ“人”でも、力を入れる対象が従業員ではなく顧客になっているケースが多くあるかと思います。
唐澤:そうですね。業績を上げるために営業やマーケティングに力を入れ、そこにKPIを設定することはよくあります。「灯台下暗し」ということわざがあるように、組織の外にいる顧客だけに目を向けて、組織内のことは後回し。ただ、数字をつくっているのは従業員なので、本来は先に組織に投資しなければなりません。
組織内にある課題をしっかり改善することで、従業員のパフォーマンスが上がり、顧客に提供できる価値が大きくなり、その結果として売り上げがついてくる。この流れに則って投資できるかが経営に重要なポイントで、意思決定の順番を間違えてはならないのです。
協奏的に文化が浸透していく、メルカリのカルチャーモデル
WORK MILL:カルチャーモデルをうまく実践している組織として、どのようなところが挙げられますか?
唐澤:事例の一つとして、メルカリが挙げられます。メルカリのバリューは「Go Bold(大胆にやろう)」「All for One(全ては成功のために)」「Be a Pro(プロフェッショナルであれ)」です。このバリューを実現するために、人事評価や採用基準、福利厚生に落とし込むほど、徹底して一貫性をもたせていました。
こうして組織内に深く浸透させた結果、意思決定が必ずそろうようになるのです。迷って安定の道を歩む意思決定をしそうになっても、絶対に誰かが「それって、Go Boldではないよね」とフィードバックをしています。
忖度をしないフィードバックは、言われたときに凹むかもしれません。しかしよく考えれば、そもそも「All for One」をめざして動いているわけだし、透明性がありオープンな「Trust & Openness」というカルチャーが共有されているので、原点に立ち返って気持ちよく意見に合意できるのです。
また、こうした一連のやり取りを新しく入った従業員が見ることによって、「Go Boldは、こういうことなのか」とメルカリらしさを肌で学べます。やがては、そうやって学んできた人たちが、「本当にそれってGo Bold?」と正す側の人間になっている。こうして、従業員同士が協力してカルチャーを奏でながら、協奏的にカルチャーが浸透していきます。
WORK MILL:メルカリのカルチャーがそこまで深く浸透した要因はなんですか?

唐澤:言いやすく、共有しやすい言葉にしたのが大きいと思います。使いたくなる言葉にして、日常的に組織内で飛び交えば、自然とカルチャーが自分たちのなかで当たり前になっていきますから。
あとは、一人ひとりの行動がカルチャーに基づいたものになるよう、人事制度や評価基準と紐づけて設計するのも重要です。
WORK MILL:例えば新規事業を立ち上げる際、今あるカルチャーを反映させた人事制度や評価基準だと、時代の変化についていけないことや、求められているスピードに追いつかないことはありませんか?
唐澤:あると思います。新規事業は、既存の概念とは違う概念で立ち上げることもあるので、もともとのカルチャーから分けて考えるのもアリでしょう。メルカリでも、スマホ決済サービス「メルペイ」を立ち上げるにあたり、カルチャーを共通させる部分と、あえて変える部分とを切り分けて検討しました。
新規事業ごとに出島のように新しいカルチャーをつくり、組織とつながりながらも少し飛び出たところで並列する。そして、新しくつくったカルチャーに基づいて、制度設計を行っていく。中途半端に合わせると、どこかで今のカルチャーと新規事業とのギャップが生じ、混乱を招くことになってしまいますから。
「今までとは領域が違う新規事業を立ち上げるから、その事業ではカルチャーを変える」と明言し、整合性を取りながら進めていくのがいいでしょう。
従業員の心に火をつけるなら、ボトムアップでの推進が必要
WORK MILL:カルチャーモデルを推進するにあたり、必要なことはなんでしょうか?
唐澤:必要なことはさまざまありますが、おすすめはボトムアップで推進することです。

唐澤:トップの頭のなかに道筋が描けていること、それを可視化すること、メンバーにメッセージとして伝えること自体はいいと思います。ただ、トップが決めて「あとは推進よろしく」だと、従業員とのあいだに温度差が発生し、なかなかカルチャーが定着しません。
従業員にカルチャーを自分ごと化してもらうには、従業員の頭や心のなかにあるものを可視化することが大切です。例えば、日本マクドナルドでは、カルチャーを言語化するプロジェクトをスタートさせるにあたり、リーダーとなる有志を公募で募りました。
純粋な公募のメンバーだけでなく、部長やマネージャークラスにも個別に声をかけて公募に手を挙げてもらうなどして、集まった30名ほどの有志を「火を付ける主役」としてリーダーに任命。そして、約600名の本社スタッフがほぼ全員参加するワークショップを実施し、会社全体を巻き込みながらプロジェクトを推進していきました。
ワークショップでは、参加者が肩書きや立場を気にせずに発言できるよう、「破かれた執行役員の名札」の写真を提示するなどの演出も。こうして、ボトムアップでカルチャーを推進できる環境を用意し、従業員が自分ごと化できるように進めていきました。
WORK MILL:従業員を起点にしたカルチャーづくりが重要だ、と。
唐澤:そうですね。私はカルチャーを、社内的・社外的なブランドイメージとして捉えています。
マーケティング視点でのブランドイメージとは、顧客の頭のなかにある商品やサービスのイメージのこと。企業側がどんなに「これはCOOLな商品だ」と訴えても、伝えたいイメージを喚起できなければ意味がありません。
これは、企業のカルチャーも一緒ではないでしょうか。カルチャーを対外的なイメージと一致させなければ、最初にお話しした通り、新しく入社した中途社員が設定していた期待値とのギャップが発生し、「こんなはずじゃなかった」と思われかねないのです。
期待値と現実のギャップが少ない「いい会社」をつくるためには、既存社員の暗黙知を可視化し、なおかつありたい姿も言語化して、自社のカルチャーとして浸透させていく必要があります。従業員とともに「私たちは何者か」「どんな強みがあるのか」と紐解いた先に見えてくるのがカルチャー、就活でいう自己分析のようなものだと思います。

前編はここまで。後編では、採用におけるカルチャーモデルの重要性や、コロナ禍で企業が取るべき経営スタンスについてうかがいます。
2021年1月19日更新
取材月:2020年12月