ベストセラーを生む、明石のスタートアップ出版社 ─ ライツ社大塚啓志郎さん・髙野翔さん
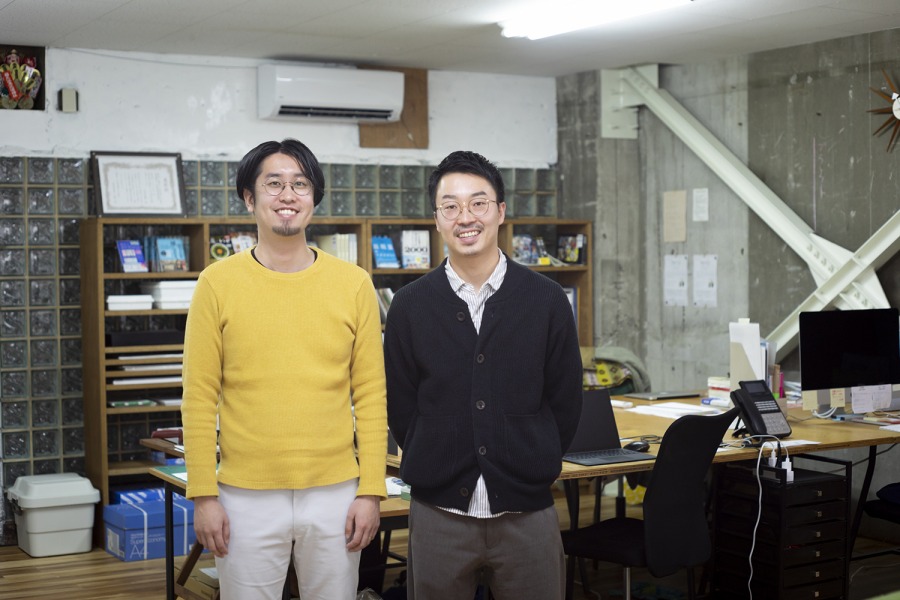
あなたは月に何冊本を読みますか? 1、2冊ほど書店で手に取る人もいれば、電子書籍でチェックする人。情報収集はネットのみで、本をまったく読まない人もいるでしょう。帝国データバンクの調査によると、出版社1,757社の2018年度総売上は約1兆6000億円。10年前と比較すると約15%の減少となり、「出版不況」という言葉は現実のものとなっています。
そんななか、2016年9月創業のライツ社は『リュウジ式悪魔のレシピ』(9.1万部)や『売上を、減らそう。』(5.6万部)といったベストセラーを次々と世に送り出し、業界内で注目を集める新興出版社です。縮小を続ける市場で、いかにその逆風を乗り越えているのでしょうか。前編では創業の経緯とヒットする企画の立て方について、代表の大塚啓志郎さんと髙野翔さんにうかがいます。
「やりたいことはやれているけど、このままの働き方は難しい」と考えた
WORK MILL:ライツ社はおふたりで代表を務めていらっしゃるんですね。どこで知り合われたのですか。
大塚:もともと京都の出版社で同僚として働いていました。詩人でもある社長が、自分の作品集を出すために立ち上げたほぼ20代ばかりの若い会社で、僕は2008年に会社で初めての編集者として新卒で入社したんです。

ー大塚啓志郎(おおつか・けいしろう)
ライツ社 代表取締役 編集長。1986年兵庫県生まれ。2008年京都の出版社に入社し、編集長を務めた後に30歳で独立。2016年9月、兵庫県明石市でライツ社を創業
大塚:出版社と言っても、雑貨とウェディング、そして出版の3部門が柱になっていて、作品集を出せばどんどん売れる状態でした。僕が入ってはじめて、作品集以外の本をつくるようになったんです。だから、自分より上の人もいないし、業界の慣習もなにも、わからなかった。他の出版社の方から業界の知識や仕組みを教えてもらいながら、ずっと下積みしていくような感じでした。髙野が入社したのは僕の3年後なんですが、髙野もまったく出版業界のことを知らなかったんです。
髙野:出版業界って、あまり会社同士で「ライバル」みたいな感じにはならないんですよ。本屋さんで他の出版社の営業さんと会っても「お! 最近どう?」って挨拶するし、飲み会も頻繁に開かれる。当時はあまりにわからないことが多すぎて、メモを取りながら飲み会に参加していましたね。

ー髙野翔(たかの・しょう)
ライツ社 代表取締役社長 営業責任者。1983年福井県生まれ。京都の出版社で営業マネジャーを務めたのち、2016年9月に兵庫県明石市でライツ社を創業
髙野:初めての名刺交換のときなんか、緊張しすぎて紀伊國屋書店の人に、その前にもらったジュンク堂書店の人の名刺を渡しちゃったんですよ。「あれ、これ違うよ(笑)」って言われました。笑ってもらえてよかったですけど。
大塚:そんな素人集団だったのですが、少しずつ軌道に乗り、2014年くらいから前年比を上回るようになって、最終的にはいちばん悪かった時期の4倍にあたる2億円くらいの売上になったんです。当時、100名くらいの会社でしたが、その頃には僕も編集長兼出版事業部長として、10名くらいの組織をマネジメントするようになりました。周りの方々に教えてもらったことを実践すると、しっかり結果が出て、それなりにやりがいを感じていたのですが、僕らが売上を伸ばしていたのとは裏腹に、タイミング悪く他の部門の売上がガクンと落ち込んでしまったんです。だから、僕らがいくら頑張っても、いっこうに給料が上がらないんです。髙野なんて、一度もボーナスをもらえなくて。
髙野:いや、1回はもらえましたよ。プロポーズと新婚旅行に全部使っちゃいましたけど……(笑)
大塚:それに事業部長になると、週の半分以上が会議だったんです。会社の理念について、採用について、事業計画について……。僕は本が作りたかったはずなのに、週に2日くらいしか編集に使えなくて。それでも会社のことは好きだし、必死に働いて売上を伸ばしていましたが、2016年の春くらいに「経営改善で、給与カットになる」と言われて。
髙野:僕も僕で、会社のことは好きだったんですよ。他の出版社の話を聞くとけっこう、編集と営業が明確に分かれていて、縦割りだったりするんですが、僕らは「これ、オモロいな」と思ったら横に大塚がいて、「あぁ、面白いね」って企画がスタートする。社長もそれを認めてくれていたし、全部自分たちで話しながら決められていたので、ずっとこうして働いていたいなって思っていたんです。

髙野:でも、なかなか給料が上がらなくて、妻も「どうするの?」と。「いや、いい会社だし、そのうち絶対上がるから、もうちょっと待ってて」と3年くらい言い続けて、「売上も上がってるから、今年こそは大丈夫」と思っていた矢先、大塚から呼び出されて「ごめん、給与カットになる」と。
大塚:ちょうど僕も髙野も、同い年の子どもが生まれたタイミングだったんです。でも、夜中に帰ってきて、寝るときと朝くらいしか子どもの顔を見られない。別に「ブラック企業」というわけではないんです。もともと芸大出身の社員が多くて、強制されているわけではないし、「好きなことやりたいから、とことんやる」という社風だった。
ただ、自分の人生の時間配分を考えると、「会社のための時間」が圧倒的に多くて、自分のやりたい編集の時間は少しだけ、家族との時間はもっと少なくなる。そこで、辞めるという選択肢をはじめて考えました。
大反対の嵐から「地元・明石」で出版社を創業
WORK MILL:そこで転職するのではなく、独立しようと考えたのはどうしてですか?
髙野:出版業界の現状や自分たちの実力を考えると、転職だろうな、と僕は思っていました。貯金も一切なかったし。

大塚:でも僕は、転職だと好きなものを作れないかもしれない、と。だから、会社に残るか独立かのどちらかでした。
髙野:僕はもう妻に約束したから、会社に残る道はなかった。ただ、これまでのように好きな仲間と好きな場所で好きなものを作って、好きなところに営業させてもらうのがいちばんいいな、と。だから、独立は理想的な選択肢ではありました。
大塚:会社に残って立て直すにしても、髙野なしでは考えられないし、じゃあ辞めるしかない。でも会社も苦しい状態だったし、辞めるまでは全力を尽くそうと思って、2016年の8月20日、つまり会社の期末まで僕は本を作り続けて、髙野もギリギリまで書店まわりをして、辞めるまで起業の準備はほとんどしませんでした。辞めてから会社を立ち上げたのはその2週間後、9月7日です。
髙野:辞めた後は、まずExcelで事業計画書を作ってみました。大塚が本を作って僕が営業、それに編集がもうひとり、事務がひとりいたとして、その4人体制だった場合に会社は成り立つのか、というものです。
大塚:僕の過去の実績を踏まえて、新刊を何冊出版して、何万部売れたら収支が合う、っていうのを全部髙野が計算してくれて。
髙野:本って特殊なのが、出版した本が売れてから会社に売上が入ってくるまで、7ヶ月かかるんです。7ヶ月間無収入で耐えるには、3000万円あればなんとかなりそうだな、と。でも全然、アテはないんですよ。まだ会社も作ってなかったし。
大塚:会社を辞めるのもみんなから大反対されて、社長だけが応援してくれたんですよね。
髙野:で、本は取次会社を通じて書店に卸されるので、「もし取次さんが本を取り扱ってくれそうなら会社を作ろうかな」と考えました。それで辞めた翌週に東京へ行って、取次さんと話してみると、「会社がないことには取引できないですね」と……まあ、当たり前なんですけどね。それで今度は日本政策金融公庫に行ってみると「会社がないとお金は貸せませんよ」と。あぁ、これは会社を作らないとどうにもならないなということで、やっと腹をくくったわけです。
でも、並行して諸先輩方に相談していたのですが、皆さんからは「辞めとけ」「無謀だ」と、口々に反対されましたね。出版業界の現状を考えると当然で、改めて起業は難しいものだと認識できました。ありがたかったです。
大塚:そもそも、新規の出版社が大手の取次会社と契約するなんて、絶対ムリだというのが常識だったんです。出版取次は上位2社でシェア8割くらいになるのですが、新規で契約できるのが年間1社あるかどうか。多くの新興出版社は、取次を通さずに書店と直接取引するか、営業代行会社にお願いするのがほとんど。それでは全国の書店になかなか広まらなくて、どんどん苦しくなってしまうのが現状です。でも結果的に、僕らは取次会社と契約することができたんです。

WORK MILL:すごい。それは何が決め手だったのですか?
大塚:その「3000万円」を借りられたからです。やっぱりお金は信用でもあるので、まずは交渉の土俵に立てた。普通3000万円なんて大金、すぐに借りられないですよね。もし僕らがあのとき東京に出て、「出版社やりたいんでお金を貸してください」って言っても、出版不況なのはわかりきっているし、絶対に借りられなかったと思うんです。
ただ、本当に僕らがラッキーだったのは、この明石でやろうと決めたことだったんです。はじめは大阪か神戸か、関西であればどこでもいいなと思っていたんですけど。明石は僕の地元で、実家は代々まちの工務店をやっていて、祖父がビルを持っていた。ちょっと古いですけど、家賃も安くしてくれるっていうし、ランニングコストも下がるからありがたい。ちょうど上の住居階も2つ空いていて、僕らが子育てもしながら仕事に集中できる環境が揃っていました。
それで、今度こそお金を借りようと地元の銀行に行ったら、「出版社にお金を貸したことなんてない」と言われたんです(笑)
髙野:出版社の8割以上が東京にありますし、ましてや神戸でもなく明石ですからね。めちゃくちゃ珍しい。僕なんて、最初に電話かけたら、ガチャって切られたんですよ。「何言ってるのかわからない」って(笑)
大塚:でも地方ならではというか、人のつながりがありきというか、実家の工務店を見てくれている税理士さん経由で聞いてみたら、会ってもらえたんです。
髙野:「大塚工務店の息子さんやね」と。それでその日のうちに1000万円。それを元手に日本政策金融公庫に行って、合計3000万円。利息もだいぶ優遇してくれて。

大塚:その通帳を見せてはじめて、取次の方も話を聞いてくれたんです。
WORK MILL:でもそんな大金を借りるのに、躊躇はありませんでしたか?
髙野:日本政策金融公庫に借りた分は保証人なしの融資で、銀行の分だけ最悪ひとり500万円返せばいい。周りの経営者に聞いたら、「アルバイトをめっちゃ頑張ったら、そのくらいなら返せる」って。ひとりで借金抱えるとなると恐ろしいでしょうけど、ふたりで半分なら、なんとかなるだろうと思えたんでしょうね。
大塚:僕も髙野も、本を作って営業する、だけではなくて、前職でずっと事業計画から考えさせてもらっていたので、予算感覚もあった。これだけ出版すれば、これくらいの売上は見込めるだろうという目算はあったんです。
みんなの「オモロイ」からベストセラーは生まれる
WORK MILL:とは言え、その時点で確実にヒットする企画を考えなければならないというのは、ものすごいプレッシャーですよね。
髙野:おっしゃる通り、1年目は見事に外れましたね。2000万円の赤字です(笑)
WORK MILL:ああ……。
大塚:ベストセラー作家さんに書いてもらったのに、1年目は「早く出さなきゃ」と、とにかく焦っていて、力不足で、結果的にどこかで見たことのあるような本になってしまいました。
髙野:他の出版社の営業部長にも怒られました。「ウチの本みたいな本を作っているね。君は独立してまでこんなことをやりたかったのか」って。もちろん、僕らはどの本も同じくらい愛してるんですけどね。
大塚:2年目のはじめに三宅香帆さんの『人生を狂わす名著50』という本を出しました。彼女は当時、京大院生で書店員としても働いていて、超マニアックな内容のブックガイドになって。それで、全国の書店員さんにゲラ(校正刷り)を読んでもらって、いただいた感想を数十人分すべて表紙の見返しに掲載したんです。誰か一人だけ「帯に一言」としていただくだけではもったいないな、と思って。
髙野:「この本、絶対オモロイなー!」と思って作りはじめたのですが、営業中に言われたんですよ。「すごいね、ブックガイドって一番売れないジャンルの一つだよ」って。
大塚:でも、もう作りだしちゃってるし(笑)
髙野:はい。それでも京大の書店に大きく展開してもらったり、感想を寄せてくれた書店員さんにお願いしたりして、なんとか1万部売ったんです。ブックガイドのジャンルでは、ある全国チェーンで2018年のランキング1位になりました。
大塚:そこから「ライツ社っておもしろい出版社なんだな」って、思ってもらえるようになった気がします。

WORK MILL:「ヒットする企画」を考えるコツはありますか?
大塚:前提として、「ニッチをメジャーに」というのが大切だと思っています。たとえば「広告コピー」って、ビジネス書の中でも「広告」とか「デザイン」っていうすごくニッチなジャンルだけど、それを「365日、自分の誕生日から読める」みたいな切り口で一般の方にもまるで「文芸書」として読んでもらえるような企画を考えたのが、『毎日読みたい365日の広告コピー』です。
髙野:そうすると、書店さんにも一言で案内しやすいんですよ。「これはこういうコンセプトで作った、日本ではじめての本です」って。
大塚:あとは「距離感」ですね。大きなテーブル1つに向かい合って、僕と髙野、あともうひとりの編集、事務の4人が座るという形でやってきました。いまは東京に営業がもう1人いるんですが、僕ら、企画会議って一度もしたことないんですよ。
WORK MILL:へー!
大塚:全部LINEでやりとりするんです。たとえば『売上を、減らそう。』のときは、髙野が佰食屋 さんのネット記事を見つけて、LINEに上げたんです。全員が「いいね」って反応だったら、企画がスタートします。みんなの意見が揃ったら、だいたいアタリなんですよ。ダメだったら、既読スルー。
髙野:けっこうサラッとしてますよね。
大塚:というのも、みんなそれぞれ好きなものが違うんです。髙野は小説や哲学、僕は旅。もうひとりの編集者はカルチャー系で、東京の営業はコミックやお酒。事務は芸大出身だから、アートが好き。男女比も3:2。バラバラの5人がそれでも「オモロイ」となったら、市場にもそれなりのニーズはあるだろうという判断軸なんです。

WORK MILL:でもそうやって感覚的に意思決定するのは、おふたりは長いつきあいだからいいかもしれませんが、他の社員の方は戸惑いませんか?
大塚:他の社員もあまり「ちゃんとしなきゃ」みたいな意識がなかったんですよね。もうひとりの編集は結構尖った編集プロダクション出身で、事務も自由なモノづくりが校風の大学を出てますし。
髙野:評価もノルマもないし、「何本企画を出せ」みたいな圧力もないので、本音で言いたいことを言えるんですよ。面白ければついみんな、ワーッと熱くなって話しますから、「あ、これならイケそうだな」って。それを、通常の出版社と比べたらすごく少ないですけど年間6冊〜7冊くらい。
大塚:そういうスピード感で企画が決まって、この距離感で作っているから、営業が書店員さんに話せることが普通の出版社の何倍もあるんですね。編集が著者さんとこんなふうに出会って、どんな考えでこの本を作ったか、ストーリーを全部話すことができるんです。高野が企画した本だってたくさんありますし。
髙野:書店員さんも忙しいですから、新刊の紹介をするにも15分くらいしか時間が取れないんですけど、ライツ社は新刊点数を絞り込んでいるので、僕はずっと1冊の本について話し続けられる。かたや通常の出版社なら、同じ時間で十数冊紹介しなければならない。当然、推される本とそうでない本が出てきます。
大塚:伝わり方が違うんだろうな、と思います。だから、普通なら5冊注文で1面展開をもらえればOKだね、というところを100冊注文もらって帰ってくる、みたいなことがけっこうあるんです。

髙野:書店員さんが応援してくれた結果なんですけど、そうやって売場の良い場所に置かれると、そもそもウチの本はオリジナリティがあるので、新鮮な展開になって、読者の目にとまって、重版率が上がっていく。
WORK MILL:重版率はどのくらいなんですか?
髙野:業界の平均はだいたい20%なのですが、ライツ社はありがたいことに重版率70%を超えています。
WORK MILL:そんなに高いんですか……!
大塚:みんな「出版不況」って言うけど、僕らからすると、最小の人数で必要な売上を作れるものすごくレバレッジが効く業界なんです。さっきは「大手取次はなかなか契約してくれない」と言って悪者扱いしたけど、実は取次のおかげで、僕らは売上を伸ばすことができる。書店って全国に1万軒くらいあるんですね。そこに取次が配本してくれて、請求も全部やってくれるからこそ、たった5人の会社でも5万部、10万部のベストセラーを生み出すことができるんです。
そして売上が上がったらボーナスとしてしっかりみんなで分けよう、という考え方。誰が担当とか関係なく、会社としてだいたい年間これくらいの売上を立てられたら、みんな幸せに暮らせるよね、という数字を目指す。だから、年間に6、7冊くらいしか本を出さないんです。

前編はここまで。後編では、東京からあえて距離を置くことで見えてくる働き方や、大切にしている価値観についてうかがいます。
2020年5月19日更新
取材月:2020年2月






