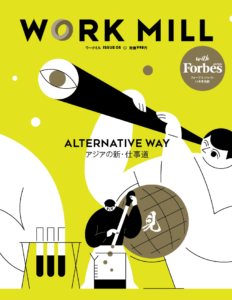「売れる良書」を生むチームプレイの仕組み ー 英治出版・原田英治さん

この記事は、ビジネス誌「WORK MILL with ForbesJAPAN ISSUE05 ALTERNATIVE WAY アジアの新・仕事道」(2019/10)からの転載です。
世界はアジアを見ている。それなのに私たちは、その価値をあまり知らない。少し拍子抜けしたものの大事な気づきだった。
やみくもに規模を拡大するのではなく、働く人や地域と共存する。目先の数字より事業の意義を優先する。
そんな「資本主義のその次」を見据えたオルタナティブな経営哲学を探しに、韓国、台湾、日本の企業を訪ねた。
仲間とつくる現実は自分の理想を超えていく― 英治出版は出版事業を「応援」ととらえ、さまざまな人とかかわりあい、その夢を後押しする。読み継がれるような本を生み出すために。
年々縮小する出版業界。利益率の低下や資金繰りの悪化で出版社や取次、書店の経営破綻が相次ぐなど、業界全体としてビジネスモデルの構造的課題を抱えている。その渦中にありながら、堅調に売上高を伸ばし、数々のロングセラーやベストセラーを出版しているのが、英治出版だ。2018年初頭に発売した『ティール組織』は、これからの時代をつくる新たな組織論として、多くのビジネスパーソンのバイブルとなった。
英治出版の船出は、「想定外」からはじまった。アンダーセン・コンサルティング(現・アクセンチュア)を経て、家業の印刷会社に取締役として入社した原田英治は、専門書を扱っていた出版部門を転換し、「一般書を出せば、社員たちがもっと楽しく働けるのではないか」と、いくつかの翻訳書を企画し、新たな出版事業をはじめようとしていた。ところが、ほどなくして経営方針をめぐり、たもとを分かつこととなる。「自分が辞めることで出版できなくなるのは、著者や翻訳者に申し訳ないから」と、さいたま市の自宅を拠点に設立したのが、前身となる会社だった。
会議は相撲の立ち合いみたい
編集経験も出版業界にいたこともない原田が、自らの出版社を立ち上げるにあたって掲げたのは、「絶版にしない」というポリシーだった。根底にあるのは、業界の常識に対する違和感だ。「文化産業だからという名目で、再販価格によって守られているにもかかわらず、絶版してその文化を閉ざしてしまっていいものなのか。第一、著者にとって嬉しいはずがない。もし、絶版しないことを約束すれば、著者さんも無名な僕らの会社で書いてもらえるのでは……そんな思惑もありました」
本をつくるプロセスも特徴的だ。そもそも編集者や営業といった肩書はなく、本に携わる社員はすべて「プロデューサー」。異業種からの転職者がほとんどで、全員の共感を得なければ、出版することはできない。毎週の企画会議で、起案者は企画の社会的意義や著者の思いなど、各人から寄せられる質問やフィードバックに対して答え、少しずつ企画を練り上げていく。
「出版することは目的ではなく、著者をはじめ誰かの夢を応援する手段。だから、著者に100%の賛同はなくとも、みんな何かしら共感できるところがあり、最終的に全員が拍手をすれば企画が決まる。それは相撲の立ち合いみたいなもので、『そろそろ、いいですかね』という間合いがあり、自然と拍手が起こる。そこで問われているのは、プロデューサーの覚悟も含めて、本をつくるための準備が整ったかどうか、各人からの十分なフィードバックが行われたかどうか、ということなのです」
原田は、自社の働き方をある意味「日本らしい」と答える。英治出版では社員が「ひとり出版社」ができるようになるほど、営業や編集などあらゆる業務を習得することを目指す。「『全部できたほうがいい』というのは、日本的ですよね。小さくとも乗り越えていけるスキルやノウハウを身につけたほうが、著者からの信頼も社員自身の安心度も高くなる。どんなに雇用の流動性が高まっても、企業としては社員に長く働いてもらえることを前提に仕組みをつくるべきだと思うのです」。「誰かの夢を応援すると、自分の夢が前進する」からこそ、社員とも長い関係を構築する。「卒業生」の社員やメンバーも含めて、毎月送るバースデーカードがその証しだ。
18 年、原田は新たなチャレンジに取り組む。3月から1年半、島根県隠岐郡海士町への「親子島留学」を行った。これからの働き方や事業を模索するにあたり、自らこれまでと異なる環境に身を置くことで、そのヒントを求めたのだ。縮小を続ける出版業界において、そのビジネスモデルが瓦解する可能性もある中、いかに会社として新たな価値提供を行い、社会へ還元していくのか──。そこで見えてきたのは、「仲間と創る現実は、自分の理想を超えていく」という経営理念だった。
「東日本大震災が起こった11 年3月11日、当時の社員がTwitterで呼びかけて、オフィスを開放しようと言いだしたんです。結果、十数人の人が夜を明かし、『どうせ帰れないから』とみんなで酒を買い込んで、心細い気持ちを紛らわせた。彼の一言で、自分では思ってもみなかったことが実現したんです。彼は残念なことにその後突然亡くなってしまったのですが、いま思えば彼が僕に、会社という組織をつくる意味を教えてくれた気がします。海士町にも元世界銀行副総裁の西水美恵子さんなどが足を運んでくれて、創業時では考えられないような著者の方と仕事ができている。その現実は、軽く僕の理想を超えているのです」

─原田英治(はらだ・えいじ)
1966年、埼玉県生まれ。慶應義塾大学卒業後、アンダーセン・コンサルティング(現・アクセンチュア)などを経て、99年に英治出版を創業。第一カッター興業社外取締役、一般社団法人アショカ・ジャパンのアドバイザーなども務める。
同時期にオープンしたEIJI PRESS Baseは、まさにそれを体現した場所だ。会員は会費を支払うと、スペースを自由に使い、英治出版のアンバサダーとして本を何冊でも友人知人へ献本する権利を得ることができる。約30人の会員もまた大切な「仲間」だ。そうやって、社員9 人の小さな組織ながら、著者、翻訳者、Base 会員、卒業生……と人のつながりを広げ、関係人口を増やしていく。
「企業力が『社員一人ひとりが持っている夢の運動エネルギー× 人数』で割り出されるとすれば、仮に大企業の社員のエネルギーが0.1人分だったとしても、1万人いれば莫大な力になる。覆すのは難しいと思っていたけど、いまは僕らだけじゃなく、さまざまな人たちがかかわってくれています。これからもっと面白くなっていくと思いますね」
原田は理想の企業のあり方を、生物の進化にたとえる。
「企業は恐竜から鳥へ進化したほうがいいんです。大きな身体を抱える限り、10 万部のマーケットを狙わなければならないけど、鳥なら1 万部で腹いっぱいになれる(笑)。僕らは絶版にしないから、未来にも読者がいるんです」
2020年3月25日更新
2019年8月取材
テキスト:大矢幸世
写真:金 東奎(ナカサアンドパートナーズ)
※『WORK MILL with ForbesJAPAN ISSUE05 ALTERNATIVE WAY アジアの新・仕事道』より転載