人間は面倒くさいけど愛らしい。現代のリーダーが持つべき「遊び心」と「パラドックス思考」のすすめ(立教大学・舘野泰一准教授)

残業は減らしながら、仕事の成果を上げないといけない。こうした「二律背反」ともいえる状況は、私たちを悩ませ、時には身動きが取れない状態に陥らせることもあります。
立教大学経営学部で教鞭をとる舘野泰一先生は、このような矛盾する要素を内包する課題を「パラドキシカルな課題」と捉え、遊び心を武器にしたリーダーシップでこれらの課題に向き合う方法を研究されています。
今回は、舘野先生が提唱する、今の職場に適したリーダーシップのあり方とその背景にある「パラドックス思考」について伺いました。矛盾だらけの現代社会、職場を軽やかに生き抜くためのヒントを探ります。

舘野泰一(たての・よしかず)
立教大学経営学部准教授。1983年生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了、博士(学際情報学)。企業・教育機関における若年層のリーダーシップ教育を専門に研究・実践。主な著書に『パラドックス思考:矛盾に満ちた世界で最適な問題解決をはかる』(ダイヤモンド社)など。
パラドックス思考とは? 現代の職場に潜む「矛盾」
先生が研究されている「パラドキシカル(矛盾した)な課題」は、職場においては具体的にどのようなものを指すのでしょうか?


舘野
現代の職場には、成果と余白、ルールと自由など、一見すると相反する多くの価値が同時に存在しています。
もっとも分かりやすい例は「プレイングマネージャー」ですね。彼らはプレイヤーとして個人の目標を達成しつつ、同時にチームの成果も引き出さなければなりません。
確かに、難しい立場ですね。


舘野
個人として成果を出しすぎると「お前が動くんじゃなくてチームを動かせ」と怒られますし、チームに徹しようとすると自分自身の個人目標が達成できない。
チームで成果を出すべきか、個人として活躍すべきか、の板挟み状態なのです。


舘野
また、働き方の多様化と組織の一体感の両立もよく挙げられます。
リモートワークは個々の働きやすさを尊重する一方で、「組織の一体感が減った」というマネジメントにおける悩みも生まれています。
確かに……。いまや、リモートワークをとりやめる会社も出てきて、ニュースになっていますね。


舘野
他にも、既存顧客を大切にしながら、同時に新規事業も開発しなければならないケース。既存事業の売上があってこそ新しい挑戦ができるわけですが、両方を同時に進めなければなりませんから。
変化と安定の同時追求も矛盾があります。安定しすぎると「思考停止だ」と言われてしまうし、毎回変わってばかりだと組織は壊れてしまう。
パラドックス思考がもたらす「感情の板挟み」
どの問題も「職場あるある」……。
とはいえ、どちらかを選ぶのって難しいですね。


舘野
そうなんです。組織内で「自由な働き方を推進しよう」という動きがある一方で、「組織の一体感が減った」と嘆く声も聞かれます。
これは、私たちの心の中に「自由にしたい」という気持ちと同時に、「みんなと一緒でいたい」「規則があった方が安心できる」という相反する感情があるためです。
自分の気持ちなのに、どうしたいのか分からなくなってしまうのですね。


舘野
はい、そのとおりです。私たちは、こういうパラドキシカルな課題に向き合う時の心理状態を「感情パラドックス」と呼んでいます。
矛盾するニーズに晒され続けていると、自分が何を感じているかすら分からなくなってしまう。そうした状況に長くおかれて、燃え尽きてしまうのが一番危険です。世の中のマネージャーの多くは、この感情のすり減りを経験していると思います。

そうならないためには、どうすればいいのでしょうか……?


舘野
まず大切なのは、自分が相反する欲求を両方持っていることを認めることです。
たとえば、「新しいことに挑戦して欲しいけれど、失敗はして欲しくない」といった感情は、実際はそう感じることがあっても、なかなか口にできませんし、そういった感情を持ってはいけないと「なかったこと」にしてしまいがちです。
そうではなく、そういう感情があるということをまず自分の中で認めることが大切になります。
なるほど、両方がとりたい自分に向き合うんですね。


舘野
そうです。たとえば、大抵の人は、完全に自由な状態を望んではいません。ある程度のルールがあってほしいと思っている。
そうした両方の気持ちが自分の中に存在することを認めるだけで、安心することができます。だからこそ、「AかBか」ではなく、「AとBを両方満たすにはどうしたらいいか」と考えるモードに切り替えることができるのです。
なぜ、「AとBを両方満たす」ように考えることが重要なのでしょうか?


舘野
結局、どちらかを選んでも完璧な答えはないからです。
たとえば、全員が完全に出社するスタイルにすれば組織の一体感は増すかもしれませんが、多様な働き方を認めないことで人が集まらなくなってしまう可能性もあります。一方で、自由に働いてくださいと全員に言うと、それはそれでまとまりがなくなる。
確かに、そうですよね。


舘野
つまり、AとBのどちらも必要で、ある種のバランスの中で両立せざるを得ないのです。
「Aか、Bか」とハッキリしないのは気持ちが悪い感覚があると思いますが、不確実性の高い状況に対する耐性がリーダーシップにおいて重要だという指摘があります。
なるほど。
ちなみに、この「パラドックス」という概念は、最近になって研究されるようになったそうですね。なぜなのでしょうか?


舘野
もちろん、昔からリーダーたちはこうした矛盾に悩んできたと思います。
しかし現代は、組織の複雑さが増している。改めて、その向き合い方が問われるようになったからこそ、研究されるようになったのです。
リーダーのあり方が変わってきたのですね。


舘野
そうですね。役職が上がれば上がるほど、自分の「正義」だけでなく、異なる部署や立場の「正義」を抱える人たちと向き合い、意思決定をしていかなければなりません。
たとえば、営業には営業の正義があり、経理には経理の正義があり、全体を統括する立場になると、それぞれの正義がぶつかり合います。
確かに、どう対処すればいいのか迷いますね……。


舘野
私は大学でゼミ生といっしょに、この矛盾との向き合い方をどうやって学ぶことができるのか、どうすればリーダーシップを発揮できる人を育成できるかを探求しています。

ツライ仕事も大丈夫?「遊び心」で矛盾を乗り越える理由
そうした“身動きが取れない”感情の状態を乗り越える鍵が「遊び心」になると舘野先生はおっしゃいますが、どうしてそう考えられたのですか?


舘野
遊びはそもそも矛盾をはらむ存在だからです。
遊びやゲームというのは、乗り越える必要のないハードルを自分で設定し、それを乗り越えることだと定義できると思いませんか?
確かに……!


舘野
たとえば、ただゴミをゴミ箱に捨てるだけならタスクですが、自分の椅子から一歩も動かずにゴミを投げ入れるというルールを自分で決めていたら、それは遊びになります。


舘野
他者から与えられた課題でも、そこに自分なりの工夫や制約を加えることで遊びに変えることができます。
このように、遊びはルールや制約を自ら設ける創造的なプロセスであり、この発想が矛盾解決に役立つのです。
制約があるのに自由。まさに矛盾ですね。


舘野
はい。あと、矛盾にさらされ続けて、「自分は何を楽しいと思っているのか」が分からなくなってしまうときこそ、遊びモードを意識してほしいですね。
遊びは外部の評価ではなく、内発的な動機にもとづく「自己目的的な活動」といえます。遊びモードに入ることで、他者のニーズに応えることから一旦離れ、「そもそも自分が何をしたいんだっけ?」という自分起点を思い出すきっかけになります。
なるほど。
与えられた制約を逆手に取る発想や、自分自身の内面と向き合うことが、遊び心から生まれるのですね。


舘野
そうですね。たとえば、「100万円稼いでください」という目標を、あえて遊びのように捉えて「営業電話をいつもの半分しかかけずにどう達成するか」を考えてみる。
こうすることで、他者評価ではなく自己目的でタスクに取り組みやすくなります。
「面倒くさいけど愛らしい」矛盾を受け入れるマインドセット
実際に、遊び心を仕事の場に活かしたいとき、何から始めるべきでしょうか?


舘野
まず、自分が楽しむ姿勢を見せることが効果的です。人は、「こうすべきだ」と強制されるのではなく、誰かが楽しそうにしている姿を見ると、つい興味を持ってしまうもの。強制すると遊びではなくなってしまうので、焦りは禁物です。
自分が楽しんでいれば、いずれ周りも興味を持つので、自然な参加を促すのがポイントです。面白いゲームをプレイしているときに、コントローラーを「ちょっとやってみなよ」と友達に渡す感覚だとわかりやすいでしょうか。
イメージしやすいです。


舘野
ただ、強制しないことは大切です。
無理に「みんなでやろうよ」と誘うのではなく、自分が楽しんでいる姿を見せ、相手に「参加したい!」と思わせることが大事です。
確かに面白そうでも、強制されたらいやですね。


舘野
あと、無理して仕事のすべてを「遊び」にしようとしないことも重要です。つまらなくてもやらなければいけない仕事はありますし、逆に仕事のすべてを「楽しい」と思わなければいけない、というのもまた一つの強制になってしまいます。
はじまりは「なんとなく」でいいのです。感覚的には「今日は歯磨きを、利き手の逆でやってみようかな」くらいの感覚で、「ふと、いつもと違う挑戦をしてみること」です。すると、いつもと同じ行動が違う側面から見えてくるようになります。
手軽に始めるというか。


舘野
仕事も同じで、誰かに強制されたり、明確な理由がなかったりしてもいいので、「ふと、いつもと違う制約を自分にかけてみること」が意外と大きな変化を生むことにつながると思います。
そういうポイント、探してみたいと思います!


舘野
私は仕事と遊び、両方の要素が混在している状態が、一番健全だと思うのです。
これは西洋的な考え方と違って、ぐちゃぐちゃした中間を許容する東洋的な考え方に基づくものだと考えています。パラドックス思考を身につけることは、日本人の強みかもしれませんね。
人間は「めんどくさいけど愛らしい」のですから。
「めんどくさいけど愛らしい」?


舘野
これは私のゼミで使う言葉なんです。
人間は面倒で複雑で、矛盾を抱えている生き物。だから、完璧な一貫性を求めず、揺らぎを許容することが重要だと考えます。
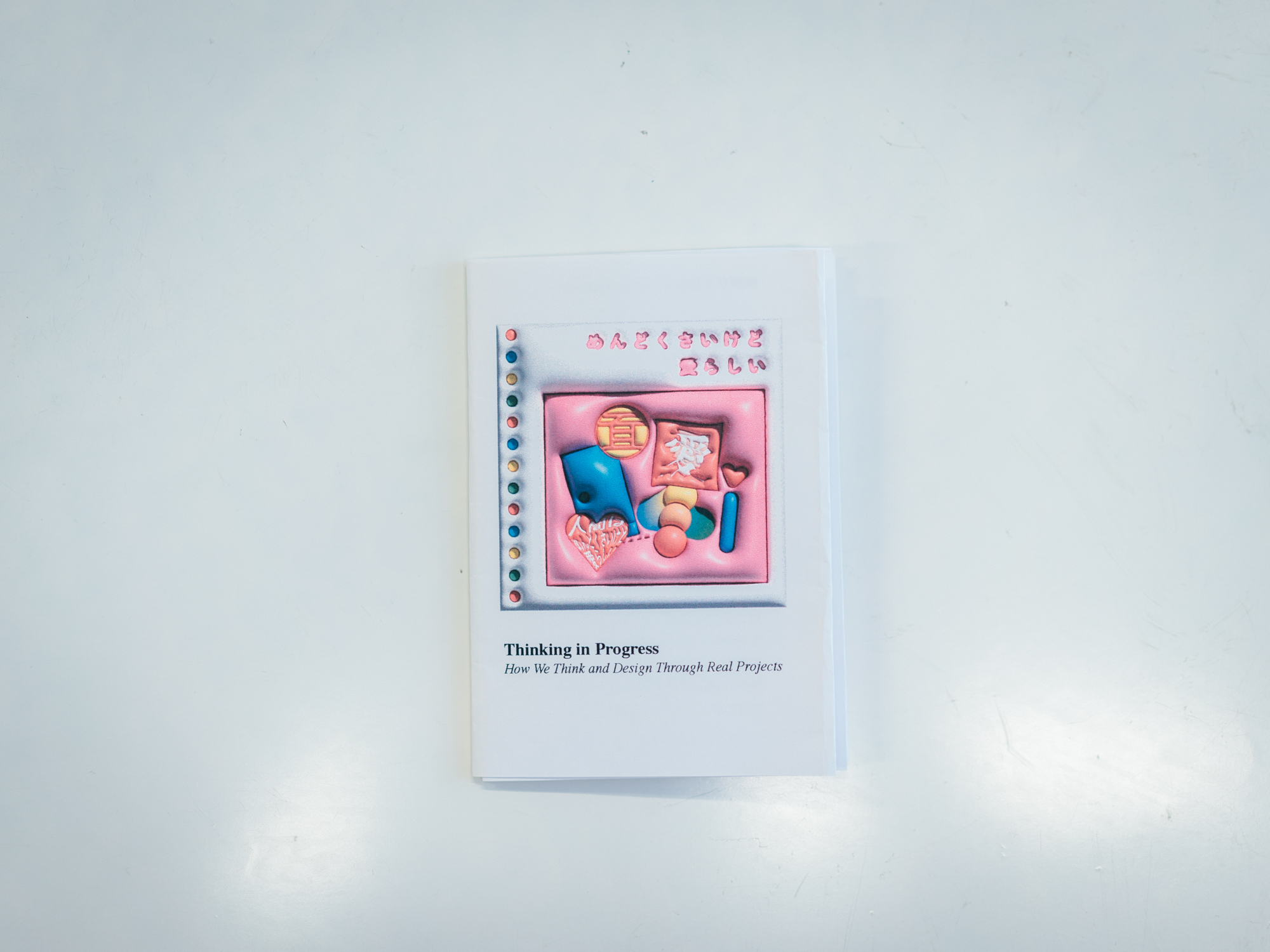
すべてにおいて一貫している人などいないですよね。


舘野
そうです。たとえば、ドラマや映画に感動するのは、登場人物が葛藤を抱えているからですよね。
片思いをしている相手がいても「好きだから好きと言えばいい」という単純な話ではないからこそ、そこに物語が生まれるわけです。
矛盾にこそ、人間味がある。


舘野
自分自身に対しても、完全に自由になりたいと言いつつ、実は束縛も求めているという矛盾を受け入れるという話がありました。
同様に他者に対しても、「昨日と言っていることが違う!」と腹を立てるのではなく、「めんどくさいけど愛らしい」と心の中で3回唱えてみましょう。人間とはそういうものなんですから。

2025年8月取材
取材・執筆=ミノシマタカコ
撮影=篠原豪太
編集=鬼頭佳代/ノオト






