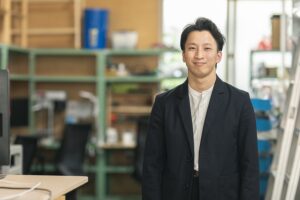公共トイレを人が集まる場所に。水道工事会社が街にパブリックスペースを作った理由(石和設備工業・小澤大悟さん)

埼玉県所沢駅から徒歩10分ほど。静かな住宅街を歩いていると、大きな屋根が特徴的なパブリックスペースと出会います。その名は「インフラスタンド」。この場所を作り、管理しているのは水道工事会社の有限会社石和設備工業です。
「トイレのイメージを変える場所を作りたい」。そんな思いから、代表の小澤大悟さんが生み出した「インフラスタンド」は、普段は安心して使えるトイレや夜の街を照らす場所として、特別な日にはマルシェやイベントスペースとして、人々の交流を生む拠点になっています。
「会社で開かれた場所を持つことで、新たな出会いや働き方にも繋がった」と小澤さんは振り返ります。
設備としてのインフラと、コミュニティのためのインフラ。この2つに向き合いながら、新たな挑戦を続ける小澤さんの思いを伺いました。
ハレとケに寄り添う「インフラスタンド」

トイレでパブリックスペースというのがイメージできていなかったのですが、素敵な建物ですね!


小澤
ありがとうございます。インフラスタンドのメイン機能は公共トイレで、大便器・小便器・おむつ台・パウダースペースなどの衛生設備が整っており、おむつや女性用品も用意しています。


小澤
清掃は1日3回行い、誰もが気持ちよく使える環境を保っています。
さらに手洗い場やベンチ、シェアサイクルステーション、自動販売機やフリーWi-Fiも設置して、誰でも自由に利用できるようにしています。
夜にはライトアップされ、街を安全に照らす街灯としての役割も果たしているんです。

オープンで使いやすく、親しみのある場所になっているんですね。


小澤
また、この場所では地域や行政と連携したイベントも開催されています。
「路地裏の秘密基地のようなマーケット」をコンセプトにしたマルシェ「KAWAYA市」はこれまでに4回開催しました。所沢の個性的なお店やクリエイターが集まり、多くの人でにぎわうイベントへと成長しています。
請負だけの水道会社を脱却し、新たな価値を提案する
改めて、石和設備工業の仕事について教えていただけますか?


小澤
石和設備工業は1969年に所沢市で開業した水道会社です。一般住宅の水道メンテナンスや大型施設の工事、道路下の配管や補修といった公共工事など、幅広い業務を手掛けています。
所沢市外から仕事を依頼されることもありますが、基本的には地元の案件を大切にしていて。責任を持って最後までやり遂げることで、信頼関係を築いてきました。

地域に愛される水道会社なのですね。小澤さんは2代目と伺いました。


小澤
はい。2011年に先代から社長を引き継いだのですが、当時は資金繰りが厳しく、まずは経営の立て直しに集中しました。
なんとか黒字化したタイミングで、ふと「会社に自分より若い社員がいない」ことに気がついたんです。
水道工事業界は60代以上でも現役の方が多く、40代でも若手扱いをされるんですよ。
高齢化しているのですね。


小澤
このままでは、社会インフラを支える大切な技術が次世代に継承されていかない。そこに危機感を覚え、若い世代に興味を持ってもらえるような取り組みを始めました。
どのような取り組みでしょう?


小澤
一言で言えば「トイレを使ったプロモーション事業」。目に見える、わかりやすい成果を出すことを第一に考えました。
配管工事は、どれだけ丁寧に仕上げても、最終的には壁や地面に隠れてしまいますよね。お客様からしたら「見た目よりも価格、問題なく使えればいい」と思われてしまうので、結果的に価格競争に巻き込まれる事も課題としてありました。
インフラ事業で生じがちな課題ですね……。


小澤
そこで、水道工事にとどまらず、トイレ全体の設営にも注力することにしました。私たちの仕事で、目に見える数少ない成果物がトイレなんです。トイレを使って主体的にビジネスをやることで、仕事の魅力を伝えられるのではと思ったのです。
たとえば、特殊な色や模様を内装に取り入れたり、ホテルのような高級感を持たせたり。デッドスペースでも有効に使えるよう、収納と一体化したトイレ空間の設計なども提案しました。
依頼された水道工事をするだけでなく、デザインや空間設計まで提案するようになったのですね。


小澤
普通、水道工事店が設計まで関わることはないんです。なので、最初は異端児扱いされましたし、そもそも私に知見もありませんでした。
それでも試行錯誤しながら取り組んだ結果、地域のお客さまは少しずつ増えていきました。
さらに、キャラクターや企業の広告を載せたり、ライブやイベント会場の仮設トイレに演出を加えたりすることで、トイレの価値をもっと広げられるのではと考えました。

確かに……!


小澤
でも、提案をすると現場の担当者からは良い反応をいただくことはあっても、なかなか決裁権を持つ上層部を通らず、本採用には至りませんでした。
私たちはこの理由は、トイレに対するネガティブなイメージが根強いからだと考えたんです。トイレには最低限の機能がついていたらいい、とも思われていたのだろう、と。
それならば、そのイメージを変えるために「理想トイレのショールーム」を作ろうと決めたんです。

想いが伝わる、設計士との運命的な出会い
インフラスタンドの始まりは、トイレや水道工事業に対するイメージを向上させるショールームだったんですね。
どのようにして今の形になったのでしょうか?


小澤
ただのショールームではなく、人が集まれる場所にしたいという思いはありました。
トイレを、人の集まる場所に?


小澤
はい。というのも、以前この場所で開催したマルシェイベントで手応えを感じたからです。
地元で仕事をしているとはいえ、住宅街の中にあるこの場所が、何の会社なのかあまり知られていません。


小澤
普段、街の人と接点が少ない社員たちが、地域の人たちと直接関わる機会にもなればと思い、クラフトマーケットの経験が豊富な妻に協力してもらいながら開催したんです。
「ここに水道屋がある」と知ってもらうだけでも、大きな価値がありましたね。
マルシェが石和設備工業のことを知るきっかけになったのですね。
インフラスタンドは広場もあるし、建物の構造も特徴的ですよね。


小澤
設計を手掛けたのは、シン設計室の高橋真理奈さんです。
同じ所沢出身の方で、大手事務所から独立し、所沢で活動を始めるためにクラウドファンディングを行っていて、私も支援をしたんです。
そのリターンで相談に乗ってもらえる機会があったので、建築確認申請の手続きをお願いしよう、という程度の軽い気持ちで話をしに行ったのですが、驚くほど熱量を持って話を聞いてくれて。
小澤さんのやりたいことを、同じ熱量で汲んでくださったのですね。


小澤
当時始まったばかりの渋谷のプロジェクト「THE TOKYO TOILET」(※)など、他の公共トイレの事例をたくさん持ってきてくれて、視察ツアーにも一緒に行きました。
話し合いを重ねる中で、「自分ごとのように一生懸命に取り組んでくれる人だ」と確信し、設計をお願いすることにしました。
※THE TOKYO TOILET:日本財団が実施した、東京都渋谷区内に公共トイレを設置するプロジェクト。さまざまなクリエイターによる個性的なトイレが次々に設置された。
所沢で素晴らしい出会いがあったのですね。
完成したインフラスタンドは、心地よい雰囲気と清潔感が両立した素晴らしい場所になりましたね。


小澤
天井は低すぎると屋内感が出てしまうし、高すぎると開放感が薄れてしまうそうで、絶妙な高さに設計されています。
また、半透明の波板は夜になると光を通し、防犯灯のなかった場所を照らす行灯の役割も果たしています。

徹底的に作り込まれている……!


小澤
いろいろと工夫していただきましたが、一番嬉しかったのはコンセプトでした。
手洗い場やハイカウンター、ベンチも設計に組み込まれていますが、これらはすべて建物の「基礎」なんです。通常、建物の基礎は目に見えない部分に隠されてしまいますが、それをあえて見えるように設計されているんです。


小澤
「人の目に触れづらいインフラの仕事が日の目を見るように」という高橋さんの思いが嬉しくて……。
今思い出しても、胸がいっぱいになります。
トイレがあると仲良くなれる? イベントで醸成されるコミュニティ
完成したインフラスタンドは、どのように利用されているのでしょうか?


小澤
登下校中の学生さんが立ち寄ったり、ベンチやブランコで話し込んだりする姿をよく見かけます。


小澤
いわゆる公園のような賑わいが日常的にあるわけではないですが、イベントを開催すると、多くの人が足を運んでくれますね。
日常の風景から、イベントまで!


小澤
先ほども話したKAWAYA市は、インフラスタンドとして初めて実施したイベントでした。
地域でつながりのある人たちに相談し、アーティストのライブ演奏があったり、飲食の販売を出店してもらったり。不思議なイベントではありますが、「なんだか面白そう」と楽しんで関わってくれる人が多かったですね。
いいですね。



小澤
2025年3月からは、よりコンスタントな開催を目指した教室型のイベント「クラス インフラスタンド」を始めます。
防災や裁縫など学びをコンセプトにして、地域に根ざした場になればいいなと思っています。
地域の人たちが集まるイベントを続けているのですね。


小澤
イベントをやってみて実感したのは、「トイレがあることで、人が長く滞在できる」という副次的な効果でした。
KAWAYA市も、最初はトイレの隣にベンチを置くことすらためらっていました。トイレの周りでマルシェを開催するなんて、果たしてどう思われるのだろう? と、それくらい手探りだったんですね。
ところが、いざ開催してみたら、若い世代の方たちがトイレの横で食事をしたり、会話を楽しんだりしている様子があって。
通常、マルシェやイベントの滞在時間は1時間以内。目当てのお店で買い物してふらっと回って帰ります。ところがKAWAYA市の滞在時間は2~3時間の方が多くいました。
すごい!


小澤
清潔なトイレがあれば買い物もご飯も安心して楽しめるし、滞在時間が長くなることで出店者さんやお客さんの間でコミュニケーションが生まれる。買い物して終わりじゃない。人と人が知り合い新しい取り組みが生まれるきっかになる。本来マルシェやマーケットなどの「まちづくり」での目的はここだと思っています。
インフラスタンドでできた関係が、また別の場所でのイベントや仕事にもつながっていったんです。
トイレとイベントの相性が良いなんて、思わぬ相乗効果でしたね!
参加者同士のつながりが生まれると、地域との縁もより深まっていきそうです。


小澤
2022年に開催した第1回のKAWAYA市は、偶然が重なって実現した所沢市との連携イベントでした。

というと?


小澤
ちょうどその頃、所沢市が町の回遊性を高める取り組みの一環として、近所にある航空公園のクラフトマーケットと同時開催のイベントを所沢駅周辺で計画していたんです。
そんなタイミングで、シン設計室の高橋さんが所沢市の担当者とつながり、私が「この場所でマルシェをやりたい」と話していたことを伝えてくれたんです。
インフラスタンドが最寄りの航空公園駅と所沢駅の中心に位置していたこともあり、まちの回遊性を高める事を目的にした所沢市の企画と親和性が高いということで、連携することになったんです。人とタイミングに恵まれ、良いスタートになりました。

場所を開けば、自分たちの動き方も変わっていく
小澤さんがやりたいことを公言し、人に直接会いにいくことで、新たな縁が生まれてきたように感じます。今後、やってみたいことはありますか?


小澤
行政とのつながりができたことで、今では公衆トイレのプランニングにも関われるようになりました。
これからは、資源や水の循環など新しい技術を持つ企業さんとも連携しながら、街の観光や楽しみ方を変えるようなトイレを作っていきたいです。
当初の目的だった、トイレや水道業界のイメージを変えることには繋がりましたか?


小澤
インフラスタンドの活動を通じて、若い人も会社にエントリーしてくれるようになったんです。
水道工事の実務とのすり合わせなど課題はありますが、働きやすい制度や仕組みを考え直すことにもつながりました。
インフラスタンドの運営は、本業である水道工事のあり方を変える入口にもなっていると感じています。
できることが増えるに従って、実現したいことも増えていきますよね。


小澤
ただ、自分が社会に価値を提供できるのは水道工事の仕事であるということは、常に忘れないようにしています。インフラスタンドができたのも、KAWAYA市などのイベントが開催できたのも周りの人の協力のおかげです。
任せるべきところは任せながら、自分たちが広げられる仕事の領域を、少しずつ開拓していけたらと思います。


【編集後記】
誰もが使うのに、無機質で遠ざけたくなる、そんなトイレという空間を、ここまでやさしく、あたたかく変えてしまうなんて、と驚きました!
「インフラスタンド」が目指したのは、ただの“キレイなトイレ”ではなく、人が集い、思いが交差する“まちの居場所”。小澤さんの想いに共鳴した人たちが集まり、DIYで少しずつ、でも確かな温度を持って作り上げた空間には、便利さ以上の「人の気配」が宿っていました。
何気ない日常のなかに、こんなにも心が動く風景があることを小澤さんのお話やインフラスタンドに訪れて感じることができました。
(WORK MILL編集長/山田 雄介)
2025年2月取材
取材・執筆=淺野義弘
写真=吉田一之
編集=桒田萌(ノオト)