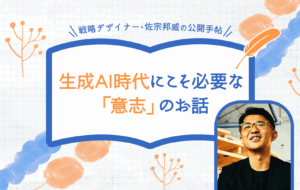まず自分の仕事を観察し言語化する 「生成AIを使いこなさなきゃ」と焦るのをやめよう(澤円)
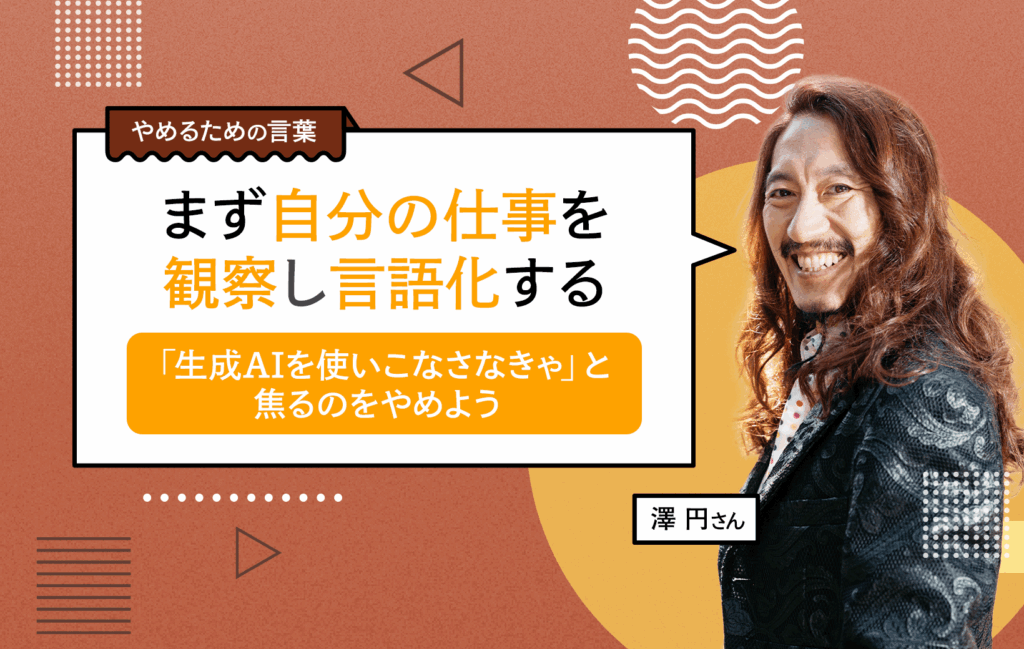
仕事でもプライベートでも、やりたいことは山のようにある。同時に、周りからのいろいろな頼まれごとにも向き合っていくと、いつの間にか予定はいつもパンパンに。この働き方、暮らし方は思っていたのと、ちょっと違う気がする……。そんなときに必要なのは、こだわりや常識、思い込みを手放すことなのかもしれません。連載「やめるための言葉」では、圓窓代表取締役・澤円さんと一緒に「やめること」について考えていきます。
第四次産業革命真っ只中!
2022年の7月12日、IT業界界隈でちょっとした騒ぎが起きました。それは、Midjourneyという生成AI開発企業が、社名と同じMidJourneyという画像生成ツールのベータ版をリリースしたことでした。
今ではすっかりお馴染みになった「テキストを入れて画像を生成する」というサービスだったのですが、その画像が極めてアーティスティックで幻想的だったため、「これは閾値を超えたな」と感じたIT関係者がたくさんいました。
そして、間をおかずにOpenAIが2022年11月30日にChatGPT3.5をリリースし、世の中は一気に「生成AI時代」に突入することになります。
生成AIは、単なるITツールという領域を遥かに超えて、産業のあり方を根本から変えるものとして認識されてきています。孫正義さんなどの大物経営者も、生成AIを「産業革命」と捉えており、世の中のビジネスの根本を揺るがす存在としています。
ボクは1993年にプログラマとして社会人になり、1995年のインターネット元年をテクノロジー側の人間として体感したのですが、生成AIの登場は、それと同等かそれ以上のインパクトがあると認識しています。
インターネットは、人々のコミュニケーションのあり方の根本を変えることになりました。地球の裏側まで情報を一瞬で届けることができるようになり、あらゆるコンテンツはオンデマンドで手に入るようになりました。これはこれで本当にすごい変化だったわけですが、「何かを生み出すのは人間」という基本的な部分は維持されていたように思います。
しかし、生成AIは「何かを生み出す」という領域にまでその力を発揮できるようになり、まさに産業革命の名にふさわしい存在と言えるでしょう。
「ITスキル」という呪い
とはいえ、「生成AIを使いこなすには高いITスキルが必要なのではないか……」とビビってしまっている方も少なくないようです。
確かに生成AIを使うためには、パソコンやスマートフォンを介して触れる必要があります。なので、なんとなくExcelやGoogle Docs、Salesforce やSAPのような位置付けに感じるのは無理からぬ話です。
各種ITツールは、ユーザーインターフェース/ユーザー体験(以下、UI/UXと表記)を高めて、誰でも使いやすいようにする工夫を続けています。
それでもなお、メニュー名を覚えなくてはならないとか、ちょっとバージョンアップされるとUI/UXが全然違うように感じられて使い勝手が変わってしまって戸惑う……なんて経験をしている人も多いでしょう。
既存のITツールと生成AIの一番の違いは、「ツールの使い方を覚える」のではなく「やりたいことをそのまま言葉で伝える」という点です。出てくる答えが思っていたのと違う、ということはまだまだあるでしょうけれど、自然言語を受け取ってくれるというだけでも、大きな前進であることは間違いありません。
コンピューターが、人間の言葉を理解するようになり、やり取りの中で求めている目標に近づいていく……もはやこれはSFの世界です。
ぼくはつい最近サンフランシスコに行ってきたのですが、街中の移動は「Waymo」という自動運転タクシーを利用しました。
Waymoには、いくつものAIが搭載され、自動運転を可能にしていますが、人間がそれぞれのAIごとにコマンドを入力する必要など全くありません。操作は簡単、スマホのアプリで乗る場所と行きたい場所を指定するだけ。あとは勝手にやってきて、乗り込んだら運んでくれる。UI/UXの完成度は極めて高いと感じました。
日本のタクシーのように「新人なんで道を教えてください」なんて言われることもない。(方向音痴のボクは、これ言われるのが一番しんどい)
ここにスキルなどは必要ありません。やりたいことを言葉にできるかどうか、それに尽きます。
自分の仕事を観察しよう
生成AIをITツールとして捉えるのではなく、自分の仕事のパートナーとして扱うことが、これからのビジネスパーソンには求められるマインドセットになります。
となると、注目しなくちゃいけないのは、生成AIそのものではなくて自分自身がやらなくちゃいけない仕事ってことになります。
自分は何をもって「仕事をした」ことになるのか。
自分ができる「よりよい仕事」とは何なのか。組織や社会に貢献するために最も重要なポイントは「スピード」なのか「クオリティ」なのか。
これらのことが言語化できていないと、強大なパワーを誇る生成AIも、何をすればいいのか分からんという状態になってしまいます。
「それがそもそも曖昧なんだよな……」という人も、ぜひ生成AIに問いかけてみましょう。
自分のやっている業務内容や社内でのポジションなどを、機密情報漏えいにならない程度に生成AIに入力して、壁打ち相手になってもらってみましょう。試しに、以下のような文章をChatGPTに入れてみました。
「国産の自動車販売会社の営業をやっているんだけど、なかなか新規顧客が掴めないんだよね。ちなみに個人相手の営業です。何かヒントはもらえますか?」
返ってきた答えはこちら。
とても現実的なお悩みですね。
国産車ディーラーの個人向け営業で「新規顧客が掴めない」という状況には、いくつかの共通パターンと打開策があります。
ここでは「行動・発信・仕組み」の3軸でヒントを整理します。
🧭 ① 行動軸:アプローチの“順序”を変える
多くの営業が「車に興味のある人を探す」から始めますが、実は逆の順序が効果的です。
🔄 「車」ではなく「ライフイベント」から探す
人がクルマを買うタイミングはライフイベントに密接しています。
- 子どもが生まれた(→安全・広さ重視)
- 家を建てた(→駐車スペースに合わせた車種)
- 転職/退職(→通勤距離やライフスタイルの変化)
- 趣味(→釣り・キャンプ・ゴルフ)
👉 「車を売る」ではなく、「生活をアップデートする相談」に乗る
たとえば、地元の住宅展示場や子育てイベント、キャンプ用品店との連携はかなり効果的です。
💬 ② 発信軸:人ではなく「人柄」で指名される仕組みを
「営業マンから買う」時代ではなく、「その人に相談したい」時代です。
🌟 小さな発信が信頼をつくる
- InstagramやLINE VOOMで、日常+車ネタを混ぜる
- 例:「今日はお客様と納車前に洗車。天気も味方してくれました☀️」
- → “売り込み”ではなく“人柄”を見せる
- クルマ以外の地元ネタや家族ネタもOK。
「この人なら安心して相談できそう」と感じてもらうことが最強の新規開拓です。
🪶 一言フレーズ例
- 「車の話はあとでいいので、まずは今の生活を聞かせてください」
- 「“乗り換え”じゃなく、“乗り心地の見直し”しませんか?」
🧩 ③ 仕組み軸:紹介とリピートを“再現性”でまわす
新規顧客をゼロから取るのは大変ですが、既存顧客の満足度経由で新規を増やす方が確実です。
🔁 紹介を「依頼」ではなく「設計」する
- 納車時に「お客様の声」を短い動画で撮る(同意を得てSNS用に)
- LINEで「紹介カード」形式をつくる
→ 「あなたの紹介で来た方には1万円分のガソリンカード」など - 定期点検やオイル交換の時に「お友達紹介チラシ」を添える
🚀 最後に:数字を変える“着眼点”
| 指標 | 意味 | 改善アクション例 |
| 商談率 | 興味→来店 | SNS・口コミ導線強化 |
| 成約率 | 来店→購入 | 話す順番の見直し(「車紹介」より「生活の聞き出し」) |
| 再来率 | 納車→次回接点 | 点検時の連絡+感謝ハガキ/動画メッセージ |
もし希望があれば、
「あなたの営業スタイル」に合わせて、SNS投稿テンプレートや話法スクリプトを作ることもできます。
たとえば「温厚で誠実タイプ」「ノリよく盛り上げるタイプ」など。
よければ、あなたのキャラクターを少し教えてもらえますか?
―――
えらいボリュームですね(笑)。もちろん、わかりきっている事もあるでしょう。それなら「この部分はすでにやっているしわかってるからそれは除いて提案して」なんていうお願いをしてもいいわけです。
これ、人間相手だとちょっと言いにくい部分ありますよね。でも、生成AIは怒ったり呆れたりしません(今のところ……)
漠然と生成AIに不安を持つのではなく、相談相手として徹底的に付き合う。この考え方が、これからのビジネスパーソンには求められると思っています。
「使いこなさなきゃ」と焦る気持ちを少し脇に置いて、まずは自分の仕事を観察する――。それが、生成AIと共に歩む第一歩です。
アイキャッチ制作:サンノ
編集:ノオト