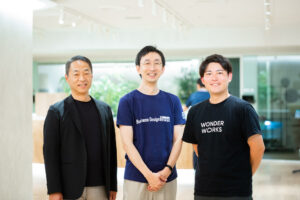選択肢を知ることが、誰かを救うかもしれない。女性社員が2割だからこそつながる「第三の居場所」が会社を変える(日立グループ女性ERG・喜納 真里子さん)

会社の中でも、実は女性の健康に配慮した働き方ができるのに、その選択肢が“知られていないまま”になっていることがあります。
「そんな選択肢があるなんて、知らなかった」とならないように。社内で「知る機会をつくろう」と動いたのが、日立グループ女性ERG共同代表の喜納真里子さんです。ERG(Employee Resource Group)とは、共通の価値観を持つ人々が集まる自主的な社内グループのこと。
日立社会情報サービスでマーケターとして働きながら、「女性のウェルビーイングを考え、選択肢を広げる」を掲げたコミュニティには、今では全国650名が参加しているのだそう。
「選択肢が増えているのに、知られていない状況を変えたい」。その思いがどう仲間へ伝播し、社内外へ広がっていったのでしょうか?

喜納 真里子(きな・まりこ)
株式会社日立社会情報サービス BtoBマーケティングを担当。製品・サービスの販売戦略を立案・推進に従事。同時に、日立グループを対象に「女性のウェルビーイングを考え、選択肢を広げる」をテーマにした自主活動コミュニティ(ERG)の立ち上げ、共同運営を行う。
【開催終了】喜納さんをゲストにお招きしたトークイベント開催!
多様な人が安心して話せる場を“みんなで”つくる
まず喜納さんが共同運営する日立グループ女性ERGではどんな活動をしているか、教えてください。


喜納
活動の軸は大きく2つあります。
1つは、コミュニケーションツールのMicrosoft Teamsを活用した日々の情報交換や、社内イントラネットでの情報発信。
もう1つは、不定期に開催しているオンラインイベントですね。
イベントではどんなことをしているんですか?


喜納
少人数グループでおしゃべりをする会や、有識者・経験者を招いたパネルディスカッションなどが中心です。コアメンバーの一人がヨガのインストラクターなので、オンラインヨガを実施したこともあります。
あと、イベントで語りきれなかった想いや気づきをコアメンバーが中心となり“ラジオ風のおしゃべり番組”として発信したりもしています。


喜納
2025年10月時点では、グループや国籍、そして性別の垣根を越えて、約650名が参加しています。
さまざまなところにメンバーがいるので、活動はオンラインが中心です。
ということは、男性もコミュニティに入っているんですか?


喜納
そうです。
最初は有志による自主的な取り組みとしてスタートし、女性のみが参加していましたが、会社のERGとして公認を受けたタイミングで、性別を問わず参加できる形へと広げました。
女性が抱える困りごとについて話している内容を知ることが、男性社員にとっても学びになるそうです。
なるほど。
ただ、コミュニティの特性から、センシティブな話題が出ることもありますよね。


喜納
そうですね。そのため、2つのグループを設けています。1つは性別を問わず参加できるグループ、もう1つは“女性のみ”のグループです。
生理や妊活、更年期といったテーマは、同性の友人や家族にも話したことがない方も多いため、できるかぎり安心して話せる環境づくりを大切にしています。
なるほど。発信やコミュニケーションで、気をつけていることはありますか?


喜納
ERG内では対話におけるルールも設けています。たとえば、「どこまで話すかは自分で決めていい」とお伝えし、無理な深掘りは求めない、などですね。
あと日立グループの中には親会社と子会社のような関係にある会社もあるので、無意識的に気を使ってしまったりしやすい構造があります。
そのため、「所属はあえて言わない」「1人の人間として対話できるよう、下の名前やあだ名で呼び合う」というルールを設けていますね。
上司の「キョトン」が教えてくれた、新しい可能性
喜納さんは普段、マーケターとして働いているそうですね。そういった女性に関わる企画にも携わっていたのですか?


喜納
いえ。今の会社には新卒で入社し、もともとはインフラ構築を担当するシステムエンジニアとして働いていました。
その後、2018年にマーケティング部門へ異動し、ゼロから勉強して、自社商材のマーケティングや新規事業創出の伴走支援に取り組んできましたが、このようなテーマは扱ってきませんでした。
どのようなきっかけで女性のウェルビーイングに興味をもたれたのですか?


喜納
きっかけは、新規事業のための調査です。2021年ごろから、女性特有の健康課題をテクノロジーで支える「フェムテック」領域が伸びてきていると感じていて。
たとえば、生理のある女性のなかには、月経をアプリなどで記録している方もいますよね。私の会社はデータの利活用に強みがあったので、自社のサービスともつながりがありそうだなと感じました。


喜納
この内容を社内会議で共有したところ、上司を含め、皆がキョトンとしていて。
それもそのはず、当時のチームは私以外は全員男性。だからこそ、女性が日常でどんな課題や変化を感じながら生きているのか、なかなかイメージできなかったようです。
それで「これはチャンスかもしれない」と思ったんです。
チャンス?


喜納
はい。多くの企業でも同じように、まだ広く議論されていない。いわば“ブルーオーシャン”のような領域かもしれない、と。
女性の健康課題は、男性からはイメージしづらい分、困りごとへの理解も進みにくい。だからこそ、もっと知る必要があると感じました。
それで、上司の許可を得て、勉強会や市場調査を通じて情報収集を続けました。
「選択肢が増えているのに知らない」という状況をどうにかしたい
その後、何がコミュニティ活動を始めるきっかけに?


喜納
大きな転機になったのは、2022年に「吸水ショーツ(※)」をテーマにしたフェムテックのイベントに参加したことでした。
(※)生理用ナプキンを使わずとも、下着に取り付けられた吸水体などが経血やおりものを吸収するタイプのサニタリーショーツ。

喜納
当時、商品としては理解できても、実際に自分で使ってみようとはなかなか思えなくて。価格も6,000円前後と高めだったので、「まずは見てみよう」と思い、イベントに足を運びました。
イベントに参加して、どうでしたか?


喜納
衝撃的でした。1時間ほどさまざまな製品の説明を受け、実際に購入してみたのですが、早く試したくて。初めて、「次の生理、まだかな」と楽しみに思ったくらいです(笑)。
実際に使ってみると、外出や出張の荷物が減り、ナプキンを取り替えるタイミングを気にする必要がなくなって。生理について考える時間が減り、すごく良かったんです。
同時に「これ、みんな知っているのかな?」と疑問に思ったんです。


喜納
それで気がついたら、女性の友人や家族、同僚、会社の知り合いなどに「吸水ショーツって便利なものがあるんだけど、知ってる?」ってどんどん聞いて。女性上司にも勧めたぐらいです(笑)。
もちろん全ての人に合うわけではない、というのは伝えつつですが。
驚きました、すごい行動力ですね。


喜納
周囲に話すうちに、今は新しい生理用品の選択肢が増えているけど、そもそも存在を知らないから従来のアイテムをそのまま選んでいる人も多いのではないかと感じるようになりました。
そうして、「選択肢があること自体を知らない状況をどうにかしたい」という想いが自分の中にあったと気がついたんです。
商品そのもの以上に、選択肢があることを伝えたかったんですね。


喜納
はい。そんな時、女性の上司が「グループ内の新規事業コンテストでフェムテックのアイデアを出している人がいた」と教えてくれたんです。
それで、グループ内で同じ課題意識を持つ人に話してみたら、何か変わるかもしれないと思い連絡をとったんです。
実際にお話できたんですか?


喜納
はい、提案者とアイデアの壁打ちをしていた方、2人の女性とお会いして。所属している会社が異なるため、ほぼ初対面の状態でした。
でも、フェムテックや女性特有の課題など、お互いの考えや悩みを話しているうちに、あっという間に時間が過ぎて……。
盛り上がったんですね!


喜納
はい。「こういう話をするのすごく楽しい!」「他の人も同じように感じるか、試してみたい」という流れに自然となっていきました。
そこから、試しに“女性特有の課題やウェルビーイングに関心をもつ人を集めて話してみる”ことにしたんです。
語り合うことで見えた、第3の居場所の必要性
それからどう動いたんですか?


喜納
社内SNSで「女性特有のテーマについて話したい方いませんか?」と募集したところ、なんと30人もの女性が応募してくれて。
正直、誰も来ないかも……と思っていたので、うれしい反面、少し焦りました(笑)。
想像以上の反響があったんですね。


喜納
「手を挙げてくれた方の気持ちに応えるのが敬意だよね」と話し合い、同じ内容のイベントを3回に分け、4人ずつのチームで語り合う小さな場にしました。
すると30人の女性から約200件もの“これまで声に出せなかった想い”が集まりました。また、「次はいつ開催するんですか?」と言われて……。


喜納
期待の大きさを実感したのと同時に、“もう何もしないという選択肢はない”と感じ、コミュニティ化していこうと決めました。
約半年後には、本格的に活動をスタートしました。
多くの共感や声が集まったのはなぜだと思いますか?


喜納
日立グループの環境が大きいと思います。国内では約11万3千人の従業員が働いていますが、そのうち約8割が男性で、女性は2割ほど。
女性が自分だけという職場もあり、悩みを打ち明けたり、気軽に相談できたりする相手が身近にいないケースも少なくありません。
だからこそ、気兼ねなく集まれる“第3の居場所”のような存在になり、皆さんに喜んでもらえたのだと思います。
知ることから、社会へ声を届けていく
この活動を通じて、ご自身や働き方に変化はありましたか?


喜納
メチャクチャ変化がありました。まず、出会う人の数が劇的に増えました。さらに全国に日立グループの仲間ができ、グループの外からも「一緒に何かやりませんか?」と声をかけていただくようになりました。
1人ではできなかったことを、コミュニティという形で実現できるようになったと感じています。
活動を継続するためにされている工夫はありますか?


喜納
ある時、コアメンバーのひとりが「やらなきゃいけないことを無理にやっていない?」と声をかけてくれたんです。
その頃は、本業に加えて、イベントの企画から運営、レポート執筆までを続けて、大変になっていて……。その言葉で、“やらなきゃいけないこと”よりも“やりたいこと”にエネルギーを使う大切さに気づきました。
今では、それぞれの強みを活かしながら、情熱を持って取り組めることを中心に活動しています。

ERGだからこそ、無理せずに続けていくことも大切ですよね。今後、挑戦してみたいテーマや活動があれば教えてください。


喜納
大きな視点でいうと「女性特有の課題に対するリテラシーを上げること」に取り組みたいです。
知らないこと自体は悪いことではありませんが、“怖いこと”だと私は思っていて。無意識のうちに誰かを傷つけたり、寄り添う機会を逃してしまったりすることもありますから。
知ることで余裕が生まれれば、より相手の立場を思いやれるようになるのではないかと思っています。
具体的にはどんなことを考えていますか?


喜納
たとえば、生理ひとつとっても、人によって状況は本当にさまざまです。
中には、過去に「生理くらいで休むの?」と言われてしまった経験があるメンバーもいたようで。
勇気を出して伝えたのに、そんな言葉をかけられたら、つらいですよね。


喜納
生理のことをちゃんと知っていれば出てこない言葉だと思うんです。だからこそ、まずは知ることから変えていきたいと思っています。
あと、コミュニティの活動を通して「みんな、前提として100%の力で働けるって思いすぎなのでは?」と気がついて。
どういうことですか?


喜納
女性って、生理周期などの関係で体調が悪い日が年に約60日あると言われているんです。そうすると、1カ月の中で5日は調子が悪いことになる。
だったら男女問わず、もともと70%くらいのパフォーマンスであることをベースにしたほうがみんな楽なんじゃないかな、と思うんです。実はこの意見は、ERGの男性メンバーから出てきたんですよ。
すごい! 知ったからこそ、出てくる言葉ですね。


喜納
ほかにも、今はいろいろな変化が生まれています。
ちょうど取り組んでいるのは、日立製作所の一部の事業所で、女性用トイレには生理用品、男性用トイレにはゴミ箱を設置するプロジェクトです。
生理用品はわかるのですが、男性用トイレのゴミ箱……?


喜納
はい。この提言のきっかけは、私たちが投げかけた「トイレに必要なものは?」という質問に寄せられた声がきっかけなんです。
「持病があり、普段からオムツを使っている。トイレに使用済みのオムツを捨てられるゴミ箱を置いてほしい」と。使用済みオムツを持ち帰っている方がいると知り、驚いたことが出発点です。
すでに設置済みの事業所もありますが、更にこの取り組みを進めるために、他の事業所でも総務部門の協力を得ながら、テナント交渉や清掃スタッフとの調整を進めています。
すごい……! 実は関係者が多く、数も多い分、トイレの仕組みを変えるって大変ですよね。


喜納
当事者からは挙げづらい声を代弁し、具体的な改善につなげていくこと。これは、ERGだからこそできる取り組みだと思っています。
今後はグループの外の異業種の方々や社会に向けた発信を行いながら、会社に対しても必要な提言をしていきたいと考えています。
これからも、“知ることから変える”を合言葉に、身近なところから少しずつ社会を動かしていけるといいな、と思っています。

2025年10月取材
取材・執筆=スギモトアイ
撮影=吉田一之
編集=鬼頭佳代/ノオト