東京との距離感が、情報を取捨選択してくれる ー 明石の出版社が語る「地方の良さ」

「出版不況」という逆風のなか、2016年9月創業のライツ社は『リュウジ式悪魔のレシピ』(9.1万部)や『売上を、減らそう。』(5.6万部)といったベストセラーを次々と世に送り出し、業界内で注目を集めています。出版社が数多く集まる東京から遠く離れた、兵庫県明石市で本を出版する代表の大塚啓志郎さんと髙野翔さんは、地方で働くことにデメリットは感じないと言います。
あらゆるものが東京に一極集中する日本の社会構造のなか、閉塞感を覚える地方在住者も多いでしょう。それでもあえて東京から距離を置くことで、見いだせる打開策があるとすれば、それはどんなものでしょうか。彼らの仕事観や大切にしている価値観から、これからの働き方を考えます。
「海とタコと本のまち」明石の未来は明るい
WORK MILL:前編でもお話しされた通り、出版社のほとんどは東京に集中していますが、地方でハードルを感じることはありますか。
大塚:基本的には、やっぱり東京にはおもしろい人がたくさんいるので、東京在住の方と本を作ることが多いです。でも、明石に住んでみると、神戸空港から飛行機で1本なので、京都のときよりも東京に行きやすいんですよ。もともとは左京区という、京都駅まで1時間くらいかかるところにいましたから。だからといって、そこまで明石でやっていることにこだわりもない。特別、明石や関西にフォーカスした本をつくっているわけでもありませんからね。

ー大塚啓志郎(おおつか・けいしろう)
ライツ社 代表取締役 編集長。1986年兵庫県生まれ。2008年京都の出版社に入社し、編集長を務めたあと30歳で独立。2016年9月に兵庫県明石市でライツ社を創業
大塚:ただ、僕らは普通の感覚で接していても、東京の方がすごく反応してくれるんですよ。「明石にある出版社です」っていうだけで珍しがられるし、興味を持ってもらえる。本を書いてほしい、とお願いしたい方に会うと、「遠くからよく来たね」とむげにされることもないし、関西の方なら「一緒に西から盛り上げていきましょう」なんて言ってもらえる。
髙野:営業でも同じですね。東京へ営業に行くと「わざわざ来てくれてありがとう」と言ってもらえるし、関西の人が相手だと「おう、明石でよう頑張ってるやん」となる。
大塚:たぶん大阪や神戸だったら、そうはならなかったのかなと思います。ちょっとはずれた所にある明石だから、より田舎に、遠く感じてもらえるというか(笑)。同じ職能で同じ仕事をしていても、場所を変えるだけでそれがオリジナリティになったんですよ。
WORK MILL:神戸市内から30分くらいですけど、「わざわざ来てくれた」感があるのかもしれませんね。
髙野:明石ってちょうどよいというか、銀行の人も知っているし馴染みの店もあるし、みんな顔が見える距離感なんです。いま思えば、京都ですら広いくらいでしたね。
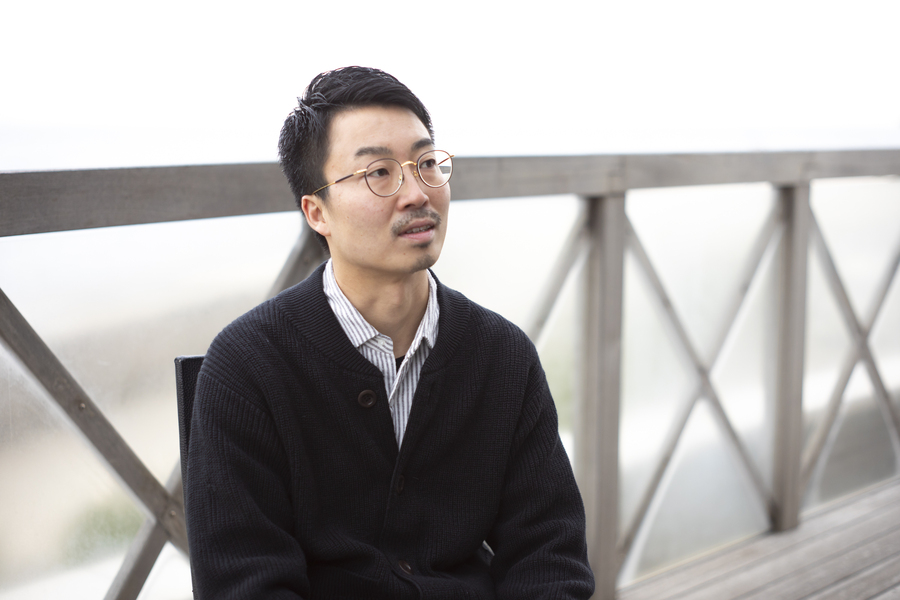
ー髙野翔(たかの・しょう)
ライツ社 代表取締役社長 営業責任者。1983年福井県生まれ。京都の出版社で営業マネジャーを務めたのち、2016年9月に兵庫県明石市でライツ社を創業。
大塚:あとはおそらく、東京とは圧倒的に情報量が違うんですよ。IT企業で毎日情報発信するような仕事なら、そっちのほうがいいんでしょうけど、僕らは年に6、7冊しか出版しないので、ある程度情報の取捨選択が必要です。そういう意味では、明石に暮らして、ここまで伝わってきて共感もできるものなら、本物だということ。間違いなく、他の大多数の地方にお住まいの方でも共感できるものだと、肌感覚でわかるんです。
髙野:よく東京の方に言われるのは、「これって面白いと思うんだけど、地方で売れるかどうかわからないんだよね」という言葉です。地方の本屋さんのイメージが湧いていないから、わからない。でも僕らは地方で売れる本がわかる。そして地方で売れる本は絶対に東京でも売れます。その逆はあまりないのですが。
WORK MILL:「都市部でしか売れない」というのはよくありますからね。
大塚:だから、必要なトレンドにしか乗らなくていいし、必要な情報だけ取ればいい。月に1、2回東京に行って、必要な情報だけを受け取る。変化のスピードに惑わされることもないし、自分たちのリズムでやっていけます。東京を好きでいられる距離感にいると、やっぱり東京ってカッコいいですよ。東京って面白いなって、ずっと思っていられる。
WORK MILL:地方にいながら、必要とあればどこにでも行く。おふたりからはフットワークの軽さが感じられます。
大塚:出版社って昔から「机と電話、ふたつあればできる職業」って言われていたんですよ。パソコンがなかった時代からの原点に立ち返れば確かに、東京にいる必要はない。実際にやってみてそう思いました。
髙野:ここは海が近いし、好きな人もたくさんいるし、好きな場所。ここで暮らしながら、会いたい人には全国どこでも会いに行く。仕事ではありますが、書店員さんや取次の方は同じ本に携わる同志だと思っています。だから、仲の良い先輩や友人に会いに全国へ行っている感覚です。

WORK MILL:うらやましい(笑)。「取引先に行くのが憂うつだなぁ」と感じている営業さんも多いでしょうから。
髙野:もちろん、そう思えるようになるまでには時間かかりましたけどね(笑)。前職のとき「出版営業のための本」みたいなのを読んだら、「コートを着ると作業の邪魔になるから、コートを着るな」って書かれていたんですよ。それを真に受けて、真冬の北海道にコートなしで出かけたんです。そうしたら「なんて格好で来るんだ!?」って書店員さんに驚かれたりして。
大塚:髙野はそんなふうに、地道に営業していて。「同じ100冊売れる本だとしても、全然会ったこともない出版社の本を売るより、来てくれた人の本を売りたい」と言ってくれた書店員さんもいて。そういう人間関係を築いてきてくれました。それと明石で良かったのは、ちょうど僕らが出版社を立ち上げようとしたところに、市長さんが「本のまち 明石」って謳いはじめたんですよ。
髙野:銀行へ行ったら、「明石って本の街になるらしいですね。それなら確かに出版社も必要ですもんねぇ」みたいな話になって。僕、外部のコンセプトには全部乗っかるタイプなので「そうなんです。本の街で出版社つくります!」と言って(笑)
WORK MILL:すごいタイミングですね。それはたまたまそうだったのでしょうか、それともライツ社が創業するから……?
大塚:どうでしょう、市長さんからは「話は聞いてますよ。頑張ってください」とは言っていただきました。2017年に駅前の再開発で複合商業施設がオープンしたんですが、そこには公立図書館とジュンク堂書店が一緒の建物に入っています。普通なら共存することのない関係のはずだから、すごくレアですよね。つまり、それだけ本の世界に浸れるというコンセプトなんです。
髙野:だから、本に挟んでいるライツ社のおたよりにも書いたんです。「海とタコと本のまち 兵庫県明石市の出版社」って。

WORK MILL:駅からここへ歩いて来ましたが、駅ビル、立派な建物ですよね。にぎわっている感じがしました。
大塚:あそこだけ都会。海のほうに行くとのどかなんです。
WORK MILL:市長さんから「話は聞いてます」と言われる距離感の近さも、すごいなと思います。ただ一方で、そういった近さが煩わしくなることもあって、地方に住んでいる方からは「人間関係が限られてるから、あまり目立つことはできない」という声も聞かれます。
大塚:そういう意味では明石の場合、街に閉塞感がないのが非常に大きいかもしれません。全国的にはいま、地方って何かと暗いじゃないですか。
WORK MILL:多くの地方では、人口が減少し続けていたり、駅前の商店街が寂れて、郊外のショッピングモールのほうが栄えていたりしますよね。
髙野:僕の地元の福井とか、まさにそんな感じですからね。
大塚:でも明石はここ最近ずっと人口が増え続けていて、特に子育て中の世帯が増えているんです。僕らが引っ越してきたときは保育園が足りなくて1年待たなきゃいけないくらいでしたが、それが解消されてからはものすごく暮らしやすい。街が明るいんですよね。人口が増えて、駅ビルもできて、でもそのビルの中には昔ながらの横丁がそのまま入っていたりして。経済も活発になって、どんどん美味しいお店も増えている。だからみんな、温かく見守ってくれるんだと思います。

本を作る上で、本当に必要なことだけをやっていく
WORK MILL:おふたりとも職場のすぐ近くに住んでいるとのことですが、職住近接の暮らしにはメリットを感じますか。
髙野:すぐに帰れますし、働く時間は以前の2/3になったので、大切な人と過ごす時間も増えましたね。家はコンパクトだけれど必要なものは揃っているし、住んでいて気持ちがいい。僕ってあまりオンオフの切り替えができないタイプで、家に帰ったところで「仕事モードから切り替わる」みたいなのはありません。逆に仕事モードにもなっていないんですけど(笑)
大塚:髙野はそもそも、本がものすごく好きな人間なんですよ。本の世界にいたい人間で、書店という空間が好き。それに、できれば仕事をしたくないと思っている。そんななかで仕事をするには……。
髙野:いちばん好きなことを仕事にしたい。だから、本なんです。
大塚:……と、前職の面接で言っていたんです。だから、オンオフがない。僕はどちらかというと「得意だから、本に関わる仕事をしている」というタイプで、オンオフをしっかり切り替えるんですよ。18時か19時にはパッと帰って、土日にはできる限り仕事をしない。この距離でもバチっと切り替える。東京出張などは「仕事をしに行く」という感じだから、妻から連絡が来てもほとんど返信しません。
髙野:びっくりしますもん。「ビジネスライクやなぁ」って。
WORK MILL:働く環境は同じでも、それぞれ働き方や仕事観に違いが出るのは面白いですね。意外なのは、なんとなく編集者のほうがものすごく本が好きで、情熱を注いで本を作っていて、営業はあくまでビジネスライクにやっている……というイメージがありました。
大塚:確かにそういうところは多いでしょうし、逆にその背景もあって、出版社のなかで営業が「下」に見られていたり、編集の意見しか通らなかったりすることもあるんです。でも僕らの場合、それが逆だからいいんでしょうね。
髙野:本屋さんに行くこと自体が好きなんですけど、前職で幸いにも全国の個店舗営業をさせてもらっていたので、ほぼ全都道府県に顔見知りの書店員さんがいるんですよ。いまは本部営業といって、書店を総括する部門とやりとりするだけの出版社も多いですが、そのおかげで本部でもある程度現場が見えているうえで話をすることができます。売場規模がわかっているので、どこにどのくらい置かれるか、立体的に見えてくるんです。「この料理の本をあの売場に置いたら絶対に売れるはずだから、厚く積んでもらえるように案内しよう」って。そうするとやっぱり売上も違います。

大塚:業界がいま厳しいと言われているのは、数を打てば何か当たるという考え方で、多くの出版社が大量に本を出版して、書店からの返品が大量に戻ってきて、それを穴埋めするためにまた新刊を出す悪循環に陥っているから。それで出版社も取次も書店も、余分な仕事が増えてみんな苦しんでいます。僕らは、印刷部数も書店への案内数も徹底的に適正数を意識しています。余分な在庫を持たず、持たせず、重版するのも少しずつ。おそらく他の出版社だったらもっとたくさん刷っているはずです。
WORK MILL:お話をうかがっていると、考え方はものすごくシンプルですよね。いまはデジタルツールも普及していますし、さまざまなデータがあるはずなのに、多くの会社が「モノが売れない」と苦しんでいる。もっと「現場」に目を向けるべきなのかもしれません。
大塚:最先端の人たちを見ていて感じるのは、「PDCAサイクルを高速で回すのが大事」みたいな風潮ってありますよね? でも、本当にそこまで超高速回転が必要なのか、少し疑問に思うんです。僕らもそれなりにトライアンドエラーをやっていますが、何かに追い立てられるほどのペースではやっていない。本当に必要なものしかやっていない感覚なんです。ある意味僕らは、その人たちがいろいろ試した結果を見ていられるから、正しい答えを選べるのかもしれないけど。
髙野:その渦中にはいませんからね。
大塚:それでも十分間に合ってしまうんです。マイナスな言い方かもしれないけど、多くの地方で何かが流行るのは、東京よりも時間差がありますから。
髙野:首都圏の書店と、地方の書店では並んでいる本がまったく違います。渋谷とか六本木に行くと、やっぱり「めっちゃ尖ってるなぁ」って思います。でも、僕らは東京と地方の感覚を両方持っていられるから、ありがたいことだなぁと。それが日本の全体像だし、だからこそ面白い本をつくることができる。

大塚:コミュニケーション・ディレクターのさとなお(佐藤尚之)さんという方から教えてもらったんですが、都道府県別の人口あたりの検索数を見てみると、東京だけ突出してるんですよ。次点の大阪すら東京の2/3で、東京ほどインターネットで情報を見ている地方って、他になくて。悪く言うつもりはないけど、かなり狭い世界でビジネスを成功させようとしてるんじゃないかな……と思ってしまいます。
髙野:僕らの本の売上って、東京が4割くらい、それ以外が他の地域なんですよ。
WORK MILL:東京で働いていると、どうしても「ここでしか稼げない」と錯覚してしまうのかもしれません。
髙野:独立したとき「東京でやらないなんて、本気じゃない」って言われたこともありましたけどね。「数年後、ちゃんと本気だったと言われるように頑張ります」と言い返しました。
大塚:もっと売上アップや事業拡大を目指すなら、東京へ行ったほうがいいかもしれないんですけど、僕らはそこを目的に働いてはいないから。
業界の外へ出れば、スキルが特別となる舞台はたくさんある
WORK MILL:売上増や事業拡大が目的でないのなら、何がモチベーションになっているのですか。

大塚:本を出版して売るのが出版社の役割だとして、本がベストセラーになって、誰かの世界を変えることができるなら嬉しいことではあります。それはそれで生業としてやっていこうと思いますが、もっと僕らの職能を他の業界にスライドさせると、実はもっと役立てることがあるんじゃないかと考えています。
『最軽量のマネジメント』という本でIT企業のサイボウズと組んで、「サイボウズ式ブックス」を立ち上げたのはまさにそういう意図でした。「本をつくる」こと……考え方や思いをパッケージにして、流通させて最大化するという、僕らの職能を外に出すことで、本にできることが増え、本に触れ、本に関わる機会が増える。そうすると本がもっと売れる──。そういうサイクルになれば、理想的だな、と。

WORK MILL:ネットを通じて情報収集することは容易になりましたが、一方で「本」というフォーマットでなければ得られない情報もありますし、本だからこそ所有欲をかきたてられることもありますよね。
大塚:さかのぼると、江戸時代は本屋さんが本をつくっていたんです。身の回りの面白い話や文化を「これ、面白いから本にまとめよう」って呼びかけて、書き手や絵描き、印刷師や製本師を集めて本をつくって、その場で売っていた。でもいまや、地方の書店のほとんどが東京でつくられた本を売るためだけの場所になっています。そのうえAmazonができて、「書店に欲しい本が置いてないから、こっちで買おう」となっている。
いま、大阪のとある書店さんが「大阪の小説をつくりたい」と言っていて、それを一緒にやる話が進んでいます。地方に本屋がある意味が薄れてきたなかで、原点回帰してもう一度本屋が本をつくろうとしている。地元の書店、地元の作家、地元の出版社が、地元の読者のために地産地消の小説をつくる。そこでしか生まれない文化があるからです。
WORK MILL:その土地で生まれて、そこでしか買えない本、ということですね。
大塚:はい。ほかにもホームレスを支援するNPOと組んで、クラウドファンディングを活用した資金集めから、本の製作や流通までお手伝いして、認知を広げる手段とする。そうやって、本と関わる人が増えていけば、出版業界が活性化したり、本の価値が高まったりするかもしれない。僕らのできることは限られているけど、僕らのスキルが特別となる舞台はたくさんあるんです。
髙野:そうやって出版社のできることを増やして、出版社の新しい形を提示して、「本って面白いな」「物語って素晴らしいな」と感じる人が増えて、「斜陽産業」と言われる出版業界の面白さに気付いて、若者や新しい人が入ってくれると嬉しいですね。
だから、ライツ社自体のスケールが目的ではないといっても、出版業界そのものをもっとスケールさせたいんですよ。僕はマネジメントが苦手なので、会社を大きくさせるつもりはない。その代わり、外部の面白い人とどんどんつながって、有機的なつながりを増やしていきたい。業界に明るいニュースを届けたいんです。

大塚:出版業界の古い仕組みはいろんなところで否定されているかもしれないけど、本をつくり届けるのに最適化された仕組みと会社と、流通網があって、これはこれで最強なんです。だから、それをもっと他の人にも活用してもらえたら。僕らが「出島」みたいになって、「ここから入ってきてください」って。
髙野:もともとそういう土壌はあるんですよ。外の面白い人に本を書いてもらって、その価値を最大化するのが出版社の仕事だから。
大塚:面白い人を消費して、燃やし尽くしてしまうのがいまの世の中かもしれないけど、僕らは薪をくべ続けていたい。種火を持った人に灯をともす存在でいたいんです。
2020年5月26日更新
取材月:2020年2月




