『ゼロからの共創』著者の庵原悠×WORK MILL 岡本栄理が語る「共創」。WORK MILL10周年イベントレポート (前編)
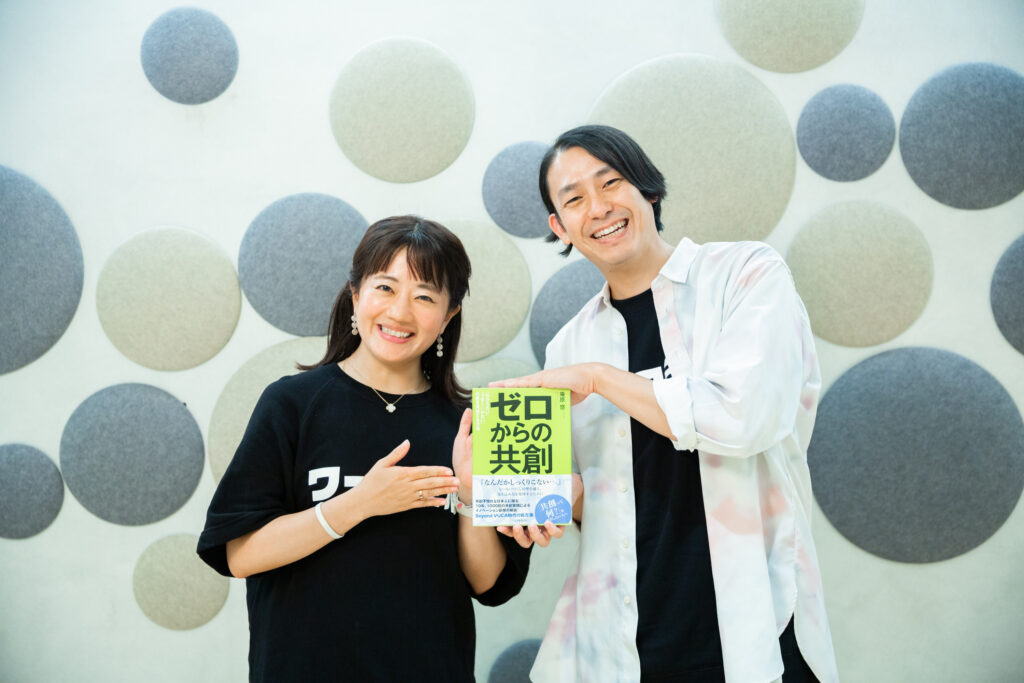
現在、「共創」という言葉はさまざまな場面で当たり前に使われています。WORK MILLは、2015年の立ち上げ当初から共創活動に取り組み、その価値や意義に真摯に向き合ってきました。
とりわけ、共創を通じて芽生える「自分って、こんなこともできる」という自己効力感、そして「うちの会社って、実はすごいのかも」という自社肯定感を、WORK MILLは重要な価値観として位置づけています。
2025年8月26日(火)、「WORK MILL 10周年 & 『ゼロからの共創』出版記念イベント」をOpen Innovation Biotope “Sea”で開催しました。今回は、第一部「WORK MILLの10年を語り合う!共創対話会」をレポートします。
登壇者は『ゼロからの共創』著者であり、WORK MILL立ち上げメンバーのひとりである株式会社オカムラの庵原悠と、WORK MILLのコミュニティマネージャーとして大阪・東京で共創活動を推進してきた株式会社オカムラの岡本栄理。
オカムラの新卒同期でもある二人が、出版に至るきっかけや本書の要点を紐解きつつ、現場での実践から得た学びを語り合いました。
WORK MILL 10年で作った新たなステートメント「もっと、ぜんぶで、生きていこう。」

岡本
WORK MILLが10周年を迎えるタイミングで、ステートメントを「もっと、ぜんぶで、生きていこう。」へ変えたんです。
この言葉はどんなイメージですか?

岡本
WORK MILLメンバーらしさがより強く表れた言葉になったと感じていますね。
WORK MILLの立ち上げ当初に掲げたステートメント「働く環境を変え、働き方を変え、生き方を変える。」でした。これは、当時のコアメンバーで決定したもので、今の現場メンバーはまだWORK MILLにジョインしてませんでしたよね。
でも、今のステートメント「もっと、ぜんぶで、生きていこう。」は今のWORK MILLメンバー自身の、現場や人を大事にする想いが前面に出ていると感じます。

庵原


岡本
変わらず持ち続ける軸は大切にしつつも、時代に合わせて表現を更新することも、活動を続けていくのには必要で。
だからこそ、現場の私たち自身が“自分の言葉”として語れるものへとアップデートしたんです。


岡本
オカムラの共創の取り組みは2012年に「Future Work Studio “Sew”」という名で始動しました。
その後、2015年に部門横断によるWORK MILLプロジェクトとして本格始動、その後10年の間に東京・名古屋・大阪・福岡の4拠点を整備したんです。
この10年の中で、何が転換点だと思いますか?

いくつかありますが、大きな転換点の一つはコロナ禍ですね。
人が来られない状況に直面しましたからこそ、改めて共創空間やコミュニティーの大切さを再確認できたと思っています。

庵原

岡本
リアルな場を大切にしてきた共創担当としては正直あの時は大変でしたが……、テクノロジーの恩恵もありましたよね!
そうですね。リモートワークや資料作成の共同編集なども当たり前になりましたね。
分かりやすく「共に創る」ことを促進されて、共創の土壌が一段階上がるきっかけになったな、と思います。

庵原
なぜ日本で共創が必要なのか?

岡本
庵原さんは今回、『ゼロからの共創』を執筆されましたよね。
きっかけについて教えてください。

約10年のWORK MILLなどでの現場経験や共創の研究を通じて、共創にはさまざまな形があると実感しました。
たとえば、企業と大学の産学共創や市民主体の市民共創。共創を支援する場も、フューチャーセンターやリビングラボ、コワーキングスペース、ファブ・ラボなどがある。
これらは、名前や形は違っても共通する要素はたくさんあるんです。

庵原

だからこそ、共創を横断的に整理し、その中でも特に「なぜ、日本で共創が必要なのか?」という目的意識と、「How To」を当社の経験を踏まえてまとめました。

庵原

岡本
本書で一番伝えたかったことは何ですか?
やはり、共創は「誰でも取り組むことができる、皆が取り組む価値のある働き方」ということですね。
これまで共創は先進的な手法として研究されてきた経緯があり、「専門家が担う特別なもの」という印象が先行していました。
ですが、現代日本の社会背景を踏まえれば、共創は誰もが取り組める。さらに言い換えると、「働き方」の一つとして捉えられると思うんですね。

庵原

共創に必要な要素を分解する
共創って、人によって捉え方がちがうし、全体像を把握しづらいと思うんです。
そこで、本書では、
・「共創の場」
・「共創」
という2つの観点を設けました。でも、箱物としての空間をつくるだけではなく、運営や計画も必ず必要です。
そこで、運営・計画・空間の3つを、それぞれ4つの要素に分解して整理しました。

庵原
運営=信念・思考・手法・体制
計画=目標・成果・入口・型
空間=機能・特設・意匠・発信

岡本
なるほど!
この分類で見ると、私たち株式会社オカムラは家具メーカーなので、空間先行型の共創のご相談が多いですよね。

会社の特性上、そうなりやすいですよね。
ただ、実際には空間を整えたあとで「運営がうまくいかなくて……」という相談を受けるケースも多い気がします。

庵原

岡本
そもそも空間と運営は両輪なのが、あまり認識されていないのかも……?
組織の仕組み上、空間づくりと運営は別予算・別部署で進められることが多いから、縦割りになってしまう、という背景もあるようですね。
ですが、最近では空間と運営を両輪として捉える雰囲気も出てきたと思います。

庵原
改めて、共創の定義とは?

岡本
今回、改めて共創を定義していますよね。
この本では、共創を「ともに、共通善に向けて価値創造する行動、状態」と定義しました。

庵原

その中でも、特に「共通善に向けて」の部分がポイントです。
パーパス経営やESG投資など「共通善」に向かう取り組みが社会的に評価され、企業活動が後押しされる時代ですから。

庵原

岡本
この場合、共創のアウトプットはなんですか?
価値創造です。しかし、その価値は必ずしもその会社の商品に関わるものだけじゃありません。
オーストリアの経済学者・シュンペーターが提唱した「イノベーションの新結合」という概念では、「プロセスの革新、市場開拓、組織・チームといった新しいルールづくりもイノベーション」と定義されていて。
つまり、価値創造とは「モノ」を生み出すことだけではなく、仕組みや関係性を変えることも含まれるんですよね。

庵原


岡本
日本語訳の「新価値創造」では、どうしても結果を出すことに注目がいきがちです。でも、価値が生まれやすい土壌をつくることも本当は大切だと言われていて。そこに共創が効くんですよね。
では、どうすれば共創はうまくいくのでしょうか?
自分は「合理性」と「属人性」がコツだと考えています。
合理性とは、効率性や経済合理性を追求すること。ただし、それだけでは共創はうまくいきません。
現場で大切なのは人の想い、つまり「属人性」です。この思いを尊重し、うまく活かしている場ほど成功しているのです。

庵原



岡本
「合理性」と「属人性」を同時に両立させるというのは、一見対極のことなので、不可能に見える。
ですが、よく考えると振り子のように行き来しながら共創の現場ではそれぞれを実践している気がします。
まさにそういうことです。また、共創の現場には支援役を指す「コミュニティマネージャー」という言葉がありますが、一方で主体的に共創を推進する人を指す言葉はみあたらないと思っていて。
そこで、場を盛り上げ、ときには起業家をフォローし、事業やプロジェクトに直接関わる人材を「共創人材」と定義しました。この「共創人材」を増やすことが、企業を牽引する次世代人材の育成にもつながるのではないでしょうか。

庵原

岡本
そう思うと、我々WORK MILLのコミュニティマネージャーも厳密には共創人材と言えますね。

現場での失敗が共創のスパイラルアップへ

岡本
ここからは、私自身が共創の現場を作ってきた中で経験した、3つの失敗事例から得た学びをお話します。


岡本
第1の失敗は、自分らしさを見失っていたこと。
コミュニティマネージャーになったばかりのころは、慣れない司会をするのに台本に依存していたんです。ある日、PCが固まり資料が映らず、自分の言葉が出ない大失敗をしてしまって……。
でも、常連の参加者さんから「岡本さんは岡本さんらしくやればええんやで」と言ってもらってはっとしたんです。
共創とは、目の前の人とのコミュニケーション。ちゃんと自分の言葉で話し、「伝わる」ことが大事だと気づきました。


岡本
第2の失敗は、予定調和にこだわりすぎていたこと。
あるトークセッションの準備として、進行スケジュールやレイアウトを綿密に組んでいたんです。
そうしたら、それを見て「台本なんていらないよ!ない方が楽しいよ!」と会社の先輩に段取りをぶち壊されるという事態が起こり……(笑)。


岡本
不安ばかりでしたが、結果として満足度が高く、腹落ちする対話が生まれたんです。
イノベーションは、人と人の感性の混じり合いの中で、新しい何かが生まれること。共創空間は、そのライブ感を生み出す場だと感じました。


岡本
第3の失敗は、女性の働き方をテーマにしたイベントで起きました。
私が「お茶出しは女性の役割」という通念に異議を投げかけたところ、参加者の1人から予想外の反論を受け、場が凍りついてしまったんです。
その時、その場にいた大阪大学でキャリアを専門にされている先生が「白黒はっきりさせなくてもいい。その間にある曖昧な状況をしっかり見つめて語り合うことが大切」と場を和ませてくれて、その後ちゃんと参加者同士で対話することができました。


岡本
その時に、価値観や世代間の違いってもちろんあるけれど、向き合って対話を重ねることで乗り越えていけるのだと学びました。
まさに「和して同ぜず」が大切だと気づきましたね。
岡本さんの経験はインドの経営学者サラス・サラスバシー教授が提唱した「エフェクチュエーション(※)」とも通じるな、と思いました。

庵原
(※卓越した起業家に共通する意思決定プロセスや思考方法を体系化した市場創造の実行理論)
10年の積み重ねで見えてきたのですが、岡本さんのように体験から学ぶ人もいれば、理論から入る人もいます。現場の体験を理論の往復の中で、失敗をスパイラルアップ(好循環)につなげていくことが重要です。
両輪が揃うことで、共創の場はより豊かになるのではないでしょうか。

庵原

変わらない「オカムラっぽくない」 価値観と10年後に見たい景色

岡本
改めて、10年間、WORK MILLを続けられた理由は何だと思いますか?
「オカムラっぽくない」という客観的な価値観が大きな理由だと思います。
この言葉は常々社外の人たちからも言われてきましたが、実は発足当初から意識していましたね。

庵原

当時から共通善を考え、オカムラという企業名よりもWORK MILLという名前を表に出すようにしていました。
振り返ってみると、我々の活動のポイントとして考えていた
・透明性
・アクセシビリティ
・多様な視点
・社内外の専門家や当事者とのオープンな共創
があるからこそ、「オカムラっぽくない」に繋がっているのかと思います。

庵原

岡本
この価値観はずっと大切にしていきたいですよね。
長くなってきましたが、このセッションの最後のテーマは、私たちが「10年後に見たい景色」についてです。
個人的には、東京以外の場所でのイノベーションや価値創造の種に興味がありますね。
大阪・関西万博をきっかけに関西圏が盛り上がるなど、むしろ東京より面白いことが起きそう、と感じていて。
また、共創人材が浸透していった景色も見たいですね。日常的に共創しなくても、部分的にでも取り入れることで、変わっていく未来もあるのではないかと楽しみにしています。

庵原

岡本
そうですよね。私は共創や「もっと、ぜんぶで、生きていこう。」という言葉を使わなくても、この考え方が当たり前になるといいな、と思っています。
WORK MILLの役割はその転換点を生み出すこと。多くの人と共に取り組み、楽しく活気ある社会をつくっていきたいです。
本日はありがとうございました!
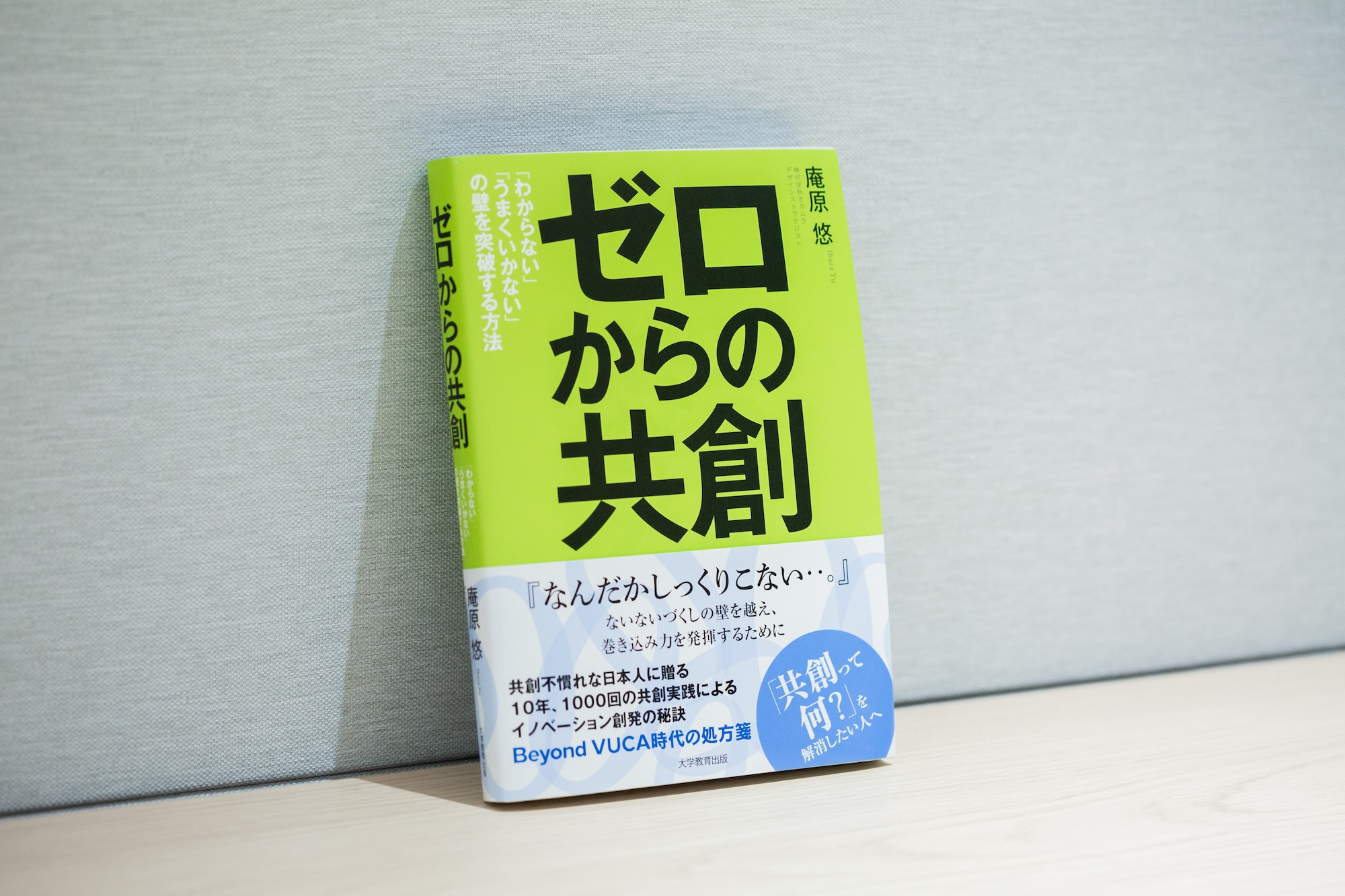
2025年8月取材
取材・執筆=西村重樹
撮影=栃久保誠
編集=鬼頭佳代/ノオト



