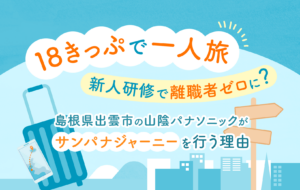参加社員数は1100名以上! 出光興産が実施する仕事のお祭り「ジョブ・フェスティバル」が年々盛り上がる理由

会社の中で、今後のキャリアをどう描けばいいのかわからない。同じ会社でも関わりのない部署がどんな仕事をしているのか実は知らない。そんな人は意外に多いのではないでしょうか。
そんな課題を解決するために、出光興産株式会社が年に一度開催しているのが「ジョブ・フェスティバル」です。
自社の社員向けに、出光興産グループの多様な仕事を知ってもらうために始まったイベントですが、第3回の来場社員数は約1100人にものぼるほど。年々盛り上がりを見せるイベントにしていくために、どのような工夫がされていたのでしょうか。
ジョブ・フェスティバルの運営責任者である出光興産・人事部の鎭野雄次さんにイベント運営の舞台裏を教えていただきました。

鎭野 雄次(しずの・ゆうじ)
2006年、出光興産へ入社。北陸支店を経て、2010年よりアグリバイオ事業部(当時)で、微生物発酵・培養技術を応用した畜産用資材の営業職へ従事。2020年に経営企画部へ異動。2023年より人事部にて、人事異動や評価、人事制度の策定のほか、キャリアチャレンジやジョブ・フェスティバル等のキャリア形成支援策の企画運営を担当。
自社の多様な仕事を知る機会として始まった
出光興産では、自社の社員を対象に各部署が業務内容を紹介する「ジョブ・フェスティバル」を開催していると伺いました。どのようなイベントなのでしょうか?


鎭野
ジョブ・フェスティバルは出光興産グループの社員約6000人を対象にした、社内の多様な仕事を知ってもらうためのお祭りです。
当社は多岐にわたる事業を展開しているため、社員によってはなかなか他の部署のやっていることを知らないんです。そこで、所属部署や関連部署以外の仕事を知ってもらう機会として、2023年から年に一度開催しています。

ジョブ・フェスティバルを開催することになったきっかけを教えてください。


鎭野
仕事のやりがい調査を毎年実施している中で、「今後、当社でのキャリアを思い描けるか」のスコアに課題があることがわかりました。
また、その後に実施した社員の意見交換でも「グループ内にどんな仕事があるのか知りたい」という要望が多く寄せられました。そこで、まずは社員に「出光を知る」機会をつくることが大事だと考えました。
なるほど。「フェスティバル」というお祭りの形式にしたのはなぜですか?


鎭野
誰もが気兼ねなく足を運べるイベントにしたいと考えたからです。
実は以前、「ジョブフェア」というイベントを開催していました。それは社内の公募型による異動制度である「キャリアチャレンジ」制度と連動したもので、人を募集する部署が応募者を対象に職務を紹介するものでした。
ただ、ジョブフェアだと参加者は異動希望者だけになってしまう。そこで、全社員を対象にした、仕事を知るお祭りにシフトしたんです。
参加者、出展部署が年々増加する理由
2025年のジョブ・フェスティバルは7月の平日に行われたそうですね。どのくらいの社員さんが参加したのでしょうか。


鎭野
2日間で、のべ約1100人の社員が参加しました。
2023年が約500名、2024年が約1000名だったので、参加者は年々増えていますね。
社内イベントとして、すごい規模です!
社員さんはお忙しい方も多いと思うのですが、参加者を増やすために、どんな工夫をしましたか?


鎭野
私がフェスティバルに携わったのは第2回からなのですが、まず運営体制を強化しました。
「社内副業制度」を活用して、ジョブ・フェスティバルに興味のある人を募集し人事部以外の多様な意見を企画に取り入れたり、開催当日の運営に関わってもらったりすることにしたんです。


鎭野
第2回開催時は、広報部や北海道製油所、アスファルトの営業担当の社員が参加してくれました。
北海道の社員は、定例のミーティングはオンラインで参加していましたが、開催当日は会場に来て運営に関わってくれました。
北海道からも参加されたんですね。


鎭野
ほかには広報部に協力してもらい、本社のデジタルサイネージで社内向けに宣伝をしました。
また、社内の上層部からも各部署に参加を呼びかけてもらうなど、社員のジョブ・フェスティバルへの参加を促してもらいました。
多くの方法で呼びかけたんですね。


鎭野
はい。あと、たくさんの部署を回れるように、ブースの配置やレイアウトも大きく変えました。
たとえば、第1回目はテーブルに部署名が記載されたパネルがあり、来場者は椅子に座って、各部署の担当者と向かい合って話すというスタイルでした。
就職活動の合同説明会のようですね。


鎭野
ただ、参加者から「わざわざ座って話を聞くのは、ハードルが高い」という声が多くて。
そこで、第2回からは出展部署がポスターや部署の製品などを掲示する展示会スタイルに変更し、参加者とのコミュニケーションを取りやすくしました。
出展部署も年々増えているのでしょうか?


鎭野
そうですね。
社内の部署や事業所、関係会社合わせて第1回が43、第2回は46、第3回は50の部署と年々増えています。
そんなにたくさんの部署が参加しているんですね!


鎭野
はい、当社は「人が中心の経営」という考え方があり、各部署とも社員の育成に強い想いがある人も多くて。人事の取り組みには積極的に参加してくれる傾向があります。
また、2回目のジョブ・フェスティバルで参加者が大幅に増えて大きな反響があったことも、3回目の参加部署の増加につながっていると思います。
スタンプラリーや展示の魅力度コンテスト。堅くなりがちなイベントだから遊び心を大事に
フェスティバルを盛り上げるために、どんな工夫をしましたか?


鎭野
お祭り感を高めるために、イベントの内容を大幅に見直しました。
第3回では、なるべく多くのブースを回ってもらうためにデジタル形式のスタンプラリーができるオリジナルアプリをつくりました。スタンプの数に応じて粗品をプレゼントしたり。
楽しそう! 遊び心がありますね。


鎭野
あと、来場者に「どの部署のブースが良かったか」を投票してもらい、1~3位までの部署を表彰しました。
どんなブースが上位に入りましたか?


鎭野
2025年の結果は、1位は2年連続でベトナムの関係会社です。アオザイを着た従業員が現地の取り組みを熱心に説明している姿が印象的でしたね。
2位は潤滑油事業です。油が入った水槽に沈めたパソコンが動作するというユニークな展示物が目を引いていましたね。実はサーバーを冷やすのに使われているものなんです。


鎭野
3位はキャリアデザイン部で、社員のキャリア形成を支援する越境学習や研修などを担当する部署です。
キャリアコンサルタント資格を持った社員が、その場でキャリア面談をするコーナーも作っていました。
社内イベントはどうしても堅くなりがちですが、ジョブ・フェスティバルはとても楽しそうなイベントですよね。


鎭野
なるべく社員が気軽に参加してもらうことを考えて、アイデアを出しました。
「景品は、社内カフェテリアで人気のメロンパンにしたらどうかなぁ」とか、社内副業で参加した人もいろいろと意見を出してくれました。
いろいろ考えた結果、今年の景品はお米になりました(笑)。
このご時世、うれしいですね!(笑)

リアルな仕事の話を聞いて、異動を実現した社員も
ジョブ・フェスティバルの参加者からはどんな声が寄せられていますか?


鎭野
アンケートに回答してくれた9割が満足しているという結果でした。
参加者も幅広く、50代以上のベテランの方々からも「若い人向けだと思っていたけど、幅広い年齢層に配慮したイベントだった」という声をもらいました。
社内の部署の紹介だけでなく、松戸市内の学校に週に一度先生としていく「週1先生」という、社員向けの越境プログラムのブースなどがあったのも良かったのではないかと思います。

なるほど。他の部署だけでなく、社内の人事制度などを知る場でもあるのですね。
実際に社内の多様な仕事を知ったことで、異動につながった事例もあるのでしょうか?


鎭野
はい。ジョブ・フェスティバルで実際に話を聞き、キャリアチャレンジに応募した事例も出てきています。
社員が社内の仕事を知り、自分のキャリア考え、実現するきっかけにも繋がっているようです。
ネガティブな意見も受け止め、確実に改善していく
ジョブ・フェスティバル、本当に年々盛り上がっているんですね。
そういうイベントになった秘訣を教えてください。


鎭野
参加する部署や社員がどんなことを求めているかを理解することを大事にしてきたことでしょうか。
前年の結果をしっかり振り返り、課題の改善を積み重ねてきました。たとえば、1回目のアンケート結果では「参加すると『異動を希望しているのか』と思われて参加しづらかった」という声が多くありました。
そこで、ジョブ・フェスティバルの意義が「仕事を知る」ことだと理解してもらうために、先ほどお話したような企画を取り入れ、気軽に参加できるイベントにしました。
アンケート結果から課題を見つけて、それを改善していったんですね。


鎭野
そうですね。
第1回の反省を踏まえて開催した第2回は、想定を超える社員が参加してくれたのは良かったのですが、アンケートでは「人が多すぎて、ゆっくり話ができなかった」という声もありました。


鎭野
真面目に話を聞きたいと思っている人が、にぎわいの隅に追いやられてしまうのはよくないので、第3回は会場を広くし、ゆったりと見たり話したりできるスペースを確保しました。
なるほど。多くの部署が集まる中でバランスを取るのは難しそうですね。


鎭野
多くの人が集まる社内イベントだからこそ、「何のためにやるイベントなのか」という原点に立ち戻ることが一番大事だと思っています。
第2回でお祭りらしい、気軽に参加できる雰囲気は作れましたが、このままでは、ただのお祭り騒ぎだけになってしまうのではないか。イベント本来の目的である、『社内の仕事を知る』が忘れられてしまうのではないか。そういう危機感も持つようになりました。
確かに、伝わらないのはもったいないですよね。


鎭野
そこで、第3回はイベントの目的が『仕事を知ること』であることを改めて強調して、それぞれの部署の「ミッション」「得られる経験」「PRしたいこと」などを記載した冊子を作成しました。
なぜ、冊子を作ろうと思ったのでしょうか?


鎭野
ジョブ・フェスティバルの開催が迫ってくると、各部署がどのような掲示をしようとしているかが分かってきます。
それを見たときに、目立つことを意識してしまい、来場者が「仕事を知る」ための情報が足りていないのではないか、と感じたのです。
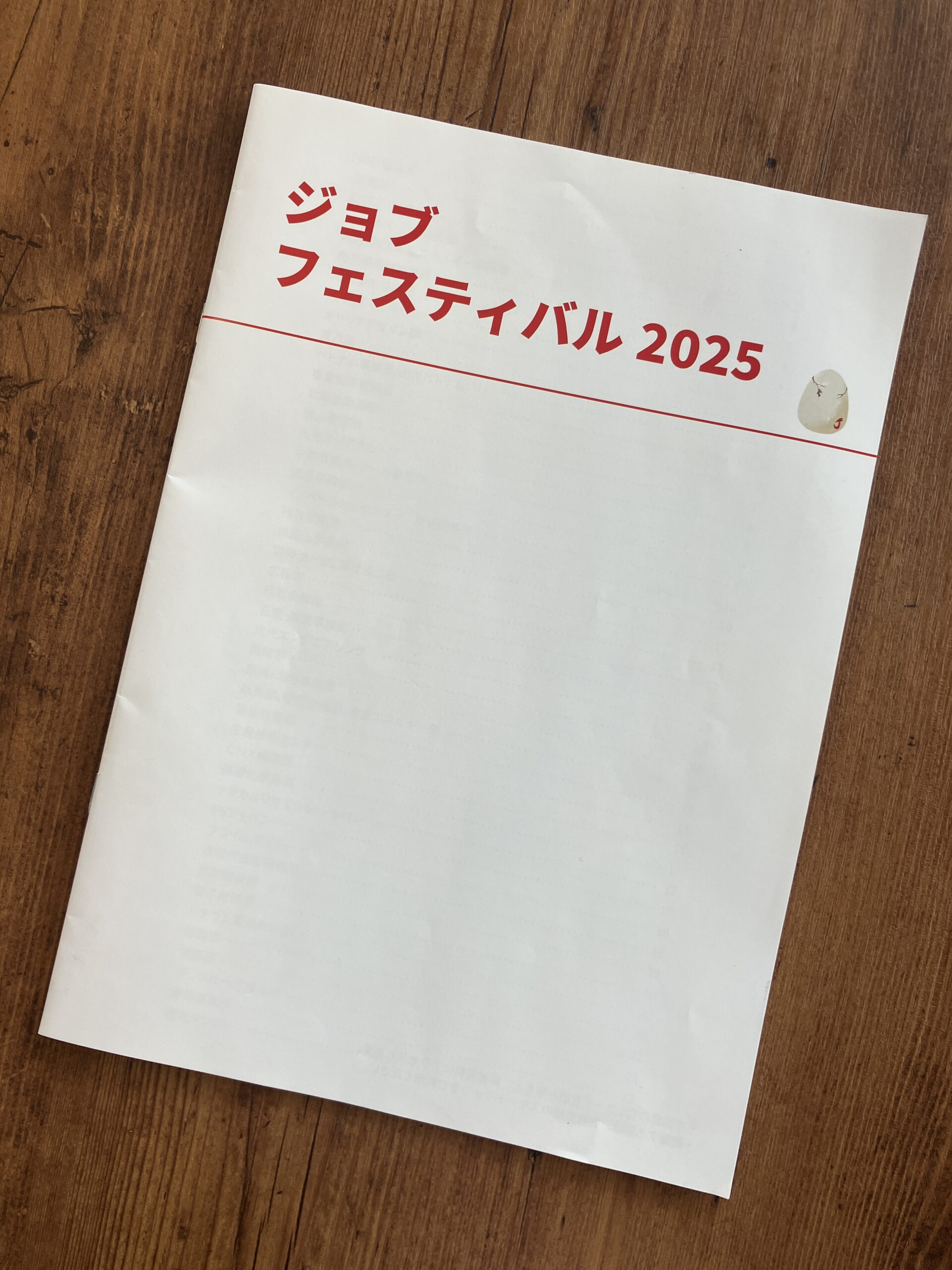
なるほど。運営から見て、来場者に伝えたいことも?


鎭野
はい。もちろん展示には独自性があっていいのですが、イベントとして大事なメッセージは共通化したい。
それで、開催直前ではありましたが、出展部署に働きかけて冊子を作ることを決めました。
多様な仕事があることを知り、キャリアを考える社員の姿も刺激になった
鎭野さんが、ここまでジョブ・フェスティバルをブラッシュアップし続けてこられた原動力は何ですか?


鎭野
私は第1回を開催していた時は人事部にはおらず、参加者の立場でした。
参加者の立場として、第1回は参加しにくい印象も残っていたので、せっかく開催するなら多くの人が参加してもらえるイベントにしたいと思いました。出展部署の人たちも時間をかけて準備しているので、なるべくみんながハッピーになれるイベントにしようと改善を重ねてきました。
ジョブ・フェスティバルに関わったことで、鎭野さん自身の学びはありましたか?


鎭野
これまで自分のキャリアを深く考えたことがなかったのですが、社内に多様な仕事があると改めて知り、いろんなチャレンジができる会社だと感じました。
そして、自身のキャリアをしっかりと考えている社員が多いことにも刺激をもらっています。

出展部署や参加者も含めて、一体感が生まれそうですよね。


鎭野
そうですね。全社向けのイベントを実行するのはとても大変ですが、さまざまな人のアイデアや力を借りると、これだけの規模のイベントが実現できるという気づきもありました。
そして、仕事の一環として、自社をもっと知ってもらう機会をつくる出光興産は、社員想いの会社だと改めて感じています。
自社を肯定的に捉える機会にもなったんですね。
最後に、ジョブ・フェスティバルの今後の展望について教えてください。


鎭野
一定の型はできてきたので、趣旨をぶらさずに次回の企画も考えていきたいです。
遠方や海外拠点などにいて来場しにくい人が参加できるようにオンライン配信は既に行っていますが、より多くの社員が参加して、当社を知るきっかけに繋がるイベントにしていきたいです。
来年のジョブ・フェスティバルはさらに進化しそうですね。今日はありがとうございました!



【編集後記】
社員同士が普段見えない他部署の仕事と出会う、この「お祭り」は、ただ情報を伝える場ではありません。ブースを回る社員の世界を広げ、胸が高鳴る瞬間を与える活動でした。展示やスタンプラリーといった仕掛けも単なる演出ではなく、人が動き、心が動くための橋渡しであり、運営に携わるメンバーのアイデアや創意工夫からもこのイベントが組織内の「生きた営み」であることが伝わってきます。
この熱意と熱気から自分のキャリアに思いを馳せ、「挑戦したい」と小さな変化を起こす。そんな芽が、このフェスティバルから生まれているのだと思います。
(WORK MILL編集長/山田 雄介)
2025年9月取材
取材・執筆=久保佳那
撮影=栃久保誠
編集=鬼頭佳代/ノオト