自分がコントロールできることへ集中する。「他者をただ羨む」をやめよう(澤円)
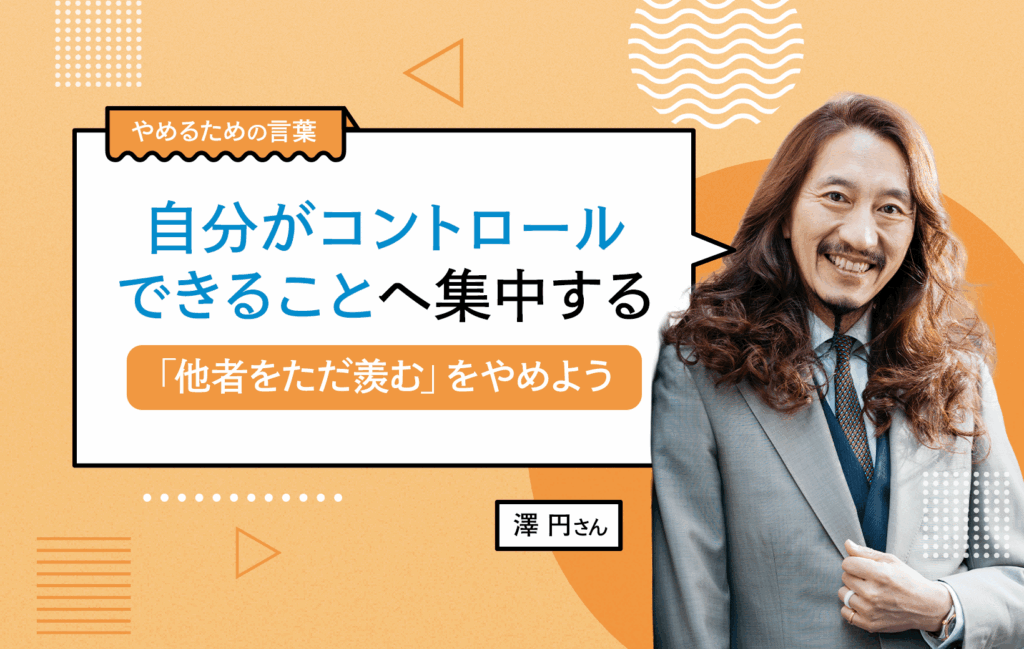
仕事でもプライベートでも、やりたいことは山のようにある。同時に、周りからのいろいろな頼まれごとにも向き合っていくと、いつの間にか予定はいつもパンパンに。この働き方、暮らし方は思っていたのと、ちょっと違う気がする……。そんなときに必要なのは、こだわりや常識、思い込みを手放すことなのかもしれません。連載「やめるための言葉」では、圓窓代表取締役・澤円さんと一緒に「やめること」について考えていきます。
SNSは「羨ましい」を増殖させた
2022年の成蹊大学の研究論文によると、Instagram利用者は非利用者より社会的比較志向が高い傾向があり、承認欲求との関連も報告されているそうです。
この論文の内容をChatGPTで要約すると以下のようになります。
この論文は、大学生184名を対象にInstagram利用と幸福度の関係を調査したものです。利用者は非利用者に比べて社会的比較志向と賞賛獲得欲求が高く、他者の投稿を見て羨望や落ち込みを感じやすい傾向が確認されました。
一方で「いいね!」を多く得ると大きな喜びを感じるなど、承認欲求がポジティブ体験にもつながることが示されました。
つまり、社会的比較は感情的幸福度を、承認欲求は人生満足度を左右する要因となり、両者が複雑に幸福感に影響を与えると結論づけています。
Instagramの利用と幸福度の関係における社会的比較と承認欲求の影響(新井 学/成城・経済研究 第235号(2022年2月))
うん、これは納得感ありますね。SNSは、羨ましさを増幅させる機能を持っており、増幅された羨ましいと思う気持ちに振り回される人が増えているんじゃないかな……と常々思っています。
ボク自身も「わー、この人こんな車買ったんだ〜、いいな〜」とか「ヘ〜〜、こんなイベントに招待されたんだ、すげーなー」と思うことはあります。
SNSは、人生の「ハレの部分」をしっかり切り取って拡散することができるので、羨ましいと思う人が爆増するのは、実に自然なことであると言えます。
逆に「羨ましい」という気持ちは、うまく利用すれば強烈なマーケティングメッセージにもなります。
美味しいごはんを食べたいでしょ?
いいところに住みたいと思わない?
素敵な人と出会いたいですよね!
こんな欲求を刺激するのが、SNSの大きな特徴でもあります。
キラキラした時間だけで生きてる人っている?
SNSの発展とともに、インフルエンサーという職業が定着しました。インフルエンサーは、SNSというプラットフォームを最大限活用して、多くの「いいね!」を集め、結果的に投げ銭を得たり商品購買をサポートしたりして、企業などから報酬を得ている方々です。
ボク自身、いわゆる「案件」と呼ばれるSNSマーケティングを何度もお手伝いさせていただいているので、大した影響力はないにせよ「インフルエンサー的な振る舞い」については体験させてもらいました。
ちょっと贅沢な体験をさせてもらったり、高価なものに触れさせてもらったりして、その情報をSNSで発信するのは、なかなか楽しいものでした。その上で感じたことなのですが、SNSは人生の一部分を切り取ったに過ぎず、全てがキラキラしているわけではないという当たり前の事実です。
贅沢体験もずっと続くわけではないですし、借りたものは返さなくちゃいけない。
本当に財力があったり社会的地位が高い人たちは、他人が羨ましく思うような情報を発信するより、自分が求められている役割……経営だったり、スポーツや音楽などのパフォーマンスだったり……をまっとうすることの方がずっと大事であると認識しているように思います。
もちろん、例外的にやたらと自慢げな情報を発信する人もいなくはないですけれど、そういう人たちもその成功を得るまでには相当な努力をしたことを考えれば、「まぁいいか」って気分になります。
SNSは、様々な情報の増幅装置である側面があります。キラキラした瞬間を切り取って増幅させるのは、SNSの最も得意な領域であると言えます。
その情報を「あくまでも増幅されたものである」と理解することが、現代人が心健やかに生きるためには大事なことだと言えるでしょう。
自分の人生を生きるという原理原則に戻ろう
さて、SNSのように「ネットの向こう側」の人たちではなく、身近な人に対して「羨ましい」って思うこともありますよね。
ボク自身、めちゃくちゃこれはしんどい思いをしました。まず、20代から30代前半にかけて、仕事の能力について周囲の人を羨ましいと思いまくっていました。
ボクは文系出身でシステムエンジニアになったので、学生時代からコンピュータに慣れ親しんでいる人たちと比べると、スタート時点で差がありました。おまけに、そもそも賢くもないので仕事の覚えが悪い。
さらには間違ってマイクロソフトという業界トップの会社に入っちゃったもんだから、その無能さは際立ってしまったんですよね。
外資系ということで英語にも悩まされました。英語もペラペラ、コンピュータの知識も十分、なんていう同僚を羨ましいと思わないわけがありません。
また、お金に関しても羨ましいと思うことがありました。Windows95の登場前後にマイクロソフトの株が一気に高騰したこともあり、ストックオプションで巨額の収入を得ている人がゴロゴロいました。
ボクが入社したのは1997年だったのですが、入社してからしばらくストックオプションをもらえなかったので、株価高騰の恩恵に預かることはありませんでした。机を並べて同じ仕事をしているけれど、入社年次が違うだけで所有財産に大きな差があるのは、仕方がないこととはいえ非常に羨ましい気持ちになったものです。
ただ、ボクがラッキーだったのはお客さんに恵まれたことです。お客さんがボクのことを信頼してくださったことで、仕事に必死に打ち込むことができ、不器用ながらも結果を出すことができました。
おそらく、周りを羨ましがってる暇がないくらいに必死に仕事と向き合うことができたので、いつの間にやらそれなりの評価を得られるようになったのではないかと思います。
2006年には、Chairman’s Awardというマイクロソフトの中では最高の賞が与えられたりして、なかなか幸せなサラリーマン人生を送ることができました。
運に恵まれたこともあるのですが、まず「自分がコントロールできることに集中する」ということが実践できたのは大きかったと思います。
文系出身で前提知識がないことも、入社年次が株価高騰の後だったことも、コントロールしようがない事実です。
だから、自分がコントロールできること……目の前の仕事に必死に取り組み、顧客に対して提供する価値を最大化することに注力する。地味ですけど結局これが一番効果的なんですよね。
近道なんかないからひたすらできることをやる。必死になってやる。そうすることで、羨ましいと思う気持ちが相対的に小さくなり、結局自分にとってプラスになることが起きやすくなるんじゃないかと思います。
幸運の分配は平等ではないかもしれませんが、自分のことに集中するというのは意思次第で誰でもできるとボクは思います。自分の人生を生きる、という原理原則こそが、幸運を引き寄せる引力になるのではないでしょうか。
アイキャッチ制作=サンノ
編集=ノオト




