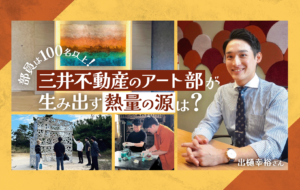仲良くなる仕組みはどうつくる?——OSIROが「かきまぜる」コミュニティの現在地(オシロ株式会社・杉山博一さん)

OSIRO(オシロ)は、クリエイターやブランドだけでなく、企業や組織の社内コミュニティやチームビルディングにも活用されている、コミュニティ形成のためのプラットフォームです。
サービスを運営するオシロ株式会社・代表の杉山博一さんは、アーティストとしての経験やフリーランス時代の孤独を通じて、活動を続けるためにはファン同士が応援し合える場と、そこで交流を生み、仲良くなれる仕組みが必要だと感じたそう。
月額制のコミュニティ運営や、ポイント制度・関心の可視化といった仕組みを通じて、感情の共有に基づく交流やチームづくりを後押しするOSIRO。このサービスが生まれた背景や、現代ならではの活用法、今後の展望について杉山さんに伺いました。
クリエイターや会社をコミュニティの力で支える「OSIRO」
コミュニティづくりをサポートするプラットフォーム「OSIRO」について教えてください。


杉山
OSIROは、熱量の高いファンやメンバーが集い、クリエイティブな活動を支えるオンラインプラットフォームです。
もともとは個人のクリエイター向けに開発したものですが、現在ではブランドや企業の中でも利用が広がっています。
コミュニティ運営に必要な決済システムやEC機能だけでなく、デザインのカスタマイズやポイント制度、興味関心のシェア機能など、さまざまな工夫がほどこされていますね。


杉山
ほとんどのコミュニティは月額会費制を採用しており、クリエイターや運営者にとって安定した収益基盤になります。
また、ブランドや企業にとっては、OSIROの機能を使うことで、日常ではなかなか聞けないメンバーの本音やリアルなインサイトが得られる点にも大きな価値があります。
クローズドだからこそ、より本音で語り合える密度の高いコミュニティが生まれているのですね。


杉山
そうですね。「人と人が仲良くなる」ことは、2015年のβ版ローンチ以来、OSIROの根底にある価値観です。
だからこそ、OSIROは単なる月額課金の支援サービスではなく、コミュニティの参加者同士がつながり合い、「応援団」として機能することを重視しています。

なるほど、応援団!
お金だけでなく、エールも届けるイメージが伝わります。


杉山
コミュニティのオーナーが一方的に発信するだけでなく、参加者同士が意見交換をしたり、イベントを企画してリアルに集まったり。
OSIROはもともとは個人のクリエイター向けに開発したものですが、「人と人が仲良くなる」ための仕組みは、最近では企業の社内コミュニケーションへも広がっています。
「クリエイター向け」というイメージが強かったので意外です!
企業ではどのように活用されているのでしょうか?


杉山
特に多いのは、M&Aや多様な雇用形態のチームビルディングの際に、「互いを知るきっかけ」として導入を検討いただくケースですね。
たとえば、大規模な会社内での交流や会社の合併後に新しいチームが生まれる場面など、バックグラウンドの異なる人たちが集まる現場でもOSIROが活躍しています。
アーティストとしての挫折と天命
OSIROの発想はどこから生まれたのでしょうか?


杉山
僕はもともと、世界一周から帰ってきた24歳から30歳まで、絵を描いて暮らしていました。
デザインの仕事と並行して活動していましたが、結局アートだけでは生計を立てられず、30歳でアーティストとしての道を諦めることになりました。
その後、32歳で会社を立ち上げるまで、仕事もずっとフリーランス。上司も同僚も部下もいない、本当に孤独な日々を8年間過ごしました。
それは長い期間ですね……。


杉山
どんなに好きで始めたことでも、孤独が長引けば心身に影響が出るものです。
今思えば、誰ともつながれない状態がある限り、金銭的な余裕があったとしても創作活動は続けられなかったと思います。


杉山
SNSのフォロワーが何万人必要だ、といった問題ではありません。
たとえ人数は少なくても、自分を応援してくれる人たちの存在を実感することが、創作活動を続ける条件だと身をもって実感しました。
強い原体験ですね。


杉山
その後、32歳のとき、金融系のスタートアップを立ち上げました。アメリカでは一般的になりつつあった仕組みでしたが、日本でも根付かせることに意義を感じていました。お金のことはプロに任せて、より多くの人が文化や創作を楽しむ時間を持てたら良いと思ったからです。
会社が軌道に乗ったタイミングで、住みやすさに惹かれてニュージーランドで暮らすことを考え始めました。実際に移住の準備も進めていたのですが、ある日、ニュージーランド行きの飛行機に乗れないという出来事が起きたんです。
あまりに突然の出来事ですね。


杉山
はい。でも、僕はそれを「まだニュージーランドでリタイアする時期じゃない」というメッセージだと受け止めたんです。
自分が諦めてしまった芸術の道。けれど、「日本を芸術文化大国にする」ことが自分の天命であり、そのために生かされてきたのだと考えるようになりました。
それで、かつて自分が挫折してしまった経験から、日本という国で「応援団」や「コミュニティ」の仕組みをつくる発想が生まれていった。


杉山
僕自身もアートを諦めた経験がありますし、今も多くの人が活動を続けられずにいる。でも、クリエイターを応援したい人は必ずいます。
そうした人たちがバラバラではなく、エールを送り合う「応援団」としてつながれば、クリエイターはもっと活動を続けていけるはず。お金もエールも継続的に循環する仕組みをつくりたいと考えた結果、OSIROが生まれました。
感情を共有するためのコミュニティ機能
クリエイター支援のために始まったOSIROですが、杉山さんたち自身も社内のコミュニケーションに活用しているそうですね。具体的な使い方を教えていただけますか?


杉山
OSIROには多くの機能があるのですが、「フロー」と「ストック」の違いを意識しています。
たとえば、雑談ルームは24時間で自動的に消える仕組みになっていて、気軽に書き込める雰囲気があります。


杉山
社内報もコミュニティ内に書いているのですが、社員が「いいね」やコメントでリアクションしてくれる。社員の日報も全員が読める形で共有しているのですが、これがすごく盛り上がるんです。
日報が盛り上がる会社はなかなか珍しいですね。社内コミュニティを盛り上げるために、工夫しているポイントがあるのでしょうか?


杉山
今は「Touch the Art(芸術給)」という仕組みを設けていて、社員は毎月3万円まで、展示やイベント、ファッションなど、自分の興味があるアート体験に自由に使えるんです。その体験から感じたことを、社内コミュニティ内のレポートで発信してもらうようにしています。
そうすると、お互いの価値観や「どんなことに心が動くのか」が見えてきて、自然とコミュニケーションが生まれるんです。
それは嬉しい仕組みですね。普段の仕事だけではわからない、その人の趣味趣向が可視化されるのですね。


杉山
日報以外にも、真面目なビジネス分析からジェラート好きの集まりまで、幅広い「部活動」がありますし、社員自身が企画して実施する「イベント」も盛んです。


杉山
スタンプでのリアクションやテキストと吹き出しを一緒に送る機能なども特徴的で、オンライン上でも感情共有がしやすい工夫を施しています。


杉山
私たちは、情報を共有する以上に、感情を共有したほうが仲良くなれる。OSIROは人と人が仲良くなるために、感情を共有するツールでもあるんです。
仕事場から失われたコミュニケーションをどう代替するか?
OSIROは企業内のコミュニケーションツールとしても広がっているそうですね。会社の中で、これまでのように自然と仲良くなることは難しくなっているのでしょうか。


杉山
そうですね。以前は飲み会や社員旅行、運動会など職場のB面とも言える「仕事以外の場」がありました。他にも、飲み会やタバコ部屋、麻雀などもそれに近いですよね。
しかし、時代の変化とともにそうした場や行事が減っていき、B面の時間によって築かれていた人と人との関係もなくなっていきます。


杉山
さらに組織が大きくなったり、リモートワークが進んだりすると、ただ同じ会社にいるだけでは仲良くなりづらくなっています。
確かに、最近よく聞く悩みです。


杉山
ある調査によれば、人が知り合いになるまでに50時間、友達になるまでに90時間、親友になるまでには200時間が必要と言われています。
社会全体で個人が尊重されるようになり、リモートワークも普及して、関わりを持たなくても良い場面が増えてきましたね。
町内会などの地域コミュニティでも同じ傾向を感じます。


杉山
かつては会社の制度によって担保されていた、仕事以外の「B面」のつながりを、OSIROは趣味や興味を通じて補完しようとしています。
仕事と関係のないきっかけで生まれた関係性でも、仲良くなることでコミュニケーションが円滑になったり、会社のクリエイティブな力を後押ししたりと、結果的に「A面」にもポジティブな影響が広がるんです。
なるほど。しかし、企業や団体でコミュニティをつくるのは簡単ではなさそうです。


杉山
おっしゃる通りです。ただツールを導入するだけで自然にコミュニティが盛り上がることはありません。実際に使ってもらうには、投稿を促す仕組みや運用ルールの設計が欠かせません。
具体的には、マインドセット・制度・ツールの三つが揃って、はじめてコミュニティは動きます。マインドセットについては、チームが「安心・安全な場所」だと感じてもらうための研修も用意しています。


杉山
その上で、OSIROというツールを最大限に活用するためには、たとえば「芸術給」のような制度でお互いの人となりを共有するきっかけをつくる必要があります。
こうした「仲良くなるための仕掛け」を考えてもらうよう、企業さんにはお声がけしています。
安心して参加できる場と、自然と投稿したくなるような仕掛け。この両方がそろって、初めて感情が共有され、コミュニティとして仲良くなっていくのですね。

求められるのは「ギリギリのおせっかい」と「かきまぜる力」
コミュニティがうまく回るために、OSIROではどんな考え方や工夫を大事にしていますか?


杉山
人が仲良くなるきっかけをどう生み出すかを意識しています。
たとえば、コミュニティのメンバーが何に興味を持っているかをテキストマイニングで分析したり、趣味が合う人同士でバディを組んだり、ポイント制度を使って関わりを生み出したりと、新しい技術も取り入れています。
なるほど。


杉山
昔はこうした「人つなぎ」や「かきまぜ役」を、地域のおせっかいな人やお店の人が担っていましたよね。
今はそういう存在が減っていて、むしろ珍しいくらいです。
世話焼きな親戚や、仲人のような人たちを想像しました。時代によっては、少し煙たがられてしまうのかもしれません。


杉山
僕は「おせっかいのギリギリを攻める」という言い方をよくしています。人と人が仲良くなるためには、コミュニティを適度に「かきまぜる」役割が必要なんです。
技術もうまく活かしつつ、ちょうどいい塩梅でおせっかいを設計する。それが、今の時代のコミュニティには必要だと思っています。
今の時代に即した、応援団をつくるための「かきまぜ役」や「おせっかい焼き」は、これからどんどん重要になっていきそうですね。
最後に、今後のOSIROが目指す方向やミッションについて教えてください。


杉山
OSIROは、まだ理想の形にはなっていませんが、「人と人が仲良くなる仕組み」として少しずつ手応えを感じてきました。コミュニティをうまく「かきまぜる」ことは、創造性やウェルビーイングにもつながると実感しています。
今後は海外展開も視野に、「日本を芸術文化大国にする」という思いで活動を続けていければと思います。

2025年6月取材
取材・執筆=淺野義弘
写真=小野奈那子
編集=鬼頭佳代(ノオト)