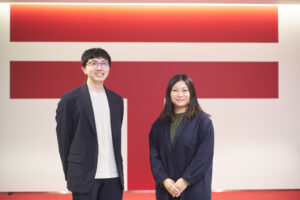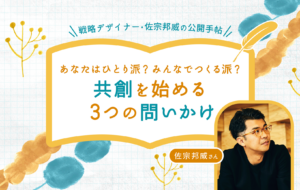遠回りこそが共創の本質。実践者が考える「時間」のもつ価値(共創プロセスデザイナー・有福英幸×WORK MILL コミュニティマネージャー・岡本栄理対談・前編)

「会社で共創活動の担当部署の配属になったけど、何から始めたらいいかわからない」
「共創空間が新設されたけど、どう活用すればいいんだろう?」
株式会社フューチャーセッションズ代表・有福さんは、共創プロセスデザイナーとして、10年以上さまざまな企業や地域の共創をサポートしてきました。
オカムラの共創空間づくりをサポートした有福さんと、オカムラでWORK MILL コミュニティマネージャーを務める岡本栄理さんが対談し、共創について深掘りします。前編では、共創空間を作り上げた経緯や昨今の共創で感じるトレンドについて語りました。
大阪の共創空間beeでの出会い

岡本
2017年、私はオカムラが大阪で運営する共創空間「Open Innovation Biotope “bee”」のコミュニティマネージャーのリーダーに指名されました。
それまでの私は経理や営業アシスタント、秘書というバックオフィス担当だったんです。なのに突然、「次は、『働く』についての共創を担当して」と言われて。「共創って何!?」と素人の状態から始まりました。


岡本
そんな私にゼロから伴走してくださったのが、有福さんだったんです。だから、今日は対談ができて嬉しいです。
そうでしたね。当時、私は名古屋にできたCue(共創空間 Open Innovation Biotope “Cue”)でフラッグシップになるようなイベントを定期開催していて。
共創においては、ワークショップやイベントも大切な要素ですから。それで、「大阪もお願いします!」とお声掛けいただいたんです。

有福


岡本
当時は有福さんたちがイベントでされていたファシリテーションが、特殊な能力に見えていましたね。引き出す力やまとめる力が必要で……。
「そういう力はセミナー形式で学ぶだけでは身に付かないから、一緒にイベントの現場を作りましょう」とご提案いただいて。それがすごく学びになりました。
我々がリードするというよりは、皆で作っていきましたね。

有福

岡本
働くに関するイベントをつくると言っても企画をしたことがないので何から始めていいかわからない……。
そんな頃、有福さんから「自分の持っているモヤモヤをそのままイベントにしたらいいんですよ」と言っていただいて、すごく安心したのを覚えています。


岡本
でも、壁にぶつかったこともあって。私がイベントでファシリテーションをしていた時、場が固まってしまったんです。
職場で女性が担うことが多かった「お茶くみ」に対する違和感を取り上げたら、年配の参加者さんの1人が声を荒げてしまったことがあって。そこに、世代による価値観の違いがあったんですよね。
ほかの出席者の方がフォローしてくださったんですけど、私も動揺してしまいました。
「お茶くみ」という言葉1つとっても、人によって受け取り方が全然違うんですよね。
テーマ設定や問いかけは、ファシリテーションで気を使う部分です。

有福

岡本
そうなんです。その時は参加者それぞれで話し合いをする場を設けて、「私たちの世代ではお茶くみに違和感があるけど、世代によって違うまなざしがあることがわかった」とお伝えしたんです。
最終的にその参加者とも和解して、穏やかな場に戻りました。価値観が違うことを共有することで、新しい気付きがあるんだとわかった瞬間でしたね。
相対する人とどう向き合うかは非常に大事です。
場が凍ってしまっても乗り越えなきゃいけないこともあると思いますよ。

有福

岡本
本当にそうですね。私は、「和して同ぜず」という言葉が好きなんです。「協力しながらも主体性を失わない」という意味があるんですけど。
違う価値観があるから話し合う意味があるし、違う人の意見を聞いて自分の視野が広がることもある。いろんな人が思いをはせる場で、そういう仕掛けを作るのが大事ですね。
あのイベントで、他の企業の参加者さんたちをケアしてつながりを作っていく姿が、岡本さんらしかったです。まさに自分をハブにして、いろんな人とつながる体験だったのではないでしょうか。
参加者にとっても、オカムラの共創空間が「共創体験空間」として活用されていたことが伝わってきました。

有福

岡本
ありがとうございます。まさに対話で価値観を共有し合う、共創の原体験となりました。
私は、2012年から「多様なステークホルダー同士がソーシャルイノベーションを起こす手段」として共創に携わっています。
ただ、やっぱりどの企業や組織も最初はやり方がわからなくて戸惑うんですよ。

有福

岡本
共創の本質を理解することが難しいんですよね。
はい。でも、共創はプロセスをしっかりと作ればだれでも再現可能なんです。
私自身、共創プロセスデザイナーとして岡本さんを約2年間フォローして、改めてプロセスの大切さを体感できたなと思いました。

有福
コロナ禍以降、企業の間で流行する「共創」

岡本
私が共創に携わりはじめたのは2017年。振り返ってみると、今までにいろいろな変化がありましたよね。
特に、コロナ禍ではリアルでの対話が世の中で希薄になり、一度盛り下がってしまって。大阪のbeeでは「コロナ禍でも共創を止めるな」という想いからオンラインでイベントを開催していました。
.png)

岡本
その後の2023年、私は東京の共創空間Open Innovation Biotope “Sea”へ異動をしました。
最近は、「作業は自宅で、オフィスでは人と交流する場・共創の場にしていこう」という文脈でオフィスに共創空間を作るご相談をいただくことも多くて。
コロナ以前のように、共創の波がもう一度来ている実感があります。有福さんの方はいかがですか?

実は、私自身はあまり共創の波を感じてないんですよ。

有福

岡本
そうなんですか!
けれど、共創が盛り上がる要因はなんとなく理解できます。
共創って何かが生まれる雰囲気を醸し出せる。それで、新規事業や組織・風土改革といった企業の課題に、一歩踏み出せる願いを込めているんでしょう。
でも、本質的に共創ができているところは少ないと思いますよ。「ただ集まって、ワイワイすれば何かできる」という意識が最近の共創にはあるような気がします。

有福

岡本
同感です。共創って、体験した上で培われる知見とマインドが必要ですよね。
そうです。本当の共創って生産性が悪くて泥臭いんですよ。でも、共創にも効率性を求めるようになっているんじゃないでしょうか。
企業が効率性や生産性を高めて短期的な成果を生み出す手段として共創を使うと、相反するんじゃないかな。

有福
共創の成果は急がば回れ

岡本
振り返ってみると、コロナ禍前のワークショップは3時間半くらい行うのが一般的でしたね。
けれど最近は、長くても2時間くらいになってきました。
これも共創に効率を求めたから起きたことですよね。効率よくやろうとすると、60~90分と短いワークショップになりがちです。それも共創の質が落ちた要因の一つでしょう。
コロナ禍以降、リアルの場での3時間の確保が難しくなっているんです。

有福

岡本
正直、参加者さんの気持ちはわかりますよね。
オンラインセミナーも乱立していますけど、録画で倍速視聴する傾向がある。「効率よく量をこなす」消費する方に傾いているんですよ。
本当は、目的を持たずに6時間対話することに価値があるんですけど。

有福


岡本
そう。
その時間をともに過ごしたという経験を通じて、特別な関係を築けるんですよね。
共創の本質は、まさに共に過ごした楽しさとか、ワクワクすることにありますから。
共創を、長く続けることで社員が生き生きと働ける。その結果として、何かが生まれてくる。それが共創の価値です。
もちろん巡り巡って事業の効率が良くなることもあるとは思いますが、それを目的に共創をするのはちょっと違うんじゃいないかと思っています。

有福

岡本
共創の本質的な部分って本当に効率が悪いし、お金になりにくい。
けれど振り返ると、「結果的に色々できている」というのが共創だなと感じます。長い目で見たら最短ルートなんですよね。急がば回れというか。
組織として、共創に時間やお金をかけるなら、新規事業のアイデアとかわかりやすい短期的な成果を出さないといけないと思いがちです。
でも、実はそこが正解じゃないんです。社員同士の関係性がよくなったり、会社以外の人とネットワークを作ったり、その結果として離職率が下がったり。
社員がやりがいを持って前向きに働ける副次的な効果が、共創にはたくさんあるんですよね。

有福

(後編に続く)
2025年1月取材
取材・執筆=ゆきどっぐ
撮影=栃久保誠
編集=鬼頭佳代/ノオト